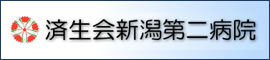『新潟ロービジョン研究会2010』 1)特別講演
テーマ:「『見えない』を『見える』に」
日時:平成22年7月17日(土) 14時~18時20分
場所:済生会新潟第二病院 10階会議室
1)「前進する網膜変性の治療」
山本 修一 (千葉大学大学院医学研究院眼科学教授/
日本網膜色素変性症協会副会長)
2)「ロービジョンで見えるようになる」
小田 浩一 (東京女子大学人間科学科教授)
3)「障がい者が支援機器を活用できる社会に」
林 豊彦 (新潟大学工学部福祉人間工学科・教授)
【特別講演】 1
「前進する網膜変性の治療」
山本 修一
千葉大学大学院医学研究院眼科学教授
日本網膜色素変性症協会副会長
網膜色素変性を代表とする網膜変性疾患は、長らく「不治の病」とされてきたが、最近の研究の急速な進歩により、臨床応用間近になりつつある。
1.網膜色素変性治療の方向性
1)遺伝子治療:遺伝子異常によって生じる網膜色素変性では、本質的治療と考えられるが、既知の遺伝子異常が少ない。また発症初期に治療を開始する必要がある。
2)神経保護:網膜色素変性の本質的治療ではないが、視機能の延命が目的。
3)人工網膜:視細胞が消滅した場合には、人工網膜か網膜移植が適応となる。
4)網膜再生・移植:網膜の再構築が最終目的であるが、まだ道は遠い。
2.レーベル先天盲における遺伝子治療
1)レーベル先天盲はRPE65遺伝子の欠損が原因であり、幼少期から重度の視力障害、眼振を生じる。イヌの実験モデルを対象に、アデノウイルスに正常遺伝子を結合させ網膜下に注入したところ視機能の改善がみられた。
2)初期の第1相臨床試験は米英の施設で、年齢の高い症例を対象に、安全性確認のために行われた。硝子体手術を行い、ウイルスベクターを網膜下に注入した。黄斑円孔などの手術関連合併症はあるが、ウイルス関連の合併症はみられなかった。視力、網膜感度、薄暮下での行動改善が得られ、この結果は米国の3大ネットワークや英国BBCのニュースで大々的に報じられた。
3)現在は第2相臨床試験が米英の施設で31例に施行中で、最長2.5年の経過観察が行われている。全例で視機能の改善がみられ、視野の拡大、ウイルス注入部分の網膜感度の改善、補助具なしで字を読む、すたすた歩く、などの効果が得られている。
4)遺伝子治療の展望:遺伝子治療を行うには、原因遺伝子の特定が必須である。また視機能の改善を得るには、比較的発症早期に治療に取りかかる必要がある。また優性遺伝では、異常遺伝子の働きを停止させる必要があり、干渉RNAによる臨床試験が計画されている。
3.毛様体神経栄養因子による神経保護
1)毛様体神経栄養因子(CNTF)は13種類の網膜変性モデルマウスで網膜保護効果が得られており、原因となる遺伝子異常に無関係に保護効果を示す。CNTFを作るように遺伝子操作したヒトの網膜色素上皮細胞を特殊なカプセルに入れ、このカプセルを眼内に埋植する。カプセルからはCNFTだけが放出され、細胞に対する免疫反応も起こらない。
2)安全性を確認するための第1相臨床試験は、10名の網膜色素変性を対象に6ヶ月間行われた。合併症はみられず、視機能が改善する症例もみられた。
3)現在は第2相試験が133例の網膜色素変性を対象に米国と欧州で進行中。視力、視野、網膜電図(ERG)などの視機能の改善はみられていないが、OCTで視細胞核厚の増加や、AO-SLOで錐体密度の減少の抑制がみられている。萎縮型加齢黄斑変性に対する臨床試験も並行して行われており、視力の維持や網膜厚の増加が観察されている。
4.ウノプロストン点眼による神経保護
1)0.12%ウノプロストンはすでに緑内障点眼薬として長い歴史があり、ヒトで点眼によりエンドセリン1の抑制を介して、脈絡膜血流を増やす。ラット光障害モデルでは、硝子体内投与で視細胞の変性が抑制される。
2)千葉大で30名の網膜色素変性患者を対象に予備試験施行。半年間点眼により、平均視力は若干低下したが、中心部の網膜感度は有意に上昇した。
3)千葉大でのパイロットスタディの結果を受けて、0.15%オキュセバ点眼の無作為二重盲検試験を全国6施設で109名が参加して施行された。プラセボ、一回1滴点眼、一回2滴点眼の3群に無作為に分割。網膜感度の悪化は、プラセボ群21.2%に対し、2滴群は2.6%で有意に抑制された。この他に、視覚関連QOLの有意な改善もみられた。今後は早期の承認を目指す。
略歴
1983年 千葉大学医学部卒業
1989年 富山医科薬科大学眼科講師
1990年 米国コロンビア大学眼研究所研究員
1994年 富山医科薬科大学眼科助教授
1997年 東邦大学佐倉病院眼科助教授
2001年 東邦大学佐倉病院眼科教授
2003年 千葉大学大学院医学研究院眼科学教授
2007年 千葉大学病院副病院長、日本網膜色素変性症協会副会長
=============================
【特別講演】 2
「ロービジョンで見えるようになる」
小田 浩一
東京女子大学人間科学科教授
昨年2009年の日本眼科医会では、ロービジョンの人口は144万人、視覚障害全体で164万人、その経済損失効果は年間約9兆円にもなり、ロービジョンが社会に与えるインパクトは小さくないという報告がなされた。ロービジョンが社会に与えるインパクトが小さくないわりには、ロービジョンという問題はあまり知られていない。一般の人がロービジョンという概念を受け入れるのに時間がかかっているのにはいろいろな理由があるだろうが、キラーアプリがないこと、これという核になる売りがないからではないのだろうか。
ロービジョンという言葉は、見えないことの代名詞であり、障害者というレッテルを貼られることを意味し、持ちたくもない白杖をもたされることを意味している。一般の人から見れば、視覚障害福祉といえば点字の情報サービスや、点字ブロックなどの誘導サービスということになるだろうが、多くのロービジョンの人からすれば点字も点字ブロックもあまり有効なサービスとは言えない。ロービジョン外来に行ったところで、虫眼鏡や安い便利グッズを紹介されて、好きなものを貸出してくれるだけで、見えるようになるわけでもないということになっていないだろうか。虫眼鏡なら文房具屋でも売っているし、100円ショップで便利グッズを探す事ができる。高度な他の眼科医療サービスと比べて、ロービジョン(ケア)は非常に素人っぽい、専門性の低いサービスとして患者の目には映るはずである。こういう状態ではロービジョン(外来)にまた行こうとは思わないし、たいしたサービスも恩恵もないのに障害者のラベルを貼られるのは御免だと思うのはごく自然なことと思われる。
では、これまで眼科の治療でも見えるようにはならなかったのが、眼科でロービジョン(ケア)というのをしてもらうと見えるようになるらしいよということになればどうだろうか?眼科に来る患者さんは、自分の目の視力がどのくらいだとか、視野がどれくらいだとかは知らないけれど、たいてい何か大事なものが読めなくて困難を経験している。それが患者にとっての「見えない」ということの意味である。眼科医療では、視力がいくつで治療できない病気の状態だという専門的な診断で終わってしまうような場合もあるだろう。言い換えれば、これまでの眼科の治療では「見えない」ままだということになる。一方、ロービジョンの専門家は、多くの場合、拡大鏡1つきっちり処方すれば患者さんは読めるようになることを知っている。きっちりした処方とは、多種多様な虫眼鏡を紹介することとは違う。読めるようになる適切な拡大鏡はこれだとフィッティングするのである。眼鏡処方と良く似ている(ロービジョンの眼鏡処方も通常の場合とは異なり専門性が必要になる。なぜなら、患者はもともと視力が低かったり使える視野が狭かったりして、自覚的に良く見える方を応えるのが困難だからである)。
ロービジョン(ケア)で読めない困難が解消すれば、患者からすれば「見える」ようになったということになる。これまでの医療では視力が低いままで病気が治らなくても、ロービジョン(ケア)という新しい医療では患者が「見える」ようになって帰って行く。これは、一般人の言葉では治る、見えるようになるということだろう。屈折異常は治療しないで眼鏡で見えるようにするというのと基本的に同じ発想だ。実際には視力があがるわけでもないが、患者さんには眼鏡で0.01から1.0に見えるようになったという印象を与えている。もちろん、それだけですまない人もあり、さまざまなサービスや他の補助具への橋渡しも非常に重要だが、コアになるポジティヴな概念=「ロービジョンで見えるようになる」ことが重要であるように思える。
略歴
1984年 東京大学大学院人文科学研究科・博士課程(実験心理学)中退
1984年 国立特殊教育総合研究所・視覚障害教育研究部・研究員
1987年 NYU心理学部へ在外研究員
1992年 東京女子大学・コミュニケーション学科・専任講師
1994年 同助教授
2001年 同教授
=============================
【特別講演】 3
「障がい者が支援機器を活用できる社会に」
林 豊彦
新潟大学 自然科学系 教授
工学部福祉人間工学科/
大学院自然科学研究科・電気情報工学専攻
新潟市障がい者ITサポートセンター長
視覚障がい者であってもパソコンを使用し、テキストデータであれば文字を音声化ソフトで読むことができる。携帯電話を使用すれば、インターネット接続によって文字・画像を送ることができる。電子情報通信技術は、障がい者の「不可能」を「可能」に変えてしまった。機器・システムという環境要因の変化によって、障がい者の「参加」と「活動」を大きく拡大できるようになった。あとは、使うべき人が使えるようになることと、どう利用するかである。
1.支援技術とは何か?
疾病や事故で心身の機能が損なわれると、社会への「参加」や「活動」に制限が加わる。しかし、それを補う機器・システムを利用すれば、その制限をなくしたり、軽減したりすることができる。義肢や車いすはその典型だ。障がい者のリハビリテーションを支援する技術分野を「リハビリテーション工学」という。高齢者は必ずしも障がい者ではないため、心身機能が単に低下した人の支援は含まない。そこでより広い意味をもつ「支援技術」(assistive technology)という用語が使われるようになった。機器からサービスまで含む広汎な概念である。支援機器の使用で大切な点は、「残存する身体機能をうまく利用して、機器・システム・環境にアクセスできるようにすること」であり、人との接点である「ヒューマンインタフェース」の選択と適合がポイントとなる。
2.支援機器に関するアンケート調査
2008年10月に、障がい者支援を目的として「新潟市障がい者ITサポートセンター」を開設した。新潟市内の障がい者を対象として、現状とニーズの調査を実施し、約800票の有効回答を得た。驚いた。障がい者は、自立・生活・就労に有効な支援機器をほとんど知らない。視覚障がい者では、拡大読書機を80%が、スクリーンリーダーを92%が知らない。支援機器を知らないのだから、それを利用したいという社会的ニーズは存在しない。知られていなければサポート体制をいくら充実しても、利用してくれる人は限られる。一時期、障がい者ITサポートセンターは、国の支援によって全国各地に誕生したが、しだいに閉鎖された。理由がわかった。ニーズがない訳ではない、知られていないだけなのだ。「ニーズの顕在化、および顕在化後の広汎なサポート体制の確立」、これが障がい者ITサポートセンターの課題だ。
3.新潟市障がい者ITサポートセンター
当センターは、新潟大学自然科学系附置・人間支援科学教育研究センターが新潟市から受託した。職員は、兼任のセンター長である私、専任の支援員、非常勤事務員の3人のみ。関連機関との連携が必要であるため、協力関係にあった新潟県障がい者リハビリテーションセンター、新潟県難病相談支援センター、新潟市視覚障がい者福祉協会の代表に、運営委員として参加頂いた。外部から活動を評価いただくために、新潟県立高等養護学校、日本ALS協会新潟県支部、新潟市ろうあ協会、自立生活センター新潟などの代表に、評価委員を委嘱した。
事業は「支援環境整備事業」と「支援事業」だ。支援環境整備事業では、「支援機器が知られていない、使われていない」という事実から、障がい者が必ず通過する「病院」と「学校」にターゲットを絞り、積極的に介入した。教師、リハスタッフ(OT、PT、ST、医療SWなど)、保護者、地域のボランティアを対象として、月1回以上のペースで説明会・研修会・体験会を続けた。いわば合法的な「押し売り」だ。その甲斐あって、2007年4月には13件しかなかった相談件数は増加し、現在では、50件前後で推移している。さらに、16の組織・機関との協力体制も確立できた。
関連機関との協力体制は、IT サポートセンターの課題のひとつ「ニーズ顕在化後における広汎なサポート体制の確立」に多くの示唆を与えてくれた。センター職員3人では、広汎なサポートなど不可能だ。解決策は、センター機能の分散化および支援の階層化だ。病院のリハスタッフや教員の一部に支援技術に関する基本的な知識・技能を身につけてもらえれば、簡単なケースは学校や病院の現場で解決することができる。難しいケースだけ、サポートセンターと恊働で対応すればよい。
もうひとつは、専門家集団によるチームアプローチの有効性だ。病院では、リハスタッフ、医療SWとの連携が不可欠だ。単に医療リハビリの質向上だけでなく、退院後におけるQOL向上にもつながる。支援技術には、医療と社会福祉とのインタフェースとして機能があることがわかった。特別支援教育でも、教師、保護者、リハスタッフとの恊働が不可欠だった。多くのケースで、当センターはコーディネーター役も果たした。ITサポートセンターといえば、PCを中心とする情報通信機器や支援機器の選択・適合、それにPC教室を思い浮かべるかもしれない。しかし実際に始めてみると、学校でも病院でも、他の専門職と恊働しながら「利用者にとって最良の支援とは何か」という本質的な課題に取り組むことになる。
これこそが、障がい者ITサポートセンターの本当の仕事であると信じる。
略歴
1979年 新潟大学大学院工学研究科修士課程修了,新潟大学歯学部・助手
1986年 歯学博士(新大歯博第50号)(新潟大学)
1987年 新潟大学歯学部附属病院・講師
1989年 工学博士(工第1613号)(東京工業大学)
1991年 新潟大学工学部情報工学科・助教授
1996年 米国Johns Hopkins大学客員研究員
1998年 新潟大学工学部福祉人間工学科・教授
2008年 新潟市障がい者ITサポートセンター長(兼任)