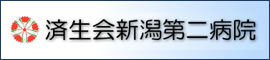講師:細井順(ヴォーリズ記念病院ホスピス希望館長;近江八幡市)
演題:生きるとは…「いのち」にであうこと ~死にゆく人から教わる「いのち」を語る~
日時:平成27年2月28日(土)15時開場 15:30~17:00
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
【講演要約】
ホスピスという場で患者さんと共に時間を過ごしていると、患者さんの死から、私は生きていく力をもらっているのではないかと思うようになった。ホスピスケアは、人に生きていく力を与えることができる。ホスピスケアを通して、人類に通底する「いのち」に気づく。人はひとりぽっちではなくて、他者とのつながりの中で生きていることを知る。「いのち」は死を貫いて遺る者に受け継がれていく。
ホスピスケアは、その人がその人らしく尊厳をもって人生を全うすることを援助することである。痛みなどの症状を除くことがゴールではなく、死の孤独に寄りそうことが真のホスピスケアと考えているが、そのためにヴォーリズ記念病院ホスピスで心がけていることを述べてみたい。
(1)患者さんと話す時間を多くとる
現代医療は、高度に専門化、細分化が進んでいる。狭い領域で専門的治療を受け、医療システムの流れに乗って効率良く連携されていく。がんのように高度の先進的医療が求められる分野では、なおさらこの傾向が強い。病人は多くの医療機関を転々として、数多くの医療者の関わりの中で、診断から治療、あるいは終末期ケアまで流れていく。いくつもの診療科で診てもらうので、かかわる医師の数も増えてくる。がんの進行度に応じて何人もの医師に治療が引き継がれていくことになる。
ここで問題になるのは、各々の医師は、それぞれの専門領域を診るにとどまり、病気の治療全体の責任の所在が明確でなくなっている。つまり、主治医が誰なのかわからないということである。患者さんは、病気が治るか否かという大きな不安を抱えている。また、治療のためにどれだけ仕事を休まなければならないのか、治療終了後に仕事に復帰できるのかなど、これから先の生活のことがとても気がかりになっている。ホスピスではまず、患者さんの言葉に耳を傾けることが基本である。
(2)かなしみへの気遣い
ホスピスで過ごす患者さんが感じることは、人生の悲哀ではなかろうか。死の影が忍び寄る胸の内を分かちあいたいということだろう。患者さんの持つ陰性感情は隠れやすいとされる。「かなしい」「つらい」「苦しい」「むなしい」「切ない」などの思いに気づくことが大切である。そして、医師と患者の立場を超えて、同じ死にゆく運命を共有する弱い人間同士という気持ちで、その場と時間を共に過ごすことである。医療者として「何とかしてあげねばならない」と気負うことなく、いずれ死にゆく仲間同士という意識で、「とことんつきあおう」ということではないかと考えている。
(3)患者さんの心の旅路につきあう
ホスピスで過ごしている患者さんたちは、誰もがこれからどのような苦しみが待っているのか、死ぬときは苦しまないだろうか、などと日々起こってくる身体の変化のひとつひとつに不安を覚える。全人的ケアという意味合いを考えると、身体症状の原因には、精神的な要素、社会的な要素、スピリチュアルな要素が含まれているということである。たとえば、「食事ができなくなった」という患者さんの訴えの場合、その言葉の背後に思いを巡らせることが大切である。決して胃腸の問題だけではない。薬が効かないというイライラが募っているかもしれないし、家族の見舞いが減っていることが気になっているのかもしれない。また、これから自分にどんなことがおこるのか不安でいっぱいになれば、食事もできないであろう。患者さんが何を思って「食事ができなくなった」と口に出したのか、この言葉をきっかけに、患者さんの心の旅路につきあうことがホスピスケアである。
(4)人生の流れの中で現在を見つめ直す
人生は物語にたとえられる。ひとりひとりの人生は、生まれてから死を迎えるまでの一巻のオリジナルな物語である。ホスピスでの時間は、その物語の大団円を迎えるときである。患者さんには、自分の人生を振り返ってもらうことがとても大切だ。今日この時まで生きてきたこと、人生で輝いていたときのこと、苦しかったときのことなどを思い返してもらい、人生が一連のつながりの中にあることを感じられたら死にゆく状況も納得しやすい。
現代日本は、団塊の世代が平均寿命を迎える10年後に多死時代を迎えるといわれている。その時を憂える声があり、死の準備を怠らないことが現代人に突きつけられた喫緊の課題である。死から学ぶことは大きい。
【プロフィール】
1951年、岩手県盛岡市の生まれ。小学二年生のとき、医師だった父の異動で京都に引っ越し、以来、大学卒業まで京都で育つ。クリスチャンホームで、物心つく前から教会に通い、中学一年生で受洗した。父親は法医学の大家、四人の叔父は外科医。
1978年大阪医科大学卒業。自治医科大学消化器一般外科講師を経て、淀川キリスト教病院外科医長となった。その時父親を胃がんのために同病院ホスピスで看取っ た。このことをきっかけに96年ホスピス医に転向。2年間研修後、愛知国際病院ホスピス長を経て、2002年よりヴォーリズ記念病院にてホスピスケアを行っている。
2004年、自身も腎がんで右腎摘出術を受けた。その後、自らの体験を顧みつつ、「死の前では誰もが平等、お互いさま」をモットーにしてケアを実践している。その様子がドキュメンタリー映画「いのちがいちばん輝く日~あるホスピス病棟の40日~」として2013年春から全国公開され、ホスピスからのメッセージを多くの人たちに届けている。
@淀川キリスト教病院 http://www.ych.or.jp/
1973年に日本で最初にホスピスケアを行い、1984年には日本のホスピスの生みの親、柏木哲夫氏(現・同病院理事長、名誉ホスピス長、金城学院長)により国内二番目のホスピスが開設された。細井氏はホスピス医としての指導を受けた。
@ヴォーリズ記念病院ホスピス http://www.vories.or.jp/medical_dep/kanwacare.php
@ドキュメンタリー映画『いのちがいちばん輝く日~あるホスピス病棟の40日』 http://www.inochi-hospice.com
「著 書」
『こんなに身近なホスピス』(風媒社、2003年)
『死をおそれないで生きる~がんになったホスピス医の人生論ノート』(いのちのことば社、2007年)
『希望という名のホスピスで見つけたこと~がんになったホスピス医の生き方論』(いのちのことば社、2014年)
【後 記】
ホスピス医の細井順氏をお招きしての講演会。当院で3回目となりますが毎回多くの参加者があります。今回も新潟市、新潟県は勿論、神奈川県・宮城県・長野県・山形県からも参加頂き、80名を超える参加者で盛況でした。
細井節は快調でした~「いろいろな方々との最後の時を一緒に過ごし学んだことは多い。死にゆく人は遺される人に生きていく力を与える。この力が『いのち』と呼ばれるものではないのだろうか。ホスピスでは生死を超えた『いのち』にであうことができる。。。。。」
講演の後で会場から沢山の質問も頂きました。最後までみてくれるホスピスを探すにはどうしたらいいのか?認知症の方とのコミュニケーションをとることは可能か?ターミナルケアと緩和ケアというのはどう違うのか?音楽療法は行うのか?最期を看取るのは長い間診てくれている開業医の先生ではダメなのか?ホスピス医と家庭医の違いは何?医者の勧める治療法を受け入れたいが、自分の生き方とぶつかることもある。如何にしたらよいか?多くの悩みを抱え、余命いくばくと宣告された方と如何に向き合えばいいのか?ホスピスには宗教的なバックボーンは欠かせないのか?医師は患者と向き合いエビデンスに基づいた治療を行うが、同時に患者に寄り添うホスピス的なケアを同時に並行して行うことは可能なのか?、、細井先生はこれら多くの質問に丁寧に答えてくれました。
今回初めて講演会終了後、細井氏著書の販売/サイン会も行いました。多くの方が事前に購入し読了してから参加しており参加者の意識の高さを知ることができました。書籍販売の本屋さんはがっかりでしたが、、、
死は誰にでも訪れるものですが、準備ができているかと問われて大丈夫と答えることの出来る人は少ないのではないでしょうか?細井氏は死について、そして死を迎えた人との向き合い方について淡々と語りました。その普通の語り方に凄さを感じました。ホスピス医は、時に「死神が来た」と揶揄されることもあるそうです。でも、「あなたのことを私は最後までみます」と言われたら、その人はどんなに安心するでしょう。現在の医療は、多くの部分を専門家が担っています。自分の専門のところが終了すると次のところを紹介という医療が最前線と考えられがちです。こうした医療の在り方、そして己を見つめ直す機会となりました。病を治すことが医療者の仕事です。しかし、メスや薬では治らない場合、「やすらぎ」を感じてもらうような医療を提供することも大事なことだと思い至りました。
講師の細井氏、最後まで熱心に講演会に参加された方々、会場の準備・整理をして頂いた方々、講演会の模様を中継して頂いた方々、会場を提供してくれた病院関係者等々、すべての方々に感謝致します。
===========================================================
【さらに細井順を知りたい方へ】 「いのち」について
(1)木村敏に学ぶ
私のホスピス観を表すと、「生死を超えたいのちの在りかを共に探し求め永遠を想い、現在を生きる」となる。ここで平仮名の「いのち」について考えてみたい。「いのち」についての考察を深めるために、臨床哲学者木村敏の生命論的差異という考え方を援用したい。木村は、生命を個別的生命である「生」と、普遍的生命である「生それ自身」との二つに分けて考えた。個別的生命「生」は、死で終わる有限なものであり、普遍的生命「生それ自身」は、すべての生きものに通底し、死で区切られない無限性を持つ。「生」と「生それ自身」とのあいだを「生命論的差異(=主観性)」と言う。この誰にでも通底している普遍的生命が「いのち」の素になっている。
(2)「いのち」の誕生
今、ある二人の人物が出会っているとしよう。A氏とB氏である。A氏とB氏はそれぞれに「生」と「生それ自身」を持ち、そのあいだを「主観的」に生きている。そのふたりが出会ったときには、A氏の主観とB氏の主観とのあいだに「間主観的」といわれるあいだができる。そのあいだを「いのちが生まれる空間」といい、人と人はこの「いのちが生まれる空間」で出会う。人と人との出会いは様々である。A氏、B氏ともに健康で、死を特別に意識せずに日常性のなかで出会うなら、この間主観的というのはそれぞれの個と個とが出会い、各々の「生」が中心となり、「生それ自身」は背後に隠れる。「生それ自身」は通常の関係性の中では特に意識されることなく、両者が健康で、競い合っているような場合には問題にならない。しかし、A氏、B氏の両者、あるいは片方に死が迫っているような、非日常的な場面では、ふたりに通底する「生それ自身」が表に出てくる。そして、日常的・個別的な「生」は後退し、ふだんは深奥で隠れている「生それ自身」が呼び覚まされてくる。このようなときには、ふたりの個別性が強調される方向ではなく、ふたりの共通性が優位になってくる。ふたりに通底する「生それ自身」が前面に現れたときに、A氏とB氏のあいだに生ずるのが「いのち」と呼ばれるものだと考える。生命の危機に臨んで、普遍的生命がふたりを結んだときに「いのち」が生まれる。
そう考えると、死を通路にして「いのち」が生まれるということになる。「いのち」は生まれるものなのだ。最初から備わっているものでなくて、出会いの中で生まれるものを指す。死という有限性を持つ人間が、無限に開けた存在となるために、「いのち」があると考えている。人間とは、ひとりの人間存在としてあるのではなく、誰かとの関係、木村の言葉では「あいだ」の中にある。そうだとしたら、私がいのちの臨床で感じる、「ひとはひとりでは生きられない、死ねない」ということも説明できるように思われる。
(3)「いのち」は受け継がれていく
ホスピスで死にゆく人たちとのあいだに生まれた「いのち」は、「普遍的生命」に根ざしたものである限り、私ひとりが生きていく力となるばかりではなくて、遺された家族、かかわってきたホスピスのスタッフにも、あるいはその患者さんと深いかかわりのあった全ての人たちの生きていく力になっていくものだと考えたい。愛する人を亡くするかなしみは個人的なものである。だが、誰もが持っている普遍的生命(「生それ自身」)が「いのち」の素となって、そこで「いのち」が生み出されるならば、それは、死の通底性から多くの人とのあいだにも「いのち」が生まれていくのである。そして、その広がりはついにひとつの「いのち」に還元されていくように思える。「いのち」とは、このように普遍的なものである。「いのち」は死を超えて次の世代に受け継がれていき、無限に続くものである。
人間はつながりの中でしか生きられず、そのつながりこそ、平仮名の「いのち」であると考える。「いのち」は、各々の生活の中にあって、他者との出会いを生き生きとしたものに換え、喜怒哀楽を演出して、人から人へと代々受け継がれていくのである。人生は物語にたとえられると前述した。ここでもうひとつの物語を考えたい。前述したものを横の物語とするなら、ここでは縦の物語と名づけよう。親から受け継ぎ、幾世代にもわたって綴られ、同時代の人々と和してひとつの章節を書き込み、次の世代に引き継がれる「いのち」の物語である。この物語は一人ひとりに生きる意味を与えてくれる。こうして、ホスピスでの死にゆく人たちとの出会いは私に生きる力を与えてくれるのである。