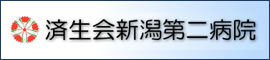報告:第139回(2007‐09月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会 宮坂道夫
演題:『かつてハンセン病患者であった人たちとともに』
講師:宮坂道夫(新潟大学医学部准教授)
日時:平成19年9月12日(水) 16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要旨】
ハンセン病は、病気というものが悲しい差別に結びつくことを、痛切に教えてくれる最たる例である。この病気が遺伝病ではなく感染症であることがわかったのが19世紀の末、日本国憲法に基本的人権がうたわれたのが1946年、ハンセン病の効果的な化学療法が開発されたのが1950年前後、世界ライ学会や世界保健機関(WHO)が隔離政策の廃止・通院診療が望ましいと公式な見解を出したのが1960年前後である。しかし、隔離政策を根拠づけた「らい予防法」が廃止されたのは、1996年のことであった。およそ一世紀にもわたる不合理な絶対隔離政策による患者の人権侵害が、かくも長く続いた原因はどこにあるのだろうか?
第1章 無知から始まる旅
2001年5月11日、何気なくテレビを見ていた。TV番組「ニュース・ステーション」で、熊本地裁判決(隔離政策に対する訴訟;原告側勝訴)のことを報じていた。谺(こだま)雄二さんが出演していた。1960年代生まれの私は、この時ハンセン病の「患者だった人」が語る姿をはじめて見た。谺さんは長い時間をかけて、カメラに向かって思いのたけを理路整然と訴えていた。彼は、病気が治って後遺症を抱える「患者だった人」である。病気が治っているのに、何故療養所で暮らさなければならないのか?そもそも感染力が強くもないハンセン病の患者が、何故故郷を捨てて人里離れた療養所に隔離されなければならなかったのか?このようなことが多くの国民に知らされていなかったのはマスコミにも責任があるのではないか?
新潟大学の全学講義(前年の全学講義は、ノーベル賞を受賞した白川英樹博士)に谺さんをお招きして、お話を伺うことにした。講義の打ち合わせで2002年3月25日、群馬県草津町の国立ハンセン病療養所の栗生(くりゅう)楽泉園に谺さんを訪問した。そこで幾多のことを教わった。園内だけでしか通用しない紙幣の存在、かつては外部との手紙も検閲されていたこと、亡くなっても御骨を故郷に埋葬できないため園内に建立された納骨堂、断種手術に使われた手術台、中絶した胎児のホルマリン漬けの標本、しかもそのような理不尽なことをかつて日本が台湾や韓国・中国でも行ってきたこと、園に入園した親を持つ子供は学校にも行けなかったこと、手でペンを持てないために口でペンをくわえて文字を書いていた人もいたこと、居住地のはずれに重監房と呼ばれる跡地。「孤独地獄、闇地獄」「日本のアウシュビッツ」、、、これは許されないことだと感じた。
第2章 医学の物語
2002年5月20日、新潟大学全学講義で谺さんに講演してもらった。演題は「人間として生きたい」であった。会場は満員となり、地元の新聞にも大きく取り上げられた。谺さんの「語り」は迫力があった。自分自身の体験を語るという当事者ならではの「小さな物語」と、日本国のハンセン病政策の歴史という「大きな物語」を同時に巧妙に織り交ぜて語って頂いた。
ハンセン病は「らい菌」が鼻粘膜や気道から侵入し感染すると考えられているが、感染の仕組みは今も解明されていない。「らい菌」を培養することが出来ていないため、細菌の生物学的性質が調べられていない。ただし確実に判っているのは、たとえ体内に感染したとしても防御免疫機能が働く場合は、感染が成立することは非常に少ないということである。
ハンセン病が進行すると「変形」と「身体障害」がもたらされる。らい菌が皮膚で増殖すると腫れ物や潰瘍を生じたり、皮膚を肥厚させる。末梢神経の障害により、手足の指が硬くなり屈曲したり、感覚がなくなり外傷や火傷を負っても気が付かないこともある。感染症対策で問題となるのは、感染を防ぐための隔離という手段の是非である。倫理学という視点からから考えると、二つの倫理原則について検討すれば、事足りる。すなわち、自律尊重原則(患者の自己決定権が尊重されるべきという原則)と、無危害原則(患者もしくは第三者にとって危害となるようなことはするべきでないという原則)である。この二つの原則から隔離を検討すると以下のようになる。病気そのものがもたらす危害が重篤で、他の手段で防げない時に限って、隔離という手段が検討される。次に隔離の医学的必要性を患者に十分に説明して、患者本人が自らの意思で隔離に応じるように促す。それが困難である場合に限って、強制隔離が検討される。
第3章 烙印の物語
ハンセン病は、古い時代から世界の多くの地域で強い差別の対象だった。特に顔貌の変化、手足の変形、潰瘍や膿、臭いなどに人々は反応した。このようなハンセン病を疎ましいと考える「烙印」、価値観は世代を超えて、そして地域を越えて世界中に存在した。仏教に、「天刑病」という言葉があり、よい行為をしなければハンセン病のようになってしまうという警告の役割をしていた。仏教に限らずキリスト教やユダヤ教をはじめ多くの宗教にこうした例を見ることが出来る。
19世紀にはヨーロッパの列強が植民地を拡大したが、そこにはまだハンセン病が蔓延していた。ノルウェーのハンセンが患者の組織から「らい菌」を発見し、感染症であることを1873年に報告し、次第に認められるようになってきた。ハンセン病がすでに過去の病気になった「文明国」は、まだ流行している「非文明国」からのハンセン病流入を防ぐため、植民地で強制隔離が行われるようになった。
オーストラリアでは、アポリジニーからのハンセン病感染を防ぐため、「らい線」と呼ばれる南緯20度に境界線(大陸に引かれた隔離の線)を引いた。南アフリカの療養所では、逃亡を防ぐため有刺鉄線がはりめぐされた。数ある収容所の中でもロベン島は最悪の場所だった。反体制の政治家、犯罪者、精神病者、そしてハンセン病患者がこの島に送られた。
わが国では、1900年当時の内務省は、(非文明国の病気であると考えられていた)ハンセン病患者の第一回全国調査を施行し、日本全国に3万人いることを報告した。このことは列強の仲間入りを目指していた日本にとって「国辱」であったと思われる。こうした事情からか、日本における強制隔離は、世界各国のものよりも群を抜いて強力なものであった。本人の意思に拠らない「強制隔離」であり、「生涯隔離」であり、たとえ完治しても隔離を解かない「絶対隔離」であった。
第4章 世界最悪のパターナリズム
光田健輔は、「救らいの父」と評価され、1951年文化勲章を受章した。ハンセン病患者への救済事業に積極的に取り組んだパイオニア的な存在であり、病型分類に貢献した「光田反応」は有名。一方で1953年制定のらい予防法に積極的に関わるとともに、法の存続に力を入れたこと、優生学に基づく患者に関する強制断種(ワゼクトミー)の実施など、ハンセン病患者の強制隔離・断種を推進し、ハンセン病患者に対する差別を助長する元凶を作った人物とも評されてる。
「強制隔離」「強制労働」「断種」「懲罰」は、患者を弾圧する、人道に反するものである。何故このようなことを思いつき、実行したのだろうか?実際は、「善行」として、良かれと思って、行なわれたふしがある。ある意味での「パターナリズム」という解釈である。「パター」とは父親という意味であり、父親と子供という当事者同士に力の不均衡があり、「強者」が「弱者」に対して恩恵を施すという価値観である。
「医は仁術」と言われる。「仁」の概念は、日本の近代医学で流通しているものと、中国の倫理思想でだいぶ異なる。「仁」は孔子によって提唱された倫理観である。「孝」が子供が親を尊ぶべきものという原則であるのに対して、「仁」はもっと広い対象への思いやりを意味する。他人に対しても親と同じような思いやりを持ち、自分を抑制するべきであるという倫理原則である。「対等もしくは同等の者が、目の上の者に対する関係」を前提としている。
日本における「医は仁術」は、専門知識を持ち、社会的地位が高い医師が、患者にかける憐れみの情を含んでいるように思われる。「救らい」という言葉で語られたハンセン病政策は、それに関わる医師、看護師、宗教家、社会事業家、学者、文化人等々が、皆「恩恵」を患者に与えようとしている。本人が意識しているか否かに拘らず、「目の上の者から、目下の者へ」というパターナリズムに近い構図のもとで成り立つ倫理観である。
「救らいの父」と称せられた光田健輔は、日本のハンセン病政策をデザインした当事者であった。弱い立場にあったハンセン病患者を「庇護」しようと、時に手弁当で働き、政府に働きかけ、ユートピアというべき療養所の建設を目指す姿はまさに「父親」のイメージであった。こうした努力により、国立ハンセン病療養所長島愛生園が完成した。その園長に就任した光田は「大家族主義」という方針を打ち出した。「患者も職員も家族であり、私が家長となり、親兄弟のように暮らしていきたい」。そして家長は罰する権限を持つとも述べている。家族主義の中には、「罰する親」という側面も有している。
第5章 重監房であった出来事
「大家族主義」の美名の下で行われた、強力な隔離、強制労働、断種と堕胎に対して、患者が不満を持たないはずはなかった。こうした不満に対して当時の日本政府は力で抑え込もうとした。1907年に制定された「らい予防法」は、9年後1916年療養所の所長に対して懲戒検束権を付与するように改められた。さらに15年後の1931年罰則規定が定められた。罰則の内容は、謹慎、減食、監禁、謹慎と減食、監禁と減食等の段階である。期間は30日以内とされたが、最大2ヶ月まで延長を認めた。科刑の場所として、各療養所に監禁所が設けられた。監禁所で「獄死」する患者が相次いだ。
私は「生命倫理学」を専門にしているが、ハンセン病問題を知るほどに、複雑な思いを抱かされた。米国から「患者の権利」「インフォームド・コンセント」といった概念が日本に紹介されたのは1970年代だが、ハンセン病の患者さんたちが人権擁護の運動を起こしたのは、それよりずっと前の1950年前後のことである。しかし、生命倫理学のテーマとして、ハンセン病問題が取りあげられたことはほとんどなかった。日本の医学史に「患者の権利の確立」という項目があるとすれば、ハンセン病問題抜きに語ることはできないであろう。この巨大な「事件」を生命倫理学という観点から見つめ直すこと- それは研究者としての自分自身への問いでもあった。
昨年(2006年)刊行した『ハンセン病 重監房の記録』(集英社新書)をベースに、お話をさせて頂いた。
【宮坂道夫先生:略歴】
http://www.clg.niigata-u.ac.jp/~miyasaka/hansen/jukambonokiroku.html
昭和63年 3月 早稲田大学教育学部理学科卒業
平成 2年 3月 大阪大学大学院医学研究科修士課程修了(医科学修士)
平成 6年 9月 東京大学大学院医学系研究科博士課程単位取得退学
平成 7年 9月 東京大学医学部助手
平成10年 9月 博士(医学)取得(東京大学)
平成11年10月 新潟大学医学部講師
平成15年 1月 新潟大学医学部助教授
平成19年 4月 新潟大学医学部准教授
主著『医療倫理学の方法』(医学書院)
『ハンセン病 重監房の記録』(集英社新書)
http://www.clg.niigata-u.ac.jp/~miyasaka/hansen/jukambonokiroku.html
【後記】
ハンセン病、こんなに苛酷な実態だったとは、、、。知ってしまった、今後見過ごすことは出来ないというのが実感でした。
改めて、ウィキペディアで「光田健輔」、検索してみました。「救らいの父」と評価され、文化勲章を受章した光田健輔氏。ハンセン病患者への救済事業に積極的に取り組んだパイオニア的な存在であり、病型分類に貢献した「光田反応」は有名です。一方で1953年制定のらい予防法に積極的に関わるとともに、法の存続に力を入れたこと、優生学に基づく患者に関する強制断種(ワゼクトミー)の実施など、ハンセン病患者の強制隔離・断種を推進し、ハンセン病患者に対する差別を助長する元凶を作った人物とも評されています。
お話している時の宮坂先生は、静かに怒っているように見えました。光田氏「個人」に対する批判を避け、生命倫理学者の立場から「世界最悪のパターナリズム」と結論されました。
お聞きしているうちに今回はかなり重いテーマの勉強会と感じていましたが、宮坂先生は最後に、「私は怒りに満ちて闘争している訳ではありません。谺(こだま)雄二さんや、国立ハンセン病療養所栗生(くりゅう)楽泉園の皆さんの人柄に触れて、交わりを楽しみ、今後もお付き合いしていきたいという思いがつよいのです。」と語ってくれました。それを聞いて何故か少しホッとしました。
亡くなっても御骨を故郷に埋葬できないため園内に建立された納骨堂のお話を聞いてた時、新潟県の視覚障がい者で構成する男性合唱団「どんぐり」(*)が、「粟生楽泉園」で行ったコンサートのことを思い興していました。最後に歌った曲は「故郷」。「兎追いしかの山~こぶな釣りしかの川~~~」。帰りたくても帰れない故郷を思いながら、全員で涙して歌ったと聞いています。
ハンセン病、もう少し勉強してみたいと思いました。
(*)男性合唱団「どんぐり」
http://www.ginzado.ne.jp/~tetuya/donguri/ayumi.htm