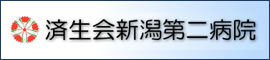報告:第177回(10‐11月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会 栗原 隆
演題:「私たちは何と何の間を生きているのか」
講師:栗原 隆 (新潟大学人文学部教授)
日時:平成22年11月17日(水)16:30~18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要旨】
私たちが〈生〉を享ける時点はどの時点であろう か。この世に誕生した時が〈生を享けた時〉だと単純明快に言い切ることが出来ないのは、妊娠中絶や生殖補助医療によって、〈生〉の始まりに人の手が介入できるようになったことによる。脳死をもって人の死と判断するようになって以来、死も、運命ではなく、私たちの判断によって定められるようになった。そうすると、私たちは、人と人との間に生きているからこそ、人間であるとも言われるが、日常的な場面で、常に私たちは倫理的な葛藤状況に身を晒し、その都度、どうするべきか対処することを求められていることも考え合わせるなら、私たちは倫理的な判断を生きていると言えるかもしれない。
1 胎児の数は誰が決めるのか
赤ちゃんの65人に一人が、体外受精で生まれる時代に、多胎妊娠の処置は、諏訪マタニティー・クリニックの他、15の診療所施設だけでしか行なわれていない。減数手術は「堕胎罪」に問われかねないからである。日本産科婦人科学会は、1996年以来、子宮に戻す受精卵・胚の数を、原則三個と規定してきたものを、2008年4月12日に「生殖補助医療の胚移植において、移植する胚は原則として単一とした。ただし、35歳以上の女性、または二回以上続けて妊娠不成立であった女性などについては、二胚移植を許容する と、移植胚数を制限するに到った。
減数手術に対して、医師が生まれてくる子どもを決めることに異論が出されてきたにもかかわらず、今度は医師によって、初めから、生まれてくる子の数が決められることになった。減数手術には厳しい眼が向けられる他方で、妊娠中絶の件数は、赤ちゃんが4人生まれるのに対して、1人が母胎内で命を絶たれる計算で、主婦層中心から、低年齢化している。
2 誰の迷惑にもならないことなら、何をしても許されるか
――出生前診断と着床前診断
体外受精による受精卵が、4~8分割した段階で細胞一個を取り出して、核のDNAを検査することで、遺伝性疾患の有無や性別を確かめる着床前診断は、妊娠後に、羊水検査など、胎児の細胞を調べるいわゆる出生前診断によって異常が発見された場合 に、判断を迫られる妊娠中絶を避けることが出来て、母親の肉体的・精神的負担の軽減に繋がると言われる。確かに、出生前診断では、染色体異常の子どもである可能性が170分の1とか、50分の1などという確率の形でしか出てこないため、受け止め方に関して、人によっては混乱を来たしかねない。子宮に針をさして、羊水を20ミリリットルほど抜き取って、そこに含まれている胎児から剥がれた皮膚や粘膜の生きた細胞を培養して染色体を検査する羊水検査は、平均で300回に一回の割合で流産が引き起こされる。誰にも迷惑や危害を及ぼさない技術だからといって、出産に関する自己決定権の行使として守られるべきものであろうか。妊娠率が低くなると言われてもいるこの着床前診断にあっては、8分割した段階で細胞を1~2 個、検査のために取られるというのであるからして、胚の尊厳を冒していないと言い切れるであろうか。
倫理を云々する以前に、胚にとって安全な技術であるのか、疑問が残る。最も確実な男女産み分けは、精子に蛍光塗料を加え、レーザー光線を照射して、男女産み分けをするフロー・サイトメトリーという方法があるが、必要の前に倫理は無力であってはならない。
3 胎児に生まれてくる権利はあるのか
祝福と希望に満ちて生まれてくる赤ちゃんもいる一方で、その4分の1ほどの数の胎児が中絶されている。日本では妊娠22週未満という〈線引き〉がなされている。妊娠中絶をめぐる〈線引き〉についての、ジューディス・ジャーヴィス・トムソンによる「人工妊娠中絶の擁護」(1971年)は、妊娠に繋がるかもしれない行為だと知っていながら行為に及んで、妊娠に到った場合の中絶をも擁護する議論を呈示した。どの段階から、受精卵は、胚ではなく胎児として、自然的紐帯のなかに迎え入れられるのであろうか。筆者の実感では、妊娠が最初に確認されて、超音波で、ごくごく小さな心臓の、限りない拍動が目に見えるようになった時、8週目くらいだったろうか、その時から胎児は家族の一員になった。
生まれてくる権利とか、女性の権利という概念で割り切れない命の繋がりが、その時からエコーの画面で目に見えるようになった。重要なのは、「権利」や「正義」という文脈ではなく、また受精卵一個の、胎児一人の生命ではなく、もっと大きな生命の繋がりの中で命が育まれてゆくというような形で捉え直されなくてはならないということである。「権利」や「正義」は、相手に対する共感・思いやりがない場合には、自分勝手なものになりかねないからである。家族として、胎児に対して理解を深め、共に生を営んでいく、そうした「生の繋がり」を、ディルタイは、「体験」を軸に分析的に描き出した。ヴィルヘルム・ディルタイは、『歴史的理性批判のための草稿』で、普遍的な生の連関を拓く契機を「体験」に見定めて、他者を理解することの成り立ちを明らかにしようとした。
生きてゆくということは、「人生行路(Lebensverlauf)」という表現にもあるように、時間と場所を経てゆくことである。日々、私たちが生きてゆくさなかにあって、次々と時間を過ごし、さまざまな場所を得ながら、いろいろな体験をしている。体験(Erleben)とはまさに生きる(Leben)ことである。生きてゆく場所のそれぞれは、瞬間のそれぞれは、次々と流れ去ってゆくように思われる。にもかかわらず、そこを生きている私は、同じ私として、連続したアイデンティティを担っている。人生の意義と目的とが自覚されていてこそ、その都度の出来事が体験として、その人の糧になる。
4 結び
個人の人生自体、自分だけで営まれているのではないのは、私たちの〈自己〉が、家風や家柄、しつけや作法、生活習慣や生活スタイル、経済状態、倫理観、順法意識、国家、宗教、芸術への趣味、学問、思想によって 影響されていることからしても、明らかであろう。親になって初めて、子育ての限りない喜びと束の間の苦労と些かの心配とが理解できる。
私たちに理解できるものが用意されていないことについては、理解のよすがを持つことができない。他者を理解しようとすると、自らを相手の立場に置き換えてみる「自己移入」が必要である。そうであるならば、書かれたテクストを読む場合であろうと、人に接する場合であろうと、いや、さまざまな患者さんと接する医療者であればこそ、相手を理解するためには、それだけ解釈する人の体験を豊かにしておかなくてはならないことになる。
【略歴】 栗原 隆(くりはら たかし)
新潟大学人文学部教授(近世哲学・応用倫理学)
1951年 新潟県新発田市生まれ。新潟市立万代小学校~鹿瀬小学校~
鹿瀬中学校~見附市立葛巻中学校~長岡高等学校
1970年 新潟大学人文学部哲学科入学(1974年卒業)
1974年 新潟大学人文学専攻科入学(1976年修了)
1976年 名古屋大学大学院文学研究科(博士課程前期課程)入学(1977年中退)
1977年 東北大学大学院文学研究科(博士課程前期課程)入学(1979年修了)
1979年 神戸大学大学院文化学研究科(博士課程)入学(1984年修了・学術博士)
1982年 大阪経済法科大学非常勤講師(1991年辞職)
1984年 神戸大学大学院文化学研究科助手(1987年辞職)
1987年 神戸女子薬科大学非常勤講師(1991年辞職)
1991年 新潟大学教養部助教授
1994年 人文学部に配置換え
1996年 新潟大学人文学部教授
【参考図書】
「現代を生きてゆくための倫理学」 著者;栗原 隆
(京都)ナカニシヤ出版 (2010/11/15 出版) 価格:2,730円 (税込)
現代世界において露呈する、個人の自己決定権の限界を見据え、再生医療、臓器売買、希少資源配分、将来世代への責任など、現代の諸問題を共に考えることで、未来への倫理感覚を磨き上げ、知恵の倫理の可能性を開く一冊。
【後 記】
難しそうなテーマでしたので、あまり多くの方は参加されないかも、、、と危惧しておりましたが、遠くは名古屋からの参加者も含め多くの方に集まって頂きました。
今、ハーバード大学のマイケル・サンデル教授の、『ハーバード白熱教室』がTVや書籍で話題です。今回の栗原先生の講演は、同じような興奮を感じながらお聞きしました。 胎児の数は誰が決めるのか? 誰の迷惑にもならないことなら、何をしても許されるか? 胎児に生まれてくる権利はあるのか?
出来ることはやるべきなのか?、、、様々なテーマを投げかけながら話が進みました。 「カント哲学」では、こう考える、、、、最後に医療従事者への提言と話は進みました。その展開にドキドキしながら引き込まれ、あっという間の50分でした。
お互いが相手のことを理解することは大事なプロセスです。医療の現場においては特に求められていることです。しかし理解できるものが用意されていないことについては、理解のよすがを持つことはできません。相手を理解できるのが追体験のみであるとするなら、障害のある人を理解することは、障害のない人にはできないということになってしまいます。自らを相手の立場に置き換えてみる「自己移入」が必要と栗原先生は喝破されました。
『眼聴耳視』(「げんちょうじし」あるいは「がんちょうじし」)という言葉を、何故か思い起こしました。眼で見るのではなく、眼で聴こう。耳で聴くのではなく、耳で見よう。大事なことは目に見えない。耳では聞こえない、という意味だそうです。
眼で聴くというのは、明るく元気な人を見ると「幸せそうだ」と思いますが、心の叫びを聴けなければ本当の姿は分かりません。耳で視るということは、洗い物をしているお母さんは赤ちゃんの泣き声を聞いただけで、オッパイを欲しいのか、オムツを替えて欲しいのかが目に浮かんできます。何も語らない人の思いを聴いて、見えない姿に心を寄せて視るということです。
哲学者である栗原先生の語りは、圧倒的でした。哲学というものを、今まであまり身近に感じたことはありませんでした。今回いろいろなテーマを突き付けられ、幾つかの論点を、さまざまな角度から考えるいい機会を設けることができ、とても有意義な時間を過ごしました。
サンデル教授ばりのお話を、またお聞きする機会を設けたいと思います。
栗原隆先生の益々のご発展を祈念致します。