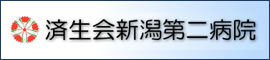第14回 日本ロービジョン学会学術総会
シンポジウム2「サブスペシャリティーからのロービジョンケアの展望」
■登壇日時:2013年10月12日(土) 16:20~17:50
■会 場:第1会場(倉敷市芸文館 1F ホール)
■司 会:安藤 伸朗 済生会新潟第二病院
佐藤 美保 浜松医大
■演 者: 門之園 一明 横浜市大医療センター
佐藤 美保 浜松医大
若倉 雅登 井上眼科
根岸 一乃 慶應義塾大学医学部 眼科学教室
栗本 康夫 神戸市民中央病院
安藤 伸朗 済生会新潟第二病院
【オーガナイザー挨拶】
安藤 伸朗 (済生会新潟第二病院)
佐藤 美保 (浜松医科大学医学部病院教授)
近年の眼科医療の進展は著しいものがある。今、必要とされている知識や技術は、3年と持たない。ロービジョンケアはもちろん、患者の望むこと・患者のニーズに沿うことが基本であるが、新しい医療の要求に応える(対応する)ことも求められる。こうした視点から、今回の「サブスペシャリティーからのロービジョンケアの展望」は、各専門分野のトップランナーが、疾患別にロービジョンケアを語ることを意図したシンポジウムである。
各分野のリーダーに、眼疾患を治療する場合の最新の知見を述べて頂き、かつ各演者がロービジョンケアに期待することを語って頂く予定である。
ロービジョンケアは必要だとは認めるが、なんとなく敷居が高いと思っている眼科医が多いのではないだろうか?ロービジョンケアは、決して一部の眼科医のみが関わる特殊な領域ではない。予定していた治療効果が得られない場合や、患者が期待していた視機能が得られない場合、治療に携わるすべての眼科医が関わる分野である。
今回のシンポジストは、これまでロービジョン学会にあまり参加していない、多士済々な顔ぶれである(以下、敬称略)。網膜硝子体は、門之園 一明(横浜市大医療センター)、 小児眼科は、佐藤 美保(浜松医大)、神経眼科は、若倉 雅登(井上眼科)、白内障・屈折は、根岸 一乃(慶応大学)、再生医療は、栗本 康夫(神戸市民中央病院)、精神的サポートは、安藤 伸朗(済生会新潟第二病院)。本学会では新鮮な、そして通常ではありえない面々のコラボである。
各分野の専門家に「疾患ごとに求められるロービジョンケアのあるべき姿」を語って頂き、近い将来に必要となる新たなロービジョンケアの方向を模索してみたい。トップランナーが何を語るか?どんなシンポジウムになるか?今から楽しみである。多くの方々の参加を期待している。
1)網膜硝子体とロービジョン
門之園 一明 (横浜市立大学医療センター 眼科教授)
網膜硝子体手術は近年急速に進歩し、多くの疾患の視機能を救うことができるようになった。いうまでもなく、現在では、視機能障害を改善することのできる重要な治療手段のひとつである。一般に網膜硝子体手術には術前後を含めて多くの時間を労力を費やすため、術者は網膜の形態学的な改善と視力の向上を以って、治療の成功を決める傾向が強い。
しかし、重度な増殖硝子体網膜症を仮に首尾よく治療できたとして、患者にとってその視機能が満足の行くものでなければ、治療は術者の満足のみに陥ることになるだろう。患者と医師の間に治療の理解と満足度の隔たりのある限り、なかなか本来の治療は生まれないであろうし、少なくとも我々はその溝を少なくする必要がある。また、これは、広い意味で周術期管理といえる。
網膜硝子体術者は、難しい疾患と向き合う頻度が高く、いつもこの課題を背負っているため、精神的なストレスの多い仕事である。このため、多くの術者はこれまで、自分なりのやり方でそれなり対応をするか、あまり術後のフォローに関心を示さないように演じて来ることで、対応してきたのではないであろうか。
ロービジョン学は、近年非常に進歩し低視力患者に貢献している。現在では、術後の患者の抱える問題点を解決する唯一の手段をなっているにもかかわらず、残念ながらロービジョンを理解し、これを応用する網膜硝子体術者は少ない。具体的な視機能向上のための装具や治療器具を含め、心理的なサポートの方法など、ロービジョン治療学の中には、網膜疾患患者へ応用できる知識が多く含まれている。
これからの網膜硝子体術者は、その手術技量を向上させるだけでなく、術後に否応なく訪れる可能性のある不完全な視機能に対して、ロービジョンを手術後管理に積極的に取り入れる傾向が強くなるであろう。また、これは中枢神経組織を扱う網膜外科の本来の健全なあり方である。
【略歴】
1988年 横浜市立大学医学部卒業
2000年 横浜市立大学医学部眼科講師
2005年 横浜市立大学市民総合医療センター眼科准教授
2007年 横浜市立大学市民総合医療センター眼科教授
現在に至る
2)小児眼科
佐藤美保(浜松医科大学医学部病院教授)
小児眼科外来は、小児の良好な視力発達を目標として治療を行っているが、重度の先天性眼疾患をもって生まれた児や、未熟児網膜症などで、改善の期待できない重度の視覚障害をもつ児に対して、その家族も含めたロービジョンケアを行うことは重要な役目である。
浜松医科大学付属病院では視覚障害のある小児を対象とした療育相談を行っている。そのなかでも3歳以下を早期療育相談として、視覚支援校と早期に繋がりをもたせる試みを行っている。早期療育相談の流れは、重篤な視力障害を持つ乳幼児が受診した場合に、院内早期療育相談の存在を養育者に伝える。養育者が相談を希望した場合には、ロービジョン外来担当の視能訓練士が窓口となって、視覚支援校の乳幼児発達支援指導員と連絡をとる。
院内早期療育相談は、視覚支援校の教員が大学病院の外来を訪問する。初めに眼科医、視能訓練士が同席して、病状を保護者と教員に説明するとともに児の眼症状をいっしょに確認する。その後、教員が乳幼児の行動を観察しながら、育児支援、発達支援、情報提供などを保護者に対して行う。院内早期療育相談終了後、保護者からの希望があれば視覚支援校を訪問しての教育相談に繋げていく。
低視力の原因は、黄斑低形成、未熟児網膜症、第一次硝子体過形成遺残、眼白子症、先天白内障 先天小瞳孔、視神経異常、網膜色素変性症、緑内障 強角膜症などである。視力は0.1以上のものもいたが、ほとんどは0.1以下であった。そして、相談を受けた養育者の多くは、引き続き視覚支援校との連絡をとり視覚支援校幼稚部への進学を選択するものが多くみられた。
生まれてきたばかりの赤ちゃんが、生涯視力に問題を抱えていきていくという事実を受けいれることは容易なことではない。医師の役目は正しい診断をくだし、治療可能なものにたいしては全力で治療にあたるが、そうでない場合には予後を判断したうえで正直に事実を伝えることである。予後の判断が即座にできない疾患に関しては継続的なフォローをしながら必要な情報を提供していく。ときには悲観的な説明ばかりではなく、児が成人となる20年後の未来の医療への希望へとつなぐ説明を行うことも必要である。養育者は子育てに悩みながら相談できる場所をさがしているため、早期療育相談を通して医療と教育、福祉をうまくつないでいくことが重要と考える。
【略歴】
1986年 名古屋大学医学部卒業
1992年 名古屋大学医学部大学院外科系眼科学満了
1992年 学位取得
1993年 名古屋大学眼科学助手
1993年9月- 米国Indiana 大学小児眼科斜視部門留学
1995年3月
1997年7月 名古屋大学眼科学講師
2002年7月 浜松医科大学医学部眼科学助教授(准教授)
2011年1月1日 浜松医科大学医学部病院教授
現在に至る
3)神経眼科より
若倉 雅登 (済安堂 井上眼科病院 名誉院長)
神経眼科の臨床においては、視神経症やさまざまな中枢性疾患により、不可逆的に視覚が障害されたり、視覚が快適に利用できない状態に対して、医療者としてどのように対応すべきかは残された大きな問題である。これまでの日本の臨床医学は診断、治療までが医師の業務で、その先に存在すべきマネージメント、医療ケアを行うマインドに欠けていた。臨床に時間的、経済的制約があるとはいえ、卒然卒後教育にそのような視点がなかったことがその要因であろう。
神経眼科領域に限ったことではないが、眼科臨床においては、慢性進行性疾患はもとより、急性疾患でも不可逆的変化が生じ、視覚障害や不都合が生涯残る症例に少なからず遭遇する。こうした場合のケアとしては、患者の不都合や不満を実感的に十分傾聴し、それを理解し、障害を抱えた状態で生きる患者の今後に、何らかの指針を与えられるのが理想ではある。しかし、そこまで医師に心理学者、哲学者、宗教家であることを求めるのは無理がある。
眼科学的に今の障害の状態がどうして生じているのか、丁寧に平易な言葉で説明することが、眼科医としてできるすべてではないかと私は考える。その上で、精神医学の手法を応用して、認知行動療法を試みることで、患者自身が現状把握、受け入れ、前進という過程を踏むことができる場合がある。これは、心療眼科の大事な役割のひとつである。
以上の過程を円滑に進めるために、同症者とその家族で構成する「患者友の会」はしばしば非常に有効な手段になる。私は、「眼瞼・顔面痙攣患者友の会」や「レーベル病患者友の会」、また当院の視覚障害者の十数人で構成される「ボネの会」の設立を支援してきた。ここでは、患者同士が自身の不都合や体験を遠慮なく口にできる(一般社会で彼らがそれを口にすることは非常に少ない、一般に家族にはうるさがられ、社会では無視や差別の原因になるからである)。同症者の状況を知ることで、孤独感、特殊感の軽減、解消にも役立つ。さらに、互いに情報交換することの意義もある。私が関わったこうした患者友の会の状況について、設立に至る経緯と、実際の成果についても時間があれば報告したい。
【略歴】
1976年3月 北里大医学部卒
1980年3月 同 大学院博士課程終了
1986年2月 グラスゴー大学シニア研究員
1991年1月 北里大医学部助教授
1999年1月 医)済安堂 井上眼科病院 副院長
2002年1月 医)済安堂 井上眼科病院 院長
2010年11月 北里大学医学部 客員教授 (現在に至る)
2012年4月 医)済安堂 井上眼科病院 名誉院長
4)白内障・屈折
根岸 一乃 (慶應義塾大学医学部眼科学教室)
一般に白内障および屈折矯正手術は、視力の改善が期待できるものに行われ、それ以外は適応外であるとされる。ロービジョン患者に関しては、患者が手術を希望しても「適応なし」として放置される場合もしばしばであり、これは「視力予後」という観点から見れば正しい判断だといえる。
しかしながら、近年、白内障および屈折矯正手術は患者のQuality of Life(QOL)に大きく関与することがわかってきている。たとえば、白内障手術を行うと歩行速度が速くなり、睡眠の質が改善し、ひいては寿命の延長につながる可能性もある。
本講演では、主として白内障手術が患者のQOLに及ぼす影響について自験例のデータを示し、ロービジョン患者における白内障および屈折矯正の治療の意義について検討する。
【利益相反公表基準:該当】無
【略歴】
1988年 慶應義塾大学医学部卒業・同眼科学教室入局
1995年 国立埼玉病院眼科医長
1998年 東京電力病院眼科科長
1999年 慶應義塾大学眼科学教室講師(兼任)
2001年 慶應義塾大学眼科学教室専任講師
2007年 慶應義塾大学眼科学教室准教授、
現在に至る。
5)iPS細胞がもたらす網膜・視神経の再生医療とロービジョンケア
栗本康夫(神戸市立医療センター中央市民病院、先端医療センター)
長年にわたって、成熟した哺乳類の中枢神経はひとたび細胞死や軸索の切断をきたすと再生することはないと信じられてきた。眼科領域においても、中枢神経系に属する網膜および視神経は再生しないと信じられ、再生医療は夢の話であった。しかし、近年の神経科学および幹細胞研究の長足の進歩により、中枢神経の再生医療が現実のものになろうとしている。
人工多能性幹(iPS)細胞研究で世界をリードする我が国は網膜再生医療で世界の先陣を切って臨床応用が進む可能性があり、既に我々は滲出型加齢黄斑変性に対するiPS 細胞由来の網膜色素上皮シートの臨床研究の実施を開始した。
網膜の再生医療はロービジョンケアにも大きな変革をもたらす可能性がある。従来、ロービジョンケアとは、著しく障害された視機能が医学生理学的に回復を見込めない患者に対して行われるケアであり、基本的には患者の視機能は良くても現状維持、しばしば低下していくことを念頭におかねばならなかった。ところが、網膜の再生医療を施行された患者では、治療により視機能の改善も期待できる。
残された視機能をいかに活用して生活機能を向上させるかがロービジョンケアであったのが、残された視機能そのものが向上していく可能性があるわけである。これはロービジョンケアのパラダイムチェンジと言えるかもしれないし、新たな視能訓練分野の創成に繫がるのかもしれない。ただし、網膜再生医療はまだこれから第一歩を踏み出すところであり、当初はめざましい視機能の改善を期待できるものではない。本講演では、黎明期にある網膜再生医療とロービジョンケアの近未来の展望について考えたい。
【略 歴】
1986年 京都大学医学部卒業、同眼科学教室入局
1988年 京都大学大学院医学研究科
1992年 国立京都病院眼科医師
1993年 神戸市立中央市民病院眼科副医長
1997年 信州大学医学部眼科講師
2000年 ハーバード大学博士研究員
2002年 信州大学医学部眼科助教授
2003年 神戸市立中央市民病院眼科部長代行、
先端医療センター視覚機能再生研究チームディレクター (兼任)
2006年 神戸市立医療センター中央市民病院眼科部長、京都大学臨床教授(兼任)
2008年 先端医療センター病院眼科客員部長(兼任)
2011年 先端医療センター病院眼科統括部長(兼任)
2013年 神戸大学臨床教授(兼任)
患者・家族の精神的サポート
安藤 伸朗 (済生会新潟第二病院)
医者は「治す」ことを目指し、患者は「治る」ことを期待する。しかしすべての医師が「ブラックジャック」ではない。眼科医は、患者が治療後に視機能が回復している時は、喜びを共有できる至福な時を享受するが(日常的になり過ぎて麻痺している場合もある)、一方で重篤な症例の場合は、なかなか視機能が向上せず、忸怩たる思いで悩む。
最大限の治療をしても結果が伴わないとき(患者が望む結果でなかった場合)、最も必要なのは精神的サポート(こころのケア)である。患者のみならず、家族に対するケアも大事である。よく医師と患者は、「疾病」という共通の敵に対して立ち向かうパートナーだと言われるが、それは治療が上手く行った時には当てはまるが、そうでない場合は、ともに「敗者」となってしまい、いい関係を保つことは困難となる場合が多い。
「治療」は医師の誇らしい仕事、「ロービジョンケア」は敗戦処理なのだろうか?私は、すべての眼科医にとってロービジョンケアの理解と精神的サポートが必要だと言いたい。最大限治療しても患者が満足できない視機能に留まった時は、ロービジョンケアの専門医に、その後の対応を委ねよう。保有視機能を活用することにより、患者の生活の質を向上させることが出来る可能性があるからである。
「医学的に良いこと」(網膜剥離が復位する、視力がよくなる、眼圧が下がる、視野が回復する、、、など)を目指して、眼科医は頑張る。ただ、医学的に良くなることが、患者本人が最も望むものであるとは限らない。患者は疾患を持っているが、それ以上に一人のヒトとして生きている。
病気が深刻であればあるほど患者は医師を頼り、医師は必然的に患者の人生に深い関わりを持つようになる。患者の不安を取り除くことができるのは、医師のメスばかりではない。医師が、患者の心理や問題点を認識し理解することが、患者側と医療者側のより良い関係を築く礎になる。そのためにも私たちは、患者との心のこもった会話を欠かすことはできない。
【略 歴】 安藤 伸朗(あんどう のぶろう)
1977年3月 新潟大学医学部卒業
1979年1月 浜松聖隷病院勤務(1年6ヶ月)
1987年2月 新潟大学医学部講師
1991年7月 米国Duke大学留学(1年間)
1992年7月 新潟大学医学部講師(復職)
1996年2月 済生会新潟第二病院眼科部長
2004年4月 済生会新潟第二病院第4診療部長
現在に至る
2011年12月 第17回日本糖尿病眼学会総会(東京国際フォーラム) 会長
2013年 6月 第22回視覚障害リハビリテーション研究発表大会(新潟)大会長