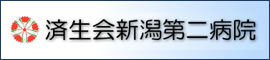第17回日本糖尿病眼学会 (2011年12月3日)
シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(東京国際フォーラム ホールB7-1)
------------------------------------
S-3 ベーチェット病による中途視覚障害の親を通して学んだこと
西田 朋美 (国立障害者リハビリテーションセンター病院 眼科)
【講演要旨】
誰に頼まれた訳でもないが、私の生い立ちが私を眼科医にしたように思う。私の父は、25歳でベーチェット病を発病し、30歳で完全失明した。父は、私たち家族の顔を全く知らないし、私も父の見えている時代を知らない。幼少時、父は盲学校で勤務しており、母が父の送り迎えをしていた。幼い私はよく同行し、盲学校の生徒さんや教職員の方々に大変可愛がってもらった。そんな頃、父は見えていないのかな?と思うことが増えてきた。父は、幼い私にも、ものの色や向きを尋ねたし、母といつも一緒に歩いているし、他の家のお父さんと違うことが多かったからだ。就学前、今でも鮮明に覚えているが、母に父はどうして見えないのか?と聞いたことがある。母は、「ベーチェット病という病気のせいよ。」と答えた。幼いながらも、「どんな病気なの?」と聞くと、母は、「原因が分からない病気よ。」と教えてくれた。その時の母との会話が大きなきっかけとなり、私は医師になろうと思うようになった。短絡的で幼い発想だが、眼科医になれば、父の病気が治せると考えていた。
その後、私は本当に医学部へ進学し、医師になった。しかも、大学卒業後、ベーチェット病を専門にしている大野重昭教授率いる横浜市立大学の大学院へ進学することができた。当時の私は、これでベーチェット病について取り組めると意気揚々としていた。しかし、その反面、疑問に思うこともあった。それは、大学時代や医師となった後の研修でも、種別を問わず、障害や福祉などに関して学ぶ機会がほぼ皆無だったことだ。父や周囲の方々の話を聞いていると、医療と福祉はとても近接しているように思えていたが、実際に医療の中に自分の身を置いてみると、意外なほどに福祉との接点がほとんど見えてこなかった。そのような疑問を感じながらも、当時の私にとっては、ベーチェット病に取り組めるということで、やっと長年の敵と向かい合えるような心境でもあった。
大学院修了後には、米国留学の機会も与えられ、研究を手がける医師として恵まれた環境にいたと思うが、やはり私にとっては、医師になった当初の疑問が逆に大きくなってきた。臨床経験を積むにつれ、「見えにくくなる」というテーマについて、患者と医師のやり取りに接する機会も増えた。ほぼ全ての患者は、見えないということは、恐ろしいことで、何もできないという、ネガティブな言葉で終始していた。それに対する医師側のコメントも「見えなくなったら、大変でエライことですからね」という程度の言葉で会話が終了しているのが大半だった。
私にとっては、何か違うと思うことが増える一方だった。身近で、幼少時から多くの視覚障害者が明るく、前向きに頑張っているのを知っている私にとっては、たとえ全盲になっても、こんなこともあんなこともできるという、前向きなコメントを患者にしてあげたいと思うようにもなってきた。つまり、私はたまたま身近に知る機会があったが、多くの患者や眼科医は、視覚障害者の日常を知る機会がないのだろうとも考えた。そして、医師こそ、障害や福祉について目を向けないと、包括的な本当の医療はできないのではないか?とも思えた。
振り返って考えてみれば、少なくとも私の時代には、各種診断書の書き方ひとつ大学時代や研修でも習ったことはないし、患者が見えにくくなったら、どういうところに行って、どのようなリハビリテーションを受ければいいのかなど、全く眼科の中でも学んだことはない。私も、父がいなければ、このような領域について、全く想像もできないし、わからないことばかりだっただろう。
「失明を 幸に変えよと 言いし母 臨終の日にも 我に念押す」
これは、父が詠んだ短歌である。父がいよいよ失明するのか!?という絶望の淵に立たされていた頃、祖母が入院中の父のところにお見舞いに来た。病状を聞いた祖母は、「失明はだれでも経験することのできるものではないよ。これを貴重な体験として、これを生かした仕事をしてはどうかね。たとえ、それが小さくても社会貢献につながれば生きがいになるのではないかね」という言葉をかけた。すぐには父も言葉を受け入れることはできなったようだが、徐々に祖母の言葉を理解することができ、それが視覚障害者として再出発を果たした父の大きな原動力になった。父は、盲学校勤務の後、自分と同様に中途視覚障害で再出発を目指す人のための施設で、定年まで長きに渡って勤めた。自分が担当する利用者の皆さんにも、折に触れて、祖母の言葉を紹介してきたようだ。今、私も縁が重なり、同系列の病院眼科で勤務をし、ロービジョンケアを必要とする患者と接している。
祖母の言葉は、そのまま私にも当てはまる。中途視覚障害の親を持つ私は、眼科医として何物にも変えがたい貴重な経験をさせてもらっていると思う。今、私は、患者がロービジョンだからと構えることなく、その方が以降の人生をどれだけ満喫できるか、患者に夢を与える眼科医としてサポートしていきたいと考えている。今は、この仕事を選ぶ礎を築いてくれた父と、これまで出会った多くの視覚障害者の方々に深く感謝している。
参考:第9回オンキヨー世界点字作文コンクール 国内部門 成人の部 入選佳作
横浜市 西田 稔 「忘れることのできない母の言葉」
http://www.jp.onkyo.com/tenji/2011/jp03.htm
【略 歴】
1991年 愛媛大学医学部 卒業
1995年 横浜市立大学大学院医学研究科 修了
1996年 ハーバード大学医学部スケペンス眼研究所 留学
2001年 横浜市立大学医学部眼科学講座 助手
2005年 聖隷横浜病院眼科 主任医長
2009年 国立障害者リハビリテーションセンター病院眼科 医長
現在に至る
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「TEAM 2011」3学会合同スリーサム
日本糖尿病眼学会シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(2011年12月3日16:30~18:00:東京国際フォーラム ホールB7-1)
オーガナイザー:
安藤 伸朗(済生会新潟第二病院)
大森 安恵(海老名総合病院・糖尿病センター
東京女子医大名誉教授、元東京女子医大糖尿病センター長)
S-1 1型糖尿病とともに歩んだ34年
南 昌江 (南昌江内科クリニック)
S-2 母を生きる 未熟児網膜症の我が子とともに
小川 弓子(福岡市立肢体不自由児施設あゆみ学園園長;小児科医)
S-3 ベーチェット病による中途視覚障害の親を通して学んだこと
西田 朋美 (国立障害者リハビリテーションセンター;眼科医)
S-4 夫と登る、高次脳機能障害というエベレスト
立神 粧子 (フェリス女学院大学音楽学部・大学院 音楽研究科)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.