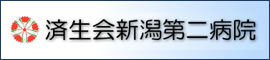報告:第70回(2002年3月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会 宮坂道夫
演題:NBM(narrative based medicine)
-物語論の観点から医療をとらえなおす-
講師:宮坂道夫(新潟大学医学部保健学科講師)
日時: 平成14年3月13日(水)16:00~17:30
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要旨】
1. 〈物語〉の広がり
NBM(narrative based medicine=「物語に基づく医療」)というものが最近注目されるようになってきている。これは何か。特にその核心部分である〈narrative=物語〉とは何だろうか。この基本的な問いに答えるのは、実はたいへんに難しい。物語という語は、最近では人文・社会科学の広い領域で使われており、しかもその意味内容は実に多様である。昨年お話をうかがう機会のあった、この分野に造詣の深いある哲学者は、物語という言葉は使う人によって意味が違うと言っておられた。文献を眺めていると確かにその通りで、姿形の異なる樹木が立ち並ぶ雑木林に踏み込んだような気になってくる。それでも、物語という言葉の定義よりも、それを使おうとする人たちの動機や関心の流れを追ってゆくと、何となくではあるが、この語が医療も含めた幅広い分野で使われるようになってきた理由が見えてくるように思う。
医療者が関心を抱く物語とは、患者が病や実人生について語る〈生の物語=life narrative〉である。しかし、物語という言葉を聞いてまず思い浮かぶのは、『源氏物語』のような文学作品としての物語の方だろう。患者の語る物語と文学フィクションとではまったく別物に思える。しかし、両者をよくよく比べていくと、実はそんなに大きな違いはないことがわかってくる。どちらも始まりがあって、終わりがある。語り口は様々だが、様々な出来事の叙述がある。患者の物語も文学作品も、例えばカルテのような〈事実の記述〉以上の情報を含んでいる。そこに登場する人々がとった行動だけでなく、その時に何を見て、何を思ったかが語られる。〈語られないこと〉もある。何を語り、何を語らないかを取捨選択するのは、患者であり、作者である。
このような類似性は、文学研究の一領域である〈物語論=narratology〉では、もはや当然のこととして受け入れられている。たとえば、ジュネットによれば、物語とは・物語内容(イストワール)(語られた出来事の総体)、・物語言説(レシ)(それらの出来事を物語る、発話されるか書かれるかした言説)、・語り(ナラシオン)(語るという行為そのもの)という三つの側面を持っている。『源氏物語』といえば、私たちはその話の内容(物語内容)にばかり注目しがちだが、語り手と聴き手の存在や、語り聴くという行為、および物語を伝える媒体にまで視点が拡大しているのである。
2. 〈物語〉の背後にあるまなざしの転換
このような視点の拡大は、現代思想の潮流と深く関係している。その潮流をあえて一言でいうならば、〈正当なものとして権威づけられ、固定されたまなざしの正当性への疑問〉といえるように思える。たとえば、「正常者」と「異常者」の線引きへの疑問(フーコー『狂気の歴史』)、「世界の中心」である西洋社会と「辺境」である非西洋社会という世界認識への疑問(レヴィ・ストロース『悲しき熱帯』)、政治や経済の歴史を「正史」と見なして普通の人々の生活史を記述しない歴史認識への疑問(アリエス『死を前にした人間』)というように。こうした思想家たちは、従来は顧みられることもなかった「普通の」(あるいは「異端の」)人々がそれぞれに生きている固有の〈生の物語〉の中に、人間や社会の真実を見いだそうとした。フーコーは精神病患者を長年にわたって観察し、レヴィ・ストロースは文明化されていない部族の中に入って生活を共にしながら彼らを観察した。アリエスは「日曜歴史家」と自称して、一般大衆の日記などを収集した。彼らに共通しているのは、現実は単なる科学的事象とは違って、その現実を生きる人それぞれの視点によって異なったものであり、さらにそれが語り手から聴き手へと語られることで、意味づけられ、解釈され、形づくられてゆくものだという認識である。
3. 医療における〈物語〉
このような流れから考えれば、NBMの位置づけも見えてくる。NBMはしばしばEBM(証拠に基づいた医療)との対比で語られる。これは、NBM自体に、「〈患者〉ではなく〈病気〉を見る」という近代医学のまなざしへの反省が込められていることをあらわしているように思う。医学的データからは最適な治療法でも、患者にとってはそうではない場合もあるかもしれない。たとえば、医学的適応だけでなく、患者のQOLを視野に入れて治療やケアの方法を選択することは、今日では当然のこととされているはずだが、QOLの評価は「証拠に基づいた客観的評価」だけでは不可能であり、個々の患者に固有の価値観に基づいて評価すべきものである。したがって、医療者は、患者個々の生のなかで抱かれている価値観を知るために、患者個々の生の物語に耳を傾けざるをえない。そこからNBMが始まる。
これは患者の立場からすれば歓迎すべきことで、まさに「患者中心の医療」の実践にほかならない。しかし、医療者の側にとっては必ずしも簡単なことではない。NBMを誠実に実践しようとすると、一つの難問に悩ませられることになる。それは、物語をどう評価し、解釈し、理解すればよいのかという問題である。患者の物語に耳を傾けること自体はよいとして、その物語をどう捉え、臨床判断にどう反映させてゆけばよいのか。たとえば容易に想像がつくリスクは、患者の物語を、医療者の都合や偏見によって過度に単純化してしまったり、「いかにもありがちな」ステレオタイプなストーリーに当てはめてしまうことであろう。「患者の物語」が、いつの間にか「医療者の物語」に作りかえられてしまう。こうしたことを避けるにはどうしたらよいのか。
この難問に取り組もうとしているのが、早くから物語を積極的に利用してきた領域、つまり精神医学、臨床心理学だと思う。この領域では、患者の物語を語り聴くことそのものがケアとして成り立っている。医療者は患者の物語を、患者自身が語ったり、意味づけたりするのを促したり、手助けしたりする。ここで紹介することはできないが、どこまで患者の物語に立ち入るべきか、どのような価値観に基づいて意味づけを促すかについて、すでに様々な議論が行われている。
むろん、一般の医療では、患者の物語をめぐって、ここまでの働きかけをする必要はあまりないのだろう。それでも、患者の物語を基礎に置いて、そこから何らかの臨床判断をしてゆくのであれば、医療者は自分の立場を決めなければならないようにも思う。「事実は小説より奇なり」というように、患者の物語は文学フィクション以上に複雑な、深い森のようなものである。それを外から眺めているのか、そこに分け入ってゆくのか。黙って「森の声」を聴いているのか、それとも何らかの働きかけをするのか。このような問いかけをしてゆくことが、NBMの本質として求められるような気がする。そして、このような問いかけを深めてゆくと、患者の側だけではなく、医療者の側にも各人に固有の〈生の物語〉があることに突き当たるのではないだろうか。NBMとは、そうした気づきの上に成り立つものであってほしい――これは筆者の素朴な感想にすぎないが。
NBMはしばしばEBM(証拠に基づいた医療)との対比で語られる。これは、NBMに、「〈患者〉ではなく〈病気〉を見る」という近代医学への反省が込められていることをあらわしている。医学的データからは最適な治療法でも、患者にとってはそうではない場合もある。医学的適応だけでなく、患者のQOLを視野に入れて治療やケアの方法を選択することは、今日では当然のはずだが、QOLの評価は「証拠に基づいた客観的評価」だけでは不可能であり、個々の患者に固有の価値観に基づいて評価すべきものである。
したがって医療者は、患者個々のなかで抱かれている価値観を知るために、患者個々の生の物語に耳を傾けざるをえない。そこからNBMが始まる。これは患者の立場からすれば歓迎すべきことで、まさに「患者中心の医療」の実践にほかならない。しかし、医療者の側にとっては必ずしも簡単なことではない。「患者の物語」が、いつの間にか「医療者の物語」に作りかえられてしまう事がある。こうしたことを避けるにはどうしたらよいのか、、、、、
【略 歴】
早大卒業後、阪大で修士、東大で医学博士を取得。
現在は新潟大学医学部講師。生命倫理・医療倫理の専門家。