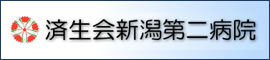報告:第84回(2003‐5月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会 栗原隆
演題:「共感とケアの成り立ち」
講師:栗原隆 (新潟大学教授;生命倫理)
日時: 平成15年5月14日(水) 16:30~18:00
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要約】
1 他人の痛みは分かるか? 心はどこに存在するのか
他人の痛みは分からない。私の歯が痛む時、隣の人は快適に過ごしているかもしれない。私の足が痛くて、歩くのさえ辛い時、ひょっとすると足を引きずっていることで、足が痛そうだということが察知されることもあるかもしれないが、それでさえ、私の足の痛みを他人は感じることはない。ひょっとすると、あなた自身は人間でも、他人はアンドロイドかもしれない、いやロボットかもしれないし、異星人かもしれない。私たちは他人については何一つ自分のことのように知ることができない。それでいて、おおむね経験上、周囲の人々が自分と同じ人間であると想定して、振舞っている。それはある種思い込みかもしれない。なぜかというと、私がワイシャツの胸ポケットに入れておいた小銭がポケットに開いた穴から落ちて、体を滑り落ちてゆくのを止めようとおなかを抱きかかえた時、人は、私が腹痛に苦しんでいると思うかもしれない。目でウインクしたのに、単にゴミが入ったと思われるかもしれないからである。
私たちは、他人の痛みを何ら体験することはできないが、ある程度は、その身振りや仕草、さらには言葉で訴えるものから、自分の体験を振り返って、それに基づいて類推する。主観的な根拠に照らし合わせての類推であるからして、相手に生じている事態を言い当てることもあるかもしれないが、外れることもある。私たちは、他人を類推することしかできないのかもしれない。痛みだけでなく、相手の気持ちだってそうである。たとえ、言葉でコミュニケーションを図る時でさえ、相手を理解したと思っていても、実は自分の理解でしかない。そのことは次の俳句の例から明らかである。
古寺に 斧こだまする 寒さかな
わが恋は 空の果てなる 白百合か
実は、この俳句はコンピュータで文字を配列しただけのものなのである。きわめて簡単なプログラムだというが、デモンストレーションしているところに来た客が、「ヒヤヤッコ」と入力したらたちどころに、
冷奴 我が影にさす 酒の酔いと答えたという。
それを見ていたご婦人が、それでは私もと「夏草や」と入力したら、コンピュータは今度は
夏草や 盛り過ぐらむ 身の嘆き
と応じたという嘘のような本当の話が報告されている(『理想』一九八三年一二月号水谷静夫「国語研究と計算機」)。
たとえば、この場合、文字列が俳句だと思われようと思われまいとに関わらず、作者というものが存在していると見なす立場もあろう。そうした立場では実際の作者はコンピュータ、あるいはプログラマーということになるかもしれない。こうした立場をさしあたり、作者についての「実体論的把握」と整理しておこう。
これに対して、作品というものは読まれることによって初めて成立するのであって、作者とは厳然と実体のように存在しているのではなくて、読まれ、作品と見なされてこそ作者というものが、俳句の背後に虚焦点のように想定されるのであるからして、文字列を読み取り、解釈して、理解して、思いや感慨を抱いて、作品を作品たらしめるのは、実は読み手自身の心情や思想や体験に他ならないとする立場も可能である。こうした立場によれば、作者は読み手になる。これをさしあたり、作者についての「関係論的把握」と呼んでおこう。
私たちは、自分なりにその言葉の羅列を、俳句だと解釈して、そのうえで、作者の気持ちを類推しているのである。普通なら、理解したと思う言葉によるコミュニケーションでさえ、これである。相手への思いやりというものがいかに不確かなものであるか、ということはもって瞑すべしである。
心というものは、ある存在者、人間なりコンピュータなりペットなり、相手そのものに内在している何らかのものだ、と心を想定する立場は実体論的な把握だと言えよう。これに対して、心とは他の存在者との関わりの場において成立する解釈の対象なのだ、とする立場は関係論的な把握ということになろう。
〈心〉だけではない。たとえば、〈情〉とか〈共感〉、〈思いやり〉などというものも、私たちは持ち合わせているわけでは決してない、ただ、その場の状況において、そのように受け取られることがある。〈心ある〉行為や〈情け深い〉応対、相手への〈共感〉の表明だと、相手に受け取られるところにおいて、〈心〉が現出する、というわけである。
2 共通感覚と体性感覚
近代に入って成立した市民社会では、不特定多数の人間の交流が生じることによって、これまでの倫理とは違う価値観が生まれることになった。「共感」や「同情」という観念も市民社会時代を迎えるに当たって、新たに生まれた感覚だった。確かに、古代ギリシア以来、コモン・センスの観念はあった。ところがそれは、決して社会の中で人々が共通に抱くセンス・感覚という意味ではなかった。むしろ、「もともとコモン・センスは、諸感覚にわたって共通で、しかもそれらを統合する感覚、私たち人間のいわゆる五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に相わたりつつそれらを統合して働く総合的で全体的な感得力「(中村雄二郎『共通感覚論』岩波書店七頁)のことだったと言われている。
こうした共通感覚、それぞれの感覚を統括する共通感覚として想定されていたのは何であったか。そもそも五感の間で優位な位置を占めているのは、今では視覚だと思われているが、中世までは聴覚であったとされている。聴覚→触覚→視覚、という順だったというのである。「一方で、キリスト教会がその権威をことばという基盤の上においており、進行とは聴くことであるとしていたからである。聴覚の優位は一六世紀においても、神学に保障されてまだ強かった。『神の言葉を聴くこと、それが信仰である』『耳、耳だけがキリスト教徒の器官である』とルターも言っている」(前掲書五四頁)。理性は、感性や気力さらに常識に比べて、人間の能力の中で最も高次なものと見なされているが、ドイツ語の理性はVernunftであって、つまり聴解する(vernehmen)に由来することばである。ところが、「近代文明は、触覚と結びついた形での視覚優位の方向では発展せずに、むしろ触覚と切り離されたかたちでの視覚優位の方向で展開された」(前掲書五五頁)。印刷術や遠近法、機械論的な自然観は、視覚優位の文化の産物であった。印刷術は「知」の組み換えをじつげんして、遠近法は「主体」の成立を促すことになった。機械論的な自然観は自然を対象化することを通して、人間による自然の解明、克服、征服を可能ならしめた。
しかし、視覚は本当に五感の中で優位にたつ認識能力なのであろうか。この問題は実に、近世哲学を貫いた枢軸の基本問題だったのである。すなわち、私たちの外側に広がる空間において外見として見えるものは、見るだけでそのように認識されるものかどうか、ロック、バークリ、ライプニッツ、ヴォルテール、コンディヤック、ディドロらがそれぞれに解釈を加え、さらにはルソーやヘルダーなどをも巻き込んだモリヌークス問題で検討された主題である。視覚だけで認識することができるのか、それとも外界の認識に触覚の働きを無視できないのか、という論争だと言い換えてよい。先天盲の開眼手術後の認識をめぐって、球と立方体を弁別できるかどうかを実験した結果、ロックやバークリーは視覚的認識に先立つ触覚の重要性を語ったのに対して、ライプニッツは視覚の優位性を肯定的に捉えた。ディドロは触覚の重要性を認めつつも、視覚だけで見えるとしたのに対して、ヘルダーによっては空間表象における触覚の根源性が語られもした。「遠近法」による視野の主体的な構成の問題と並んで、近世哲学の枢軸をなした問題であった。
本来、共通感覚というのは、一人の人間における互換に共通する感覚のことであったが、その中の一つ、触覚を媒介として私たちは、他者や自然との共感が可能になるならば、〈心〉なるものを持ち合わせていないわたしたちにとって、まさしく〈ふれあい〉は〈心〉を感じさせ、他者との共感を結ぶものだと言えよう。もちろん〈手当て〉はそうした〈触れ合う心〉を最大限に実現するものである。
3 市民社会における道徳様式の変貌
そもそも思想史を振り返ってみるに、触覚の重要性が見直されるようになったのは、不特定多数の人々が交流しあう市民社会の成立期で、「共感」概念が新たな意味合いを帯びるようになったのも、時代を同じくしているのである。一八世紀にエジンバラの医学校の教授であったジョン・グレゴリーは、その著『医師の義務と資質に関する講義』(一七七二)において、共感概念を用いて患者の利益を最大限に考えて行動するように、美徳と関連付けたのである。
ヒュームは『人性論』でこう述べている。「かりにもし私がかなりこわい外科手術に立ち会うとすれば、確かに手術の始まる前においてすら、手術具の準備・秩序よく並べられた包帯・熱せられた手術刀・患者及び付添い人の心配と憂慮のあらゆる表徴、それらは私の心に大きな効果を及ぼして、憐憫と恐怖とのもっとも強い心持を喚起しよう。いったい、他人のいかなる情緒も直接には我々の心に現出しない。我々はただ、他人の情緒の原因あるいは結果を感知するだけである。これらから我々は情緒を推論する。従って、これらが我々の共感を生起するのである」(ヒューム『人性論(四)』岩波文庫一八六頁)。すなわち他人の心情を類推する能力のことを「共感」と呼んでいるわけである。
ヒュームは「共感」に道徳的な心情の基礎を求めている。「この同じ{共感の}原理が美的心持〔ないしは情操〕を産むのみならず、多くの場合に道徳的心持〔ないし情操〕を産むのである。〔例えば正義の徳がそうである。いったい、〕正義ほど敬重される徳はなく、不正義ほど忌み嫌われる悪徳はない」(前掲書一八七頁)。市民社会での生活においては「正義」は必要不可欠な倫理である。それは個人個人によって違っていては、正義とは呼ばれない。自分と他人の壁を超え、身内・知人・友人の枠を超えて、普遍的な価値観であってこそ初めて、正義たり得るのであるから、そのために「共感」能力が求められることになる。「我々自身の利害や友人の利害に関わりない社会的善福は、ただ共感によってのみ快感を与える。従って、共感こそ、あらゆる人為的徳に対して我々の払う敬重の源泉である道理になる。こうして、共感は人性の甚だ強力な原理であること、共感は我々の美的鑑識に非常な影響を及ぼすこと、共感はすべての人為的徳における我々の道徳的心持〔ないし情操〕を産むこと、これらの点は明らかである」(前掲書一八八頁)。
こうした共感の成り立ちをヒュームは次のように説明している。「他人の現在の不幸が私に強く影響したとする。そのとき、想念の活気は単に直接の対象に局限されない。(……)該人物のあらゆる事情について、過去と現在と未来とを問わず、可能的と蓋然的と絶対確実とを問わず、生気ある観念を私に与える。この生気ある思念によって、私はそれらの事情に関心をもち、それに参与する。そして、私が該人物のうちに想像するすべてのものに適合した共感的な動きをわたしの胸のうちに感じるのである」(ヒューム『人性論(三)』岩波文庫一六六頁)。すなわち、他人に共感するためには、それも目の前に見えない事情にまで共感するためには、相手に対する「関心」、そして自らの側には「想像力」が必要だ、というわけである。
ヒュームに連なるアダム・スミスは、その著「道徳感情論」で、たとえ「人間がどんなに利己的なものと想定されうるにしても、あきらかにかれの本性のなかには、いくつかの原理があって、それらは、彼に他の人びとの運不運に関心をもたせ、彼らの幸福を(……)彼にとって必要なものとする」(アダム・スミス『道徳感情論(上)』岩波文庫二三頁)として、そうした原理を「哀れみ(ピティ)」と「共感(シンパシー)」に見定めている。「われわれは、他の人びとが感じることについて、直接の経験をもたないのだから、彼らがどのような感受作用を受けるかについては、われわれ自身が同様な境遇においてなにを感じるはずであるかを心にえがくよりほかに、観念を形成することができない」(前掲書二四頁)として「想像力」の働きを重視している。「われわれの想像力が写しとるのは、かれのではなくわれわれ自身の、諸感覚の印象だけなのである。想像力によってわれわれは、われわれ自身をかれの境遇に置くのであり、われわれは、自分たちがかれとまったく同じ責苦をしのんでいるのを心にえがくのであり、われわれはいわばかれの身体にはいりこみ、ある程度かれになって、そこから、かれの諸感動についてのある観念を形成するのであり、(……)なにか感じさえするのである」(前掲書二五頁)。利己的でありながら、合理的な人間たちの集う市民社会にあって、個別実体たちを繋ぐ唯一の絆とも言うべきものが、この「想像力」だったと言えよう。
4 ケアの成り立ち
「共感」は、実体としての〈心〉を持ち合わせず、しかも、他者の痛みや心情を類推するしかできない私たちにとって、他者の〈心〉を想定し、かつ自分の〈心〉を表明する能力、つまり「関係論的な把握」を可能にする能力だ、と言えよう。
今日の医療の現場では、患部や病巣の治療に主眼を置く「キュア」に対して、患者を善人格的な存在として捉えて看護する「ケア」は、「キュア」が実施不可能な病状を迎えることもあるのに比して、たとえ患者がどのような状態に陥ったとしても、実行できることから、その重要性が指摘されている。
また、つぎのように、医療の実施体制の組み換えを迫るものとしても期待されている。すなわち、「ケアの倫理は、病の了解がその中心を得て、人間へと統合されることを不可欠とみなす。そうでなければ、患者中心の医療、全人的ケア、医療のうちへの人間性の回復といったことは不可能だからである。したがって、われわれは少なくとも心身統合の、そしてそこから出発すると言う意味では心身合一の医療を構想する必要がある」(松島哲久「現代医療における倫理性の復権」世界思想社刊『生命倫理学を学ぶ人のために』二一九頁)。
キャロル・ギリガンの『もう一つの声』(一九八二)は、今日の私たちの間での「ケア」を考える上で大きな一石を投じた書である。妊娠中絶と言う具体的な問題に即して女性達から聞き取り調査を実施した結果から、彼女は、男性と女性の性差に基づく「ケアの倫理」を明らかにした。つまり、道徳的な葛藤状況に陥った時に、女性は、具体的な人間関係の親密さ・疎遠さを軸に対処する傾向があるのに対して、男性は、平等・不平等を道徳の軸にすえる傾向が強いというのである。女性は人間関係を保持し、より強化する方向で道徳的な葛藤状況を解決しようとするのに対して、男性は、道徳的な葛藤を権利主張の対立と捉えて、「公正」や「自律」を重視するのだそうである。彼女はこうした女性の倫理を「ケアの倫理」と、そして男性の倫理を「正義の倫理」と呼ぶ。
正義は、人間一人ひとりを絶対的に自立した主体として捉え、「自律」に倫理の実体を求める。これに対して、ケアは、他者への共感のうえに成り立つ。その意味では、倫理性の実体論的な把握と、関係論的な把握と言い換えても良いかもしれない。正義では原理が大切で、ケアでは関係が大切だとも言えよう。正義では、相互の権利が重要視されるなかで、公正さが〈合法性―非合法性〉を尺度に測られようし、ケアでは、不均衡な関係において〈境遇の良否と慈愛の配分〉による全体としての調和がもたらされるのかもしれない。正義にあっては、普遍的な原理が支配するが、ケアにあっては、個別具体的な対処が重要視されよう。正義にあっては、利己性は合理性をまとわなければならないが、ケアにあっては、利己性は生きるという観点で許容される、など。
小括
痛みを、確かに私は感じている。そして、誰もこの痛みを共有することはできない。と言っても医療従事者は私の仕草を見て、私が痛がって、痛みに堪えかねていることを「想像」できる、ようである。どの程度の痛みであるか、まで。そのとき、痛みは私と医療従事者の関係を結ぶ形で表現されているのであろう。〈心〉も似た状況にある。私たちは実体としての〈心〉を持ち合わせてはいないようである。しかし、〈心無い〉振る舞いもあれば、〈心温まる〉言葉もある。大森荘蔵は次のように述べている。「私の『心』というものがあるとすれば、この『ここにいる私』と『そこに見える風景』が作るこの全状況が『心』であるいがいにはない。『私の内に』ある心などはどこをさがしてもないのである」(大森荘蔵『物と心』東京大学出版会七二―七三頁)。心が想定されるとすれば、それは、関係論的な観点からのみに他ならない、そして、共感やケアというものが成り立つとすれば、実態的にこれが共感だ、これがケアだ、というものはなく、むしろ、それも関係論的な観点からに他ならない。この「ここにいる私」と「そこに見える相手」が作るこの全状況にこそ、共感やケアの成り立ちが立ち現われていると言うことができよう。
【略 歴】
万代小学校三年まで新潟市、長岡高校、新潟大学人文学部哲学科を卒業、東北大学大学院文学研究科(修士課程)、神戸大学大学院文化学研究科(博士課程)を修了した後、神戸大学大学院文化学研究科助手、神戸女子薬科大学非常勤講師を経て、1991年から新潟大学教養部助教授、1996年から人文学部教授。専門は、生命倫理学、環境倫理学、近世哲学(ドイツ観念論)。
【後 記】
参加者の方から感想が届いています。
・「心の話」とても楽しく不思議な栗原ワールドに、はまりました。「心」ってほんとにどこにあるのでしょう?目に見える物が全てで、「心なんて無い」と聞かされても、ナタラジャの美味しいカレーと、楽しいお話しで、無いはずの「私の心」は、確実に元気ななりました。タージマハールの写真も宝物です。ありがとうございました。
・栗原先生のお話は、日頃私たち教師が行っている「子どもの行動の見取り」について大きな警鐘を鳴らしていただいたように感じました。とかく教師は子どもの一面のみを見て評価しがちです。しかし、今回の栗原先生のお話を伺って、子どもを様々な角度から見取る力を身に付けたり、多くの教師で一人の子どもについてディスカッションしたりしなければならないと感じました。これからの勉強会がますます楽しみです。
・私の勉強不足ということもあり、難しかったような気がします。ただ痛感させられたのは、先生もメールに書かれていましたが、「こころ」は受け取り側の問題でもあるということが、すごい印象に残りました。今まで、『こちら側が「こころ」を開いているのに、相手が壁を作ってしまって、「こころ」通じ合わすことができない。』と思っていたのは、実は自分の中で、勝手に「こころ」開いていると思い込んでいただけで、実は、私の方が「こころ」開いていないと思っていたのかもと、改めて反省しております。