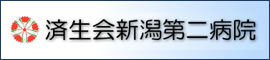もう4年も前のことですが、第17回日本糖尿病眼学会総会を主催しました(会長~安藤伸朗;2011年12月2日~4日:東京国際フォーラム)。
本来、糖尿病の眼の合併症に対して、眼科医・内科医・医療スタッフが討論するという学術的な学会でありますが、あえて下記シンポジウムを行いました。ここで改めてその内容を紹介致します。
シンポジウム「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(12月3日16:30~18:00:東京国際フォーラム ホールB7-1)
オーガナイザー:
安藤 伸朗(済生会新潟第二病院)
大森 安恵(海老名総合病院・糖尿病センター、
東京女子医大名誉教授、元東京女子医大糖尿病センター長)
S-1 1型糖尿病とともに歩んだ34年
南 昌江 (南昌江内科クリニック)
S-2 母を生きる 未熟児網膜症の我が子とともに
小川 弓子(福岡市立肢体不自由児施設あゆみ学園園長;小児科医)
S-3 ベーチェット病による中途視覚障害の親を通して学んだこと
西田 朋美 (国立障害者リハビリテーションセンター;眼科医)
S-4 夫と登る、高次脳機能障害というエベレスト
立神 粧子 (フェリス女学院大学音楽学部・大学院 音楽研究科)
報告(その1)オーガナイザーの言葉、南先生講演要約
------------------------------------
【オーガナイザーの言葉】
安藤 伸朗(済生会新潟第二病院)
大森 安恵(海老名総合病院・糖尿病センター、
東京女子医大名誉教授、元東京女子医大糖尿病センター長)
私たち医師は、データに基づいたEBM中心の医療を実践していますが、患者の心のうちをどこまで理解して診療しているのか、疑問に思うことがしばしばあります。
医者と患者の接点は病気であり、病院(医院)では医者も患者も病を治そうと思っています。しかし患者にとって病気は、幾つもある気掛かりなことの一部であり、他に沢山の悩みも抱えています。時に経済的なこと、時に対人関係、時に会社や学校のことであったりします。
病気を治す主役は患者で、医師はサポーターであると言われます。その意味では患者と医者は対等ですが、本当にそうでしょうか?英語で患者は「patient」ですが、「patient」という単語には「耐える」、「辛抱する」という意味がありま、「be patient」とは、「耐えなさい」、「辛抱しなさい」ということです。患者patientとは、洋の東西を問わず、耐えることを強いられた存在なのかもしれません。
病院hospitalが、患者にとって安らぐことのできる場、ホスピタリティーを感ずることのできる場となるためには、何よりも医療従事者が、患者の気持ちを理解する(理解しようとする)ことが大切ではないかと考えます。
本シンポジウムでは、患者さん・ご家族に、病との闘い方・付き合い方、そして本音をご自身の言葉で語って頂きました。登場するシンポジストは、ご自身あるいは家族が病と闘っている3名の現役医師と1名の大学教員(教授)です。ご自身の物語を客観的に述べることができる方々でした。
患者・家族の声に耳を傾け、想いを共有し、現場の医療を見つめ直す機会に出来ればと思います。
------------------------------------
S-1. 1型糖尿病とともに歩んだ34年
南 昌江 (南 昌江内科クリニック)
【講演要旨】
私は34年前の夏に1型糖尿病を発症しました。当初は親子とも落胆し将来を悲観しましたが、その後尊敬する医師との出会いによって人生が変わってきました。
16歳で小児糖尿病サマーキャンプに参加しました。本心は参加したくなかったのですが、主治医から半ば強制的に参加させられました。そこで、病気に甘えていた私たちに、ボランティアのヘルパーから、「糖尿病があるからといって社会では決して甘く見てくれない。これから糖尿病を抱えて生きていくなかで沢山の壁にぶつかるだろう。その壁を乗り越えられる強さを持ちなさい。」と話をされました。これまで病気を理由にいろいろなことから逃げていた自分に気がつき、その頃から病気とともに生きていく覚悟が出来、将来は「医師になって糖尿病をもつ人の役に立ちたい」と思うようになりました。
医師になって念願の東京女子医大糖尿病センター、平田幸正教授の下で医師の第1歩を踏み出しました。医師になったばかりの私に、平田先生は「あなたは貴重な経験をしている。同じ病気の子供たちのためにも、是非自分の経験を本に綴ってみてはどうかね?」というお話をいただきました。しかし研修医時代は不規則な生活が続き、糖尿病のコントロールも良くない状態で、こんな自分が糖尿病の患者さんを見る資格はないのではないかと内科医をあきらめかけた時もありました。医師になって3年目、今度は肝炎を患いました。糖尿病になって、一生懸命に頑張ってきたのにどうしてまたこんなに辛い思いをしなくてはいけないのだろうと、本当に辛い時期でした。3か月の休養をいただきましたが、その時に、ふと、以前平田先生からいただいたお話を思い出し、「こんな状態の自分でも、少しずつ自分の体験を綴ってみることはできるのではないだろうか」と思い、その後福岡に帰って勤務医を続けながら、私の経験が糖尿病の子供たちに勇気と希望を与えることができればと思い、「わたし糖尿病なの」を出版しました。
1998年に糖尿病専門クリニックを開業し、多くの糖尿病患者さんと接しています。診療の傍ら、講演や糖尿病の啓発活動を行っています。2002年に初めてホノルルマラソン(フルマラソン)を完走することができました。その時の感動は、今でも忘れられません。30kmを過ぎると本当に辛かったですが、最後のゴールを前にした時には、これまで生きて来て、辛かったことが走馬灯のように思い出され、一気に消えていきました。出会ったすべての方々への感謝と、本当に生きてきて良かった、という思いを天国の父に伝えたくて、涙を流しながらのゴールでした。
それまでは、合併症の危険性など自分の10年先の将来に自信がなかったのです。「将来、目が見えなくなるかもしれない、透析になるかもしれない。」という糖尿病の合併症の心配がどこかで自分を臆病にしていました。フルマラソンを完走できたことで、自分の体力・精神力に自信がつきました。この体験をきっかけに、(大きな借金をして)新たにクリニックを新築し、自分が長年理想としてきた糖尿病の診療をしています。
そして、“No Limit”をモットーに、“糖尿病があっても何でもできる”ことを一人でも多くの患者さんに理解して体験して頂きたいと思い、“TEAM DIABETES JAPAN”を結成し、毎年患者さんや医療関係者と一緒に参加しています。今年も無事に10回目のホノルルマラソン(2011年12月11日)を完走することができました。
自分の人生を振り返った時に、生き方や考え方を教えてくれたのは両親です。 父からは、高校生の頃に 「お前はハンディを持っているのだからその分、人の2倍も3倍も努力しなさい。」 「嫁には行けないだろうから、一人で生きていくために資格を取りなさい。」 「病気があると金がかかる。自分の医療費は自分で払えるように経済力を持ちなさい。」 と病気がある私にあえて厳しく育てられました。
私が大学受験で国立大学医学部に失敗して、浪人させてほしいと父にお願いした時には、「人より人生が短いのだから、1年でも無駄にするな。私立大学に合格したのだからそこで勉強して少しでも早く良い医者になりなさい。」と言われました。小さな電気屋を営んでいた我が家の家計では私立の医学部は到底難しかったと思いますが、両親は私のために必死で働いて卒業させてもらいました。それまで父には反抗していましたが、その時に父の愛情を深く感じました。そんな父が、2001年に癌で亡くなる前に、「もうお前は一人で生きていけるな。お母さんのことは頼んだよ。」と逝ってしまいました。
病気を持つ私に、強く生きていきなさいと育ててくれた父、いつでも「ありがたい、幸せ。」と感謝の言葉が口癖の母、そしてこれまで私が出会った方々や医学から受けた恩恵に感謝し、一日一日を大切に「糖尿病を持つ人生」を明るく楽しく自然に、いつまでも夢を持って走り続けていきたいと思っています。
最後に、私にとって1型糖尿病とは? “素敵な試練”でしょうか?
【略 歴】
1988年 福岡大学医学部 卒業
東京女子医科大学付属病院内科 入局
同 糖尿病センターにて研修
1991年 九州大学第2内科糖尿病研究室 所属
1992年 九州厚生年金病院内科 勤務
1993年 福岡赤十字病院内科 勤務
1998年 「南昌江内科クリニック」開業(福岡市中央区平尾)
2004年 福岡市南区平和に移転
現在に至る