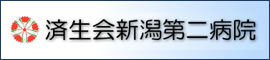「学問のすすめ」第7回講演会 済生会新潟第二病院眼科
1)iPS細胞-基礎研究から臨床、産業へ
高橋 政代 (理化学研究所)
2)遺伝性網膜変性疾患の分子遺伝学
中沢 満 (弘前大学大学院医学研究科眼科学講座教授)
日時:2012年6月10日(日) 9時~12時
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
リサーチマインドを持った臨床医は、新しい医療を創造することができます。難題を抱えている医療の現場ですが、それを打破してくれるのは若い人たちのエネルギーです。本講演会は、若い医師とそれを支える指導者に、夢と希望を持って学問そして臨床に励んでもいたいと、2010年2月より済生会新潟第二病院眼科が主催して細々と続けている企画です。
今回は、iPS細胞を利用した網膜色素変性の治療に意欲を燃やす高橋政代先生(理化学研究所)、遺伝性網膜変性疾患のお仕事を精力的にされている中澤満先生(弘前大学眼科教授)に講師をお願いし、若い人へのメッセージを添えて、先生方の取り組んでこられた研究テーマを中心に、これからの医療を背負う人たちに、夢を持って仕事・学問をしてもらいたいという願いを込めて、これまでの学究生活を自叙伝風に語って頂きました。
============================
iPS細胞-基礎研究から臨床、産業へ
高橋 政代 (理化学研究所)
============================
【講演要約】
卒業以来25年余り、臨床と研究と軸足を置き換えながら、それでもずっとどちらからも離れることなく続けてきた。5年前に京都大学から理化学研究所に移ってからは臨床は週2回の網膜変性疾患専門外来のみになったが、治療開発である我々の研究のためには臨床を離れて研究だけになってしまってはいけないと考えていた。基礎研究は重要であるが、それだけでは治療はできない。治療という出口を知る臨床医が応用研究をすることは重要なことである。
網膜再生医療研究の始まりは、1996年にアメリカサンディエゴのソーク研究所の脳研究で有名なGage研究室に留学した時であった。その際にまだ概念も定まっていなかった神経幹細胞の研究に出会った。いくつかの分野の境界領域で新しいものは生まれやすい。眼科医が脳神経研究という分野に飛び込み、神経幹細胞という概念にふれたことで、幹細胞による網膜再生(=網膜細胞移植)という新しい治療研究が芽生えた。それは神経幹細胞に出会った眼科医であれば誰でも考えつくことであった。
神経幹細胞を使えば網膜の難病が治療できると意気揚々と留学から帰って研究を続けたが、そう簡単ではなかった。様々な幹細胞を検討したが一長一短があり、2000年代初めからはES細胞の研究に移行した。ES細胞から網膜の治療に必要な網膜色素上皮細胞や視細胞が作れることを発表し、ES細胞から作った網膜色素上皮細胞は網膜治療に使えることを初めて示していた。しかし、網膜色素上皮細胞は他人の細胞の移植では拒絶反応を起こすことが胎児細胞移植で知られており、網膜の病気のために免疫抑制剤を用いて身体を危険にさらすことには躊躇を覚えた。また、日本ではES細胞は臨床には使えないという声が多く聞かれた。まごまごしているうちに、アメリカの企業はそんなことはお構いなしに免疫抑制剤を用いてES細胞由来網膜色素上皮細胞の臨床試験を着々と準備しているという情報が入り愕然とした。その頃、京都大学の山中先生によってiPS細胞が発明されたのである。iPS細胞は大人の皮膚細胞からES細胞と同じ性質の細胞が作れるので、患者さんの皮膚からiPS細胞を作り、さらに網膜細胞にすれば拒絶反応のない自分の細胞を移植できる。これで完成だと思った。
そこから、研究レベルであった細胞の作り方などを大急ぎで臨床レベルの品質に作り上げ、できた細胞の安全性や品質を完璧に確認して、iPS細胞が発明されてから5年で臨床を考えられるところまで漕ぎつけた。これには、iPS細胞の力、魅力によって産官学の多くの方々の協力が得られたことが大きい。当初、日本の場合は厚労省の規制が最も難関と考えていたが、それも指針などがどんどん改訂されて、iPS細胞を用いた治療が行えるように先回りして整備されて行っている状態である。むしろ基礎科学者や新しい治療開発に慣れていない眼科医の先生方の方が(必要以上に)厳しいと感じている。
再生医療(=細胞治療)は従来の治療とはまったく異なるものである。むしろ手術と同じで、最初から完成されて効果も一定なわけではなく、開始されてから、年月を経て徐々に改良され効果が大きくなる治療である。白内障手術は20年前と現在で大きく改良され、今やかなり完成された安全で効果的な治療となっている。網膜細胞移植も最初は重症の方から開始して効果もさほど大きくないであろうが、20年後には安全な一般的な治療になっていると想像する。
15年前、網膜再生治療の話しをすると「網膜再生は無理だ」という声を聞いた。ES細胞研究では「ES細胞は倫理的にも問題があり臨床では使えない」と言われ、iPS細胞研究で臨床の話をすると「iPS細胞はまだまだ危険だから治療を考えてはいけない」と言われていた。臨床研究が視野に入って来た今、5名の患者さんだけで安全性を確認する臨床研究がゴールではなく、一般治療にするための治験、産業化ということが必要であることがはっきりと見えてきた。「まだ産業化など考える時期ではない」と言われる人も多いが、今までの経験から何事も考えるのに早すぎるということはないと思っている。
20世紀は物理学が世界を変えた時代であったが、21世紀はライフサイエンスの時代と言われる。眼科医は眼科という非常に専門的な分野を熟知している貴重な人材なのである。その強みを生かした研究に若い人達も挑戦してみてほしいと願っている。
【略暦】
1986年 京都大学医学部卒業
1986年 京都大学付属病院眼科勤務
1988年 京都大学大学院医学研究科博士課程入学
1992年 京都大学医学部眼科助手
1996-97年 米国ソーク研究所研究員
2001年 京都大学附属病院探索医療センター開発部助教授
2006年 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
網膜再生医療研究チーム チームリーダー
============================
遺伝性網膜変性疾患の分子遺伝学
中沢 満 (弘前大学大学院医学研究科眼科学講座教授)
============================
【講演要約】
遺伝性網膜変性の代表は何と言っても網膜色素変性である。網膜色素変性と言えば、今も昔も「進行性、原因不明、遺伝性、やがて失明の可能性もある。」ということに尽きる。緑内障、糖尿病に次いで中途視覚障害の第3位、人口4000人に1人の有病率の疾患であるが、この病気の患者を診る時ほど眼科医としての無力感を感じることはないとも言える。緑内障や糖尿病網膜症は早期発見、早期治療によって重篤化を防ぐことができる。つまり人間の努力が報われる病気であるのに対して、網膜色素変性にはそれがない。どんなに早期発見しようとも患者の予後には影響がない、そればかりか早期に病名を告知したばかりに却って眼科医が恨まれる事も時にはある。結婚話や家族計画、就学就業にも深刻な影響をおよぼしてしまう。
このような難病の少なくとも「原因不明」という部分が解明されれば、それを手掛かりに何らかの治療法のヒントが得られるかも知れない、とは誰でも考えることである。私も1982年の秋から水野勝義教授の許可を得て、早坂征次先生の指導により酵素生化学的な研究の手ほどきを受け、さらに1985年から3年間米国のWinston Kao先生から分子生物学、とくに分子クローニングの基礎トレーニングを受けた。その後、1989年からは玉井信教授の許可の下、東北大学眼科を拠点として網膜色素変性の患者の血液バンクを構築した。しかし、この時点でも実際は暗中模索であった。
時代の流れは誠に凄まじいもので、ちょうど留学中の1987年に今で言うポリメラーゼ連鎖反応(PCR法)が発明され、ヒトの遺伝子診断が格段に簡便になった。そして1990年には早くも網膜色素変性の原因の1つがロドプシン遺伝子変異であることが明らかになった。それまで、ありとあらゆる学問領域の研究者がそれぞれの方法で懸命にその原因を探ってきて果たせなかった研究課題があっさりと解明されたのである。網膜色素変性の原因がロドプシン遺伝子変異であった事はコロンブスの卵のような出来事であったが、この発見は実は網膜色素変性の原因のほんのごく一部でしかなかった事も判明した。そして、世の中は世界中の多くの研究者による熾烈な遺伝子解析競争によって、網膜色素変性とは実に多種様々な原因遺伝子異常をもつ極めて異質性の高い疾患群であることが分かってきたのである。現在はアッシャー症候群、バーデット・ビードル症候群、セニョール・ローケン症候群やレーバー先天盲なども含めれば網膜色素変性の原因遺伝子ないし候補遺伝子は70種類を軽く超える。しかも、これらの遺伝子の中には網膜色素変性以外にも各種黄斑ジストロフィや小口病などの原因となっているものもある。臨床像と原因遺伝子の双方でのオーバーラップがある、というのがこの病気の特徴である。幸運にも私もこの遺伝子解析競争の流れの中に身を委ねる機会に恵まれた1人でもあった。
21世紀に入ると、多くの研究者の興味は網膜色素変性の治療法開発へと徐々にシフトした。遺伝子解析から分かった事、それは一方で疾患の遺伝的多様性であるとともに、もう一方で視細胞の変性の共通メカニズムであるアポトーシスである。現在世の中で進んでいる治療研究の視点は、いかにしてアポトーシスを止めるか、という点と視細胞アポトーシスが起きてしまってもいかにして代替手段を駆使するか、という2点に尽きる。前者には遺伝子治療と視細胞保護療法、そして後者には再生医療と人工網膜がある。私は弘前大学という研究の場を得て、視細胞保護療法の立場から網膜色素変性の治療法の開発という研究を進める機会に恵まれた。視細胞保護による進行遅延にも十分な意義がある。我々の研究チームのキーポイントは視細胞アポトーシスとカルシウムとの関係、そしてアポトーシスとカルパインとの関係である。これらを手掛かりに視細胞アポトーシスの抑制が実現できれば、という思いで牛歩のごとき遅々とした歩みではあるが、目標に向かって駒を進めている。講演ではこのうち、カルシウム拮抗薬ニルバジピンの動物実験での変性遅延効果の確認とそれに引き続いて行った単一施設ランダム化比較試験(Ib)の結果、カルパイン特異阻害を示すペプチド療法の実験的研究と点眼治療の可能性、そしてRPE65遺伝子異常マウスに対する9-シス-レチナールの実験的効果についてお示しした。
最後に、これまでの網膜変性外来での経験から「網膜色素変性診療の勘どころ」と称して、眼科医と患者との間で生じやすい2つのギャップ、すなわち失明という言葉の語感に関する医師と患者との間のギャップと視野異常の検査上の結果と日常生活で患者が感じている体感視野とのギャップの問題について私なりの考えを示した。
これまでの研究の歩みを振り返ってみると、自分自身の予想に反した結果ばかりに直面してきたことだと思う。しかし、そこから認識が深まり、新しい視点が生まれたとも言える。査読者とのやりとりは正にrefinementという言葉に尽きる。これらの経験は確実に臨床実地にも栄養となっている。
【略暦】
1980年 東北大学医学部卒業
1980年 東北大学眼科研修医
1982年 東北逓信病院(現:NTT東日本東北病院)眼科
1982年 東北大学眼科
1985年 米国シンシナティ大学眼科ポスドク
1989年 東北大学眼科講師
1995年 東北大学眼科助教授
1998年 弘前大学眼科教授