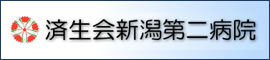報告:【目の愛護デー記念講演会 2010】
(第174回(10‐08月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
演題:「今昔白内障治療物語」
講師:藤井 青 (新潟県眼科医会会長、前新潟市民病院眼科部長)
日時:平成22年8月11日(水)16:30~18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要旨】
白内障は眼球内の水晶体が混濁する病気です。主因は加齢ですが、赤外線の被爆、オゾン層の破壊など環境破壊による過度な紫外線被爆、職業現場における紫外線やレントゲン線の過度な被爆、恒常的な高温環境などの影響も注目されています。二次的な原因はある程度予防できるとしても、主因である加齢を完全に抑えることが出来ない以上、長寿高齢化に伴って、手術適応症例は増加します。更に、運転免許証がどうしても必要な職業や生活環境の増加が手術適応を拡大しています。
一方、「白内障の手術をすると、眼鏡なしで遠くも近くもよく見えるようになる」「白内障手術は短時間で出来る簡単な手術」などという、誤った風評が眼科医療現場に様々な問題を起しています。白内障手術は本当にそんなに簡単で全く危険のない手術なのでしょうか? もう完成した手術で、今後の進歩は望めないので、少しでも見難くなったら急いで受けた方が良い手術なのでしょうか?
風評に惑わされ、誤った判断に陥る危険を回避するためには、白内障手術に対する先人達の大変な努力と苦労の跡を辿り、現在の高度な手術に至る道程を振り返ってみることも有意義ではないかと思います。昔のことは確実な文献が少なく、伝承や物語に近いところがあります。そのため、タイトルを「今昔白内障治療物語」とさせて頂きました。
白内障に対する外科的治療は、これを手術といってよいかは甚だ疑問ですが、紀元前800年頃(約3000年前)から行われていたと言われます。尤も当時は、白内障を混濁した液が瞳孔の奥にたまったものと考えられていたようで、この濁った液が流れ出る道を針で作り、眼球の中の硝子体に流して瞳孔を透明にするという方法です。
白内障が水晶体の混濁と判明したのは、ようやく1685年になってからのことです。フランスの眼科医・アントアーヌ・メートルー・ジャンが手術中、圧下させた物体(液でなく)が硝子体中でなく瞳孔から前房へ移動したことがきっかけです。いずれにしても、濁りを眼外でなく、眼球内に墜下する方法で、大変不確実で、危険なものでした。
当時のインドにおける白内障手術についてはCelsus (チェルスース)の記載があります。「患者には手術などはしない。薬を塗るだけと言い聞かせる。頭を助手がしっかり抑える。左手で上眼瞼を抑えて、下方視させる。眼球に針を刺し虹彩または瞳孔を通して水晶体の周囲へ刺入する。瞳孔がきれいになった時点で、手の指などを見せ数えさせる。24時間眼帯し、その間に、隣村へ逃げる」という大変なものでした。
日本の白内障手術はインドのベンガル地方からエジプト、更にヨーロッパ、中国を経て、10世紀頃に伝えられたとされています。疾病をテーマにした絵巻物『病草子』にも墜下法を行っている恐ろしい絵が描かれていますが、実際には、南北朝~江戸時代になって漸く医療としての形が出来てきたようです。それには、1774年『解体新書』や杉田玄白らの「眼目篇図」、1815年の杉田立卿(玄白の子)の『眼科新書』が白内障手術の進歩に大きく貢献したとされますが、江戸時代の手術記録(土生玄昌)『白内翳手術人名』によると、3年前失明したという60余歳の商人に1851年に施行した白内障手術は、手術回数7(8)回、入院期間85日とあり、確実に濁りをとるということの大変さが伺われます。
濁りを確実にとるという意味では、1864年に開発された「水晶体全摘出術」が白内障手術一つの完成といえましょう。しかし、様々な術中、術後合併症が起こり、大変だったようです。そのため、実際には、その後の約100年間は「水晶体全摘出術」でなく、「水晶体嚢外摘出術(白内障線状摘出術)」が行われました。この手術の術中合併症を少なくするには、眼球壁(角膜縁)に短時間で十分に大きな、早期に前房の消失しない綺麗な手術創をつくることが必要でしたが、このための素晴らしいナイフが考案されたからです。このナイフのデザインはコモ湖で眼科医仲間と寛いでいたグレーフェが突然思いついたもので、グレーフェ刀と命名されました。この手術刀について、「どう思いますか?」と訊ねたグレーフェに、ホルネルは「誰にもまだわからない。でも、これはシャンペンで祝うべきだ」と答えたといいます。
1922年に行われた、クロード・モネの白内障手術に係るフランスの眼科医ジェームス・G・ラヴィンの調査資料に、執刀した眼科医コーテアの記録があります。「白内障を手術するためメスを入れ、出来るだけ多くの水晶体を洗い出した。その晩、前房が改善され、大変安心した」とあり、手術は成功したのですが、縫合は全くしないか、行ったとしても一糸だけで術後10日間の絶対安静が要求されました。実際の術後安静の状態については、モネの義理の息子の記述があります。「1~2時間おきに外用薬を点眼する時以外は完全な闇の状態。枕は使用禁止。頭が動かないように両脇に砂袋が置かれた。ベッドで水平に寝かされ、手は体の脇に伸ばして身動きできない状態を保たねばならなかった。付き添いは患者が動かないように常に見守り、精神に異常を来たさないように話しかける必要があった」ということです。術後の屈折異常(強い遠視)を矯正する眼鏡も慣れるのが困難で、モネはいろいろ不満を述べています。そんなに昔ではない20世紀に入ってからの話です。
その後、水晶体全摘出術は手術器具と術式の改善により、かなり安全な手術になりました。濁りが全くなくなるため、当時の嚢外摘出術に比べれば格段に視機能の改善が高く、しばらくは水晶体全摘出術が全盛となりました。また、分厚い眼鏡レンズに対する対策としてコンタクトレンズの開発が寄与しました。
再び、水晶体全摘出術から「計画的嚢外摘出術(改善された嚢外摘出術)」へと、術式が変更され、現在は「超音波乳化吸引術」が主流です。これらの進歩は、手術器具に加え「手術機械」や「手術用顕微鏡」の開発に負うところが大きいのですが、術後視機能の飛躍的向上という点では「眼内レンズ」の開発・進歩を特筆しなければなりません。
眼内レンズは画期的な開発です。もともとの場所に代用レンズを挿入するわけですから、見え方は自然で、術後屈折異常の矯正法として最も理想的であることは議論の余地がありません。このレンズの発想は1766年に遡ります。有名なイタリア人小説家カサノバの回想録にこんな記述があります。「ヨーロッパを巡回していた眼科医Tadiniから、箱の中のレンズを見せられた。「虹彩の後ろの水晶体のところへ埋め込むつもりだ」ということです。その話をドレスデンの眼科医Cassmataに伝えた。早速Cassmataガラスレンズを試作し眼内に入れたが、重いため眼底に沈んでしまったそうです。
実際に使用できるようになったのは、20世紀も後半になってからのことです。その後も色々な問題があり、改善が試みられています。その経過を以下に列挙してみます。
1949 英国のRidley:Ridleyレンズ:水晶体に類似した形状で作成したが、重く安定性がなかった。 → そこで、光学部と支持部に分ける形状にして軽量化をはかった。
1952 前房レンズ(隅角部固定)が開発されたが、水泡性角膜症を多く発生し、眼内レンズは行ってはいけない手術とまで評価を下げた。
1967 虹彩支持レンズ(Binkhorst)の開発:水泡性角膜症が減少しIOLは有用と再評価された。白内障嚢内(全)摘出術後の虹彩支持レンズは嚢胞様黄斑浮腫起こしやすい。
→ 白内障嚢外摘出術が再評価されるようになった。
→ 従来の白内障嚢外摘出術ではなく水晶体皮質の完全除去が要求されるようになった。
Shearingはオープンループの前房レンズを後房レンズとして使用。
→ IOLによる合併症の軽減。
現在主流の手術には、単焦点後房レンズ(後房foldableレンズ)が用いられていますが、付加価値IOLとして、表面処理レンズ(異物反応抑制)、色覚を自然にするための着色(黄色)レンズ、光障害対策のUVカット、明視域の拡大のために多焦点レンズも開発されています。手術手技の進歩と手術機械の進歩、眼内レンズの進歩、術後乱視の軽減・対策、術後屈折予測値の正確な測定などの進歩、などが相呼応して、白内障手術は目覚ましい進歩発展を遂げました。
では、「白内障手術+眼内レンズ挿入術(水晶体再建術)」は本当に完成した手術で、今後の進歩は望めないのでしょうか。少しでも見難くなったら、早く手術を受けた方が良いのでしょうか?この答えはなかなか簡単ではありません。個々の患者さんによって異なる様々な要件を考慮し、総合的に検討する必要があります。
少し前のことではありますが、1993(平成5年)の吉行淳之介著『目玉』の一節をご紹介したいと思います。「ある文学賞の授賞式で出席者名簿に署名していたらいきなり大きなものが被さってきて、私の頸を両側から絞めてきた。こいつめ、こいつめ、という声が耳もとでひびいた。ぼくはこんな眼鏡をかけているのに、なにもなしで、けしからん。埴谷雄高(はにや ゆたか)氏だった。あらためて眺めると埴谷さんの眼鏡の左には度の強い凸型のレンズが入っていた」 昭和60年6月のことである。
眼内レンズが認可されたのを待って白内障手術を受けた吉行淳之介氏と、その一寸前に白内障の手術を受け、眼内レンズ挿入術を受けることが出来なかった埴谷雄高氏の対話です。なんとも悩ましい問題ですが、これからも起きてくると思われる問題です。
【略歴】
昭和40年 新潟大学医学部卒業。
昭和41年 東京大学医学部付属病院にて医療実地修練
昭和45年 新潟大学大学院医学専攻科(眼科学)終了。
昭和48年 新潟市民病院眼科科長(現眼科部長)
新潟大学講師(医学部非常勤、現在にいたる)
平成8年 潟市民病院地域医療部長(眼科部長兼任)
平成12年 新潟市民病院診療部長(眼科部長兼任)
平成16年 新潟医療技術専門学校 教授(視能訓練士科 学科長)
平成19年 新潟医療技術専門学校退職
(現在) 新潟県眼科医会会長
にいつ眼科名誉院長, ふじい眼科名誉院長
【後記】
白内障手術の歴史について紀元前800年の頃から始まり、現代の白内障手術まで、どこで手に入れられたのか、図や写真を多く挿入され、見ごたえ聞きごたえのある講演でした。眼科医である私でも知らないことが多くあり、話に引き込まれました。そして3000年に及ぶ白内障手術の歴史を学び、今なおチャレンジの中にいることを知ることが出来ました。
医療の現場では、「トライ&エラー」は許されないはずですが、医学や医療、特に手術が進歩する場面には、時に「トライ&エラー」が必要になります。第31回日本プライマリ・ケア学会学術会議の特別講演で永井友二郎氏が以下のように述べています。「われわれがよりどころとしている現代医学は、たいへん高いレベルに進歩しているといわれ、その事実もたしかにあるが、同時に、医学は完成したものでなく、開発途中にあり、どぎつい表現をすれば、医者はいつも病人に欠陥商品を売りつづけています。しかも、医者はこのことをやめるわけにゆかず、それを売り続ける義務さえあります、これが現実なのです。」
今日行った最新の白内障手術は、明日には古いものとなるというリスクをいつもはらんでいます。患者の要求が高まれば高まるほど、以前であれば術後に分厚いメガネで矯正しても視力を回復できればOKだった時代から、乱視の少ない手術、そして眼内レンズの時代に代わり、眼内レンズも小切開・非球面・着色・紫外線カット、そして多焦点と変遷してきています。
今回参加された皆様の中にも、実際に現在白内障と診断されている方、白内障の手術を勧められ迷っている方、白内障手術を施行した方などが含まれ、講演後の質疑応答も盛り上がりました。
いつ白内障手術に踏み切ればいいのか?、、、こんな一見簡単な疑問に答えるにも、実は多くのことを考慮しなければならないとうことを、患者さんに理解して頂かなければなりません。とても短い診療時間では全てをお話しできません。今後もこうした機会を通じ、多くの方々に正しい医療情報を提供していきたいと思います。
最後になりますが、どんな質問にも丁寧にお答え下さった藤井先生に、心より感謝致します。