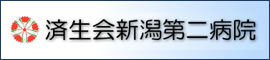演題:『「見える」「見えない」ってどんなこと?
黄斑症患者としての11年』
講師:関 恒子(患者;松本市)
日時:平成19年6月13日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要旨】
ⅰ)はじめに
病歴:1996年1月左眼の視野の中心に小さな歪みが出現し、強度近視による血管新生黄斑症と診断された。同年11月には右眼にも同様な症状が出現し、左眼は強膜短縮黄斑移動術(1997年)、左眼は360度網膜切開黄斑転移術(1999年)を施行。結局両眼合わせて入院を5回、手術を9回経験した。その後香港で光線力学的療法(PDT)を受け、更にその後ステロイド治療も受けた。現在は、左眼矯正視力は現在0.5であるが、中心部にはドーナツ型の暗点があり、その中心は歪んで見える。有効視野は狭く生活には不自由である。右眼は矯正視力0.4で、暗順応、色覚が悪く,羞明等問題はあるが、生活には役立っている。現在右眼の視野狭窄の進行が不安である。
発病からの11年を振り返ると、医療体験の中からそして家族から得てきたもの、あるいは視力障害を持ったために得た新たな感動等が思い起こされ、私には失ったものより得たものの方が多いように思われる。
ⅱ)医療体験の中から
私が気付いた最初の異変は左眼の小さな歪みだったが、黄斑変性症について何の知識もなかったため、歪みが大きくなり新聞の文字が読み難くなってから、コンタクトレンズのことでお世話になっていた開業医のN先生を訪れた。そこで視力が0.1以下に低下するかもしれないと聞いた時は信じられなかった。そして紹介された地元の大学病院で更に検査したが、確立した治療法がなく、視力低下を回復することができないと聞き、落胆した。
経過観察する中、いよいよ視力が0.3程に低下した時点で新生血管抜去の手術が提案されたが、その病院では当時まだ3例しか経験がなく、視力の改善も望めないという説明から私は手術を受けることを躊躇した。N先生は初診の日から行く度に「心配なことがあったらいつでも相談に来て下さい」と言ってくれていたので、私はN先生を訪れ、手術について相談した。N先生は私の話を聞いて、新たに大阪の大学病院で診てもらう手配を整えてくれ、私はそこで手術について相談することになった。
ところが、大阪の大学では新生血管抜去の手術ではなく、新しい手術を勧められた。視力改善が望める新しい手術と聞き、私はその手術に期待して即座に承諾して地元に帰った。早速N先生に報告すると、それはどんな手術かと尋ねられたが、その時になって私は「視力改善が望める新しい手術」としか聞いて来なかったことに気付いた。網膜の新しい手術についてはN 先生も情報がなく、とにかく情報を集めようということになり、間もなく米国の雑誌に網膜移動術の報告を見つけたのだが、その手術の結果は私の期待とはかけ離れたものだった。「受けようとしている手術がどんな手術か確かめてから受けるように」というN先生のアドバイスを受けて、私は大阪の病院に説明を求めた。
結局私は視力回復を願い、手術を受ける決心をした。私と同様に説明を受けたN先生は、私のために他の先生方の意見も集めてくれ、心配しながらも私の決心に同意してくれた。
新しい手術には危険が大きいけれど、視力改善の可能性に賭けることを私は決断した。それは何の治療も受けずにいることの方が私には遥かに辛かったからである。視機能の低下を自覚しながら、何の治療も受けられずに経過観察だけを行っていた1年間は、発症から現在までの11年間で私が最も辛かった時期であった。
手術を決意するまでの過程で、惜しみなくN先生が私を援助してくれたことから、私は精神的にも支えられ、現在に至ったことを私は大変感謝している。N先生からは「患者は、治療について説明を充分聞くこと、それを理解する努力をすること、そして最後の決定は自分自身ですべきであること」を学んだように思う。
医学にも限界がある。患者は自分の問題を全て医学に負わせるのではなく、自分の人生に係わる重大な問題の決定には、自ら参加しなくてはならないと思う。自分で決定したことには自分にも責任が生ずる。「決定に対する自己の責任」の認識が、例え結果が悪くてもそれを受け入れ、その後の人生を前向きに生きることができることに繋がり、又医療者側と患者が良好な関係を保つことにも繋がると思う。
私の手術の結果は全てが期待通りだったとは言えない。けれども、治療の存在が私に希望を与え、治療が受けられたことで当時の私が救われたことは確かであった。私は自分の決断を後悔したことはない。
ⅲ)家族と共に
両眼に発症したことが分かり、将来へ大きな不安を感じた頃のことである。「命がなくなるわけではないから、いいじゃないか」と言う夫の言葉はいかにも気軽で、「自分の眼は命より大切なものだ」と信じていた私には意外だった。しかし夫の書斎に目の病気に関する本が沢山積み重なっているのを見て夫の心の内が察せられた。
私には成人した子供、一男一女がいる。電話で私の窮状を訴えると、2人からも「目は悪くなっても死にはしないから大丈夫」と夫と同じような言葉が返ってきて驚いた。更に長男から「全盲の人でも立派に市民生活をしているよ」と言われた時、私はようやく気付いた。
それまでの私は「見えなくなるかもしれない」という不安に支配され、暗い将来ばかりに目を向けていたが、「自分はまだ見えている」という明るい側面に目を向けることができるようになったのは、その時からだった。これを契機にポジティブな考え方ができるようになり、眼が悪くなったために「できなくなったこと」を数えるより、「まだできること」を楽しみ、新たな喜びと感動を味わうことができるようになったのである。私の家族がしてくれた最大のサポートがこのように私にターニングポイントを与えてくれたことであったと思う。
私の眼の病気は、家族にとってもショッキングなことであったに違いないが、家族が動揺を見せず、常に私を支える側でいてくれたことは有り難いことだった。家族が病気を理解し、状態を敏感に察知して何気なくサポートしてくれたことにも感謝している。
ⅳ)「見たいものが見えない」「見ようとしなければ見えない」
私のように障害認定を受けるほどの障害を持たない者には、外からの援助は少ないので、患者自身が積極的に自分の問題を解決し、QOLの向上を図る必要がある。黄斑変性症になると、環境によって見え方が左右されるので、自分の見え方をよくするためにどんな環境が最適であるかを考え、可能な限り環境を整えることが大切である。
黄斑変性症患者にとって「見ようとする意識」と「見るための努力」が大切な要素となる。病気のために中心視野が見え難くなると、周辺のどうでもいい物は見えても見たい物が見え難くなる。今まで何の意識もなく見えていたのに、見ようと意識して視線をずらさないと見たい物が見えてこない。見たいという意識なしには物は見えてこないのである。そして、足りない視力を補うために面倒がらずに道具を使い、それを上手に使いこなすための工夫・努力も必要である。 こうした努力をして眼に見えてくる映像は、以前より鮮明に輝きを増し、多くの感動を与えてくれる。
ⅴ)終わりに
私の右眼は手術後近見視力がかなり改善した。しかし又悪くなるかもしれないという不安がある。今見えるうちにこの視力を最大限に活用しようと、5年前から地元の大学でドイツ文学を学んでいる。手術してくれた先生に感謝しながら、文字を読めることの喜びを噛み締めている。 これも、私が視力障害を持ったからこそ味わう喜びであり、新たに知った世界と新たな感動の一つである。
最後にドイツ文学の中からゲーテ(1749~1832)の詩劇『ファウスト』を簡単に紹介したい。
学問を究め尽くした結果知り得たことは、「何も知ることができない」ということだけだったと、失望した老博士ファウストのところに、悪魔メフィストフェレスが現れ、魂を賭けた契約をする。それは、悪魔の助けによってこの世のあらゆる歓楽を味わわせてもらう代わり、満足の余り「時よ、とまれ。お前は実に美しい!」と言ったら、死んで魂を悪魔に渡すというもであった。
早速博士は若返らせてもらい、美しい若い娘と恋をする。しかし、その恋に安住できず娘を捨て、あらゆる享楽と冒険の遍歴を重ねる。そして人のために生きたいと願うようになた時、灰色の女「憂愁」に息を吹きかけられ、失明してしまう。だが失明した博士の心の中の火は燃え上がり、輝きを増して、理想の国家建設の意欲に燃える。
メフィストは博士の墓穴を掘らせていた。目が見えない博士はその工事の音を聞いて、理想の美しい国ができ上がることを想像して思わず、「時よ、とまれ。……!」と言いつつ倒れる。しかしその魂は悪魔に渡ることなく、天国へと導かれる。
失明後の博士は、人のために生きる意欲に燃え、それまでこの世のどんな歓楽にも満足することがなかったのに、見えないために墓穴工事の音を聞いて自分の希求の完結を心の中に見て、最高の時を味わうことができたのである。
私は、「心の目」が、きっと幸せをつかんでくれることを信じている。
【略 歴】
名古屋市で生まれ、松本市で育つ。
富山大学薬学部卒業後、信州大学研修生を経て結婚。一男一女の母となる。
1996年左眼に続き右眼にも近視性の新生血管黄斑症を発症。
2003年『豊かに老いる眼』(監約:田野保雄、約:関恒子;文光堂)
松本市在住。
【後 記】
難治な疾患の治療に立ち向かった自らの経験を振り返り、医師との関係の持ち方、患者の自己責任、家族の支え、ゲーテのファウスト等々についてお話されました。静かなそして誠実な性格そのままの話し振りで、集った人々は皆、関さんの世界に引き込まれました。
以下は、関さんからお聞きし印象に残っているので紹介致します。
「『見たい物しか見えない』これが今の私の見え方を最も端的に表す言葉です。しかし、充分な視力があって、あらゆる物が見えていても、心に残る物はどれだけあるでしょうか?どんな人も見ようとする心と、心のあり方によって見えてくる物や、その姿形も違ってくると思います。人にとって大切なものは心であり、心のあり方だと思います。」