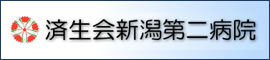報告:『済生会新潟第二病院眼科 公開講座2006』 西田親子
(第128回(06‐11)済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
「失明の体験と現在の私」
西田稔(NPO『眼炎症スタディーグループ』理事長)
「シルクロード病(ベーチェット病)からの贈り物」
西田朋美(眼科医、聖隷横浜病院)
日時:平成18年11月11日(土) 16:00~18:00
場所:済生会新潟第二病院10階会議室

「失明の体験と現在の私」
西田稔(NPO『眼炎症スタディーグループ』理事長)
【講演要旨】
ベ-チェット病発病して、来年で50年になる。当時はインフォームド・コンセントなどという概念の無かった時代だった。私は25才でベーチェット病を発病。入退院を繰り返しいろいろな治療を行ったが、28才のときには視力は右0.01、左眼は失明。大学病院に入院中の夜、見えていない左眼が急激に痛み、頭痛がした。翌日主治医の先生から、「続発性緑内障を起こしています。この目を抜きなさい」と言われた。最初は、何を言われたのか理解できなかった、、、。左眼の眼球摘出後4ヶ月して右眼に炎症が再燃。絶望のどん底に落ちて悶々とした生活を送っていた時、母が言った「目はどげんねぇー」。私「どうもだめらしい」。母「私の目を一つあげてもいい」、、、、。
しばらく沈黙の後、母はこう言った「失明は誰でも経験できるわけではない。貴重な体験と受けとめてはどうか。それを生かした仕事をして、例え小さくてもいいから社会的に貢献しなさい」。
この言葉に刺激され、その後盲学校や中途失明者更生施設の教員となり、後進の指導にあたるようになった。
現在はシルクロード沿いのベーチェット病患者とも集いを通して交流を深めている。国が違っても病気は同じ。でも国が違うと受けられる医療は異なる。貧しい国では病気の治療どころか、痛さにも対処できない。こうした思いがあり、医薬品の海外送付等の援助など、小さいながら支援を続けている。その支援組織が「NPO法人眼炎症スタディーグループ」であり現在会員数も76名となっている。活動の3本柱は、情報発信、医薬品の海外送付、研究助成である。私たち法人の活動を理解してくださる団体や個人も徐々に増え、少しずつ活動内容も整ってきているのが現状である。
参考-NPO『眼炎症スタディーグループ』
http://hw001.gate01.com/ganen/index.html
【講師略歴:西田稔氏】
西田稔(NPO『眼炎症スタディーグループ』理事長)
1932年 福岡県生まれ
1956年 大分大学経済学部卒業 同年福岡県小倉市役所(現、北九州市)就職
1957年 ベーチェット病発症 その後入退院を繰り返し失明
1961年 国立東京光明寮入寮
1963年 日本社会事業学校専修科入学
1964年 光明寮と専修科同時卒業 同年大分県立盲学校教諭
1972年 国立福岡視力障害センター教官
1984年 同センター教務課長
1992年 同センター退職
1994年から1998年まで 国立身体障害者リハセンター理療教育部講師
2000年 第1回国際シルクロード病(ベーチェット病)患者の集い
組織委員会副会長
2001年 NPO(特定非営利活動)法人眼炎症スタディーグループ理事長
その他
「お父さんの失明は私が治してあげる」主婦の友社
「寒紅」遺句集 ダブリュネット社
「小春日和」川柳、俳句、短歌集 いのちのことば社
映画「解夏」取材協力
「シルクロード病(ベーチェット病)からの贈り物」
西田朋美(眼科医、聖隷横浜病院)
【講演抄録】
ベーチェット病は、私にとって一番身近な存在だった。物心ついたときからベーチェット病で視力を奪われた父が目の前にいた。幼少時から、ベーチェット病という言葉は私の頭の中でしっかりとインプットされた。それと同時に、ベーチェット病は私にとって敵になった。この敵に立ち向かうには、医者になるしかないと思った。小学校の頃から、母は病気がちになり、時には炊事洗濯も姉妹二人の仕事になった。幸か不幸かそのまま医学部に進学した。医学部の最終学年時、たまたま友人に当時横浜市立大学に赴任されていた大野重昭教授(現、北海道大学大学院教授)がベーチェット病を専門とする眼科の教授だということを教えてもらい、大野教授の教室の大学院生になることが決まった。大野教授には、ベーチェット病の研究から米国留学、さらには第1回国際シルクロード病(ベーチェット病)患者の集いの事務局長まで大変貴重な機会を次々と与えていただいた。
現在、私は大学を離れ、聖隷横浜病院という横浜市内の病院で勤務を始めて2年目になる。新しい場所で、ロービジョン外来の充実化にコメディカルのメンバーと一緒に取り組んでいる。ロービジョン外来には、ベーチェット病のみならず、糖尿病網膜症、網膜色素変性症、加齢黄斑変性症など、さまざまな病気が原因で低視力となった患者さんが対象となる。この仕事には、幼い時から父を通じて私自身が体験してきた視覚障害者との触れ合いが大変役に立っている。また、国際患者の集いを通じて、国際的にベーチェット病の研究者や、患者組織との交流を持つことができている。
卒業試験・医師国家試験を終えたころ、出口のない苦しみの中にいた。そんな時、三浦綾子の本に出会った。何気なくみた最初のページに聖書の言葉があった『さて、イエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。「先生、この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか。本人ですか。それとも、両親ですか。」イエスはお答えになった。「本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。」』(ヨハネによる福音書第9章3節) それまでは父が病気になって目が見えなくなって悔しいと思ったり、父のことを友人に隠そうと思ったことがあったが、父は別に悪い事をしたわけではない。先祖が悪い事をしたわけでない。これもひとつの宿命、運命なんだ。そう考えると、気持ちが楽になった。
私の敵であるベーチェット病は、むしろ私に贈り物をたくさん授けてくれているのではないか?と、今では思えるようになった。
【講師略歴:西田朋美先生】
西田朋美(眼科医、聖隷横浜病院)
1966年 大分県生まれ
1991年 愛媛大学医学部卒業
1995年 横浜市立大学大学院医学研究科(眼科学)修了
1996年 米国ハーバード大学医学部スケペンス眼研究所リサーチフェロー
1999年 済生会横浜市南部病院眼科医員
2000年 第1回国際シルクロード病(ベーチェット病)患者の集い
組織委員会事務局長
2001年 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター眼科助手
2002年 横浜市立大学医学部眼科学講座助手
2004年 横須賀共済病院眼科医師
2005年 聖隷横浜病院眼科主任医長
その他
「お父さんの失明は私が治してあげる」主婦の友社
映画「解夏」、「ベルナのしっぽ」医事監修
参考-:著書
「お父さんの失明は私が治してあげる
~娘の顔も知らないお父さん、だから私は眼科医になりました」
著者:西田朋美・西田 稔・大野重昭
発行:主婦の友社
定価:本体1700円(税別)
ベーチェット病で30歳で失明された西田稔氏。父を支える母のため、父の目に再び光をと眼科医を志した娘、西田朋美氏。ご家族の絆と、ベーチェット病への思い、障害を持って生きる意味についてつづられています。また、ベーチェット病の研究をされている北海道大学大学院研究科視覚器病学分野教授の大野氏が病気の謎を追って世界中をまわられた過程から、ベーチェット病をわかりやすく解説してくれています。ベーチェット病の人もそうでない人も、生きると言う意味を考えている人に、是非読んでいただきたい一冊です。 尚、この本の売上の一部は眼疾患患者の為のNPO法人設立の為に寄付されます。
【後記】
県内外から120名を超える聴衆が集りました。西田稔氏の講演では、治療法のない場合の、医師と患者さんの対応について考えさせられました。西田氏の一言、残りました「困った時ほど、相手の事がよく見える。頼りにしていた人が案外だったり、その逆もあったり」。
講演終了後、会場から様々な質問がありました。「お母さんのことについて教えて下さい」という問いに西田朋美先生は、「失明していた父と結婚した母は、障害を持つ人を決して差別しない人でした。そしていつも偉くなってもえらぶる事のないよう、『実るほど頭を垂れる稲穂かな』が大事だよと語る人でした」と答えたのが印象的でした。
講演の後で、西田稔氏の「小春日和」を読ませて頂くと、幾つもこころに残るものがあります。「娘二人盲(めしい)しわれを導くを 何のてらいも無きが幸せ」「留学の娘の電話受くるたび 『食べているか』とまずは尋ぬる」「医師も人間 看護婦も人間 ベットのわれもまさに人間」「真中に枝豆おいて乾杯す 妻の遺影もここに加えて」「失明を幸に変えよと母は言い 臨終の日にも我に念押す」
「お父さんの失明は私が治してあげる」の中に、以下の一節があります・・・医者であり、患者の家族という私のような立場の人間を他に知りません。そうした意味では祖母が父に言って聞かせた言葉にあるように、私に与えられた貴重な体験を生かして、社会に貢献できることがまだまだあるはずです。貴重な体験を生かさなければ神様に申し訳ないという感じがします。この先どこまでできるかわかりませんが、ベーチェット病を核として、うまれたときからベーチェット病を見てきた私の貴重な体験を生かして、世の中に還元できる道を模索していきたいと思っています。父が視覚障害者だったからこそ、医師になれたのですから(西田朋美)・・・
素晴らしい親子愛を育み、それにとどまらず、世界中の患者さんに貢献している素敵な親子に巡り合えたと感動しました。西田親子の今後益々の御活躍と御発展を、期待しかつ祈念致します。
【後日、西田朋美先生からのメール】
私は、いつも思うのですが、生まれたときから目の前にいたのがすでに全盲の親だったので視力を失っていく過程を見ていません。それをみていたのが、祖母だったのだと思いますが、当人以外で一番大変だったのは、祖母だったのかなと思います。
私の記憶に残っている祖母は、ただならぬ人だったと思います。いつも明るく気丈で、かといって猛々しい所がない人でした。わが祖母ながら、とても真似できないですね。明治生まれの女性は、やはり強いのかもしれません。
【済生会新潟第二病院眼科 公開講座 2005】
演題:「ホスピスで生きる人たち」
講師:細井順 (財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院緩和ケア部長)
期日:平成17年11月26日(土) 15時~17時
場所:済生会新潟第二病院10階会議室
【講演要旨】
ホスピスとは死んでいくところと理解している人が殆どだと思うが、実際に中で働いてみるとホスピスとは生きるところだと感じる。そういう意味でタイトルは「ホスピスで生きる人たち」とした。
現代は「自分の死を創る時代」といわれている。がんが死因の第一位を占めるようになって四半世紀が過ぎ、2人に1人はがんの宣告を受け、3人に1人はがんで死ぬ時代である。私自身も昨年腎癌と診断され手術を受けた。病を知り、死を意識して生きる時間が長いのも、がんという病気の特徴の一つである。そのような時代の中で、ホスピスは「がんと診断され残り時間が半年以内と予測された人たちの、人生の残りをその人らしく悔いのないように過ごしてもらうために、多職種のスタッフがチームを組んで全人的なケアをするところ」として広く認識され、その重要性が高まってきている。自分の死を創ることの意義を考えさせられた一人の例を紹介する。
50才代男性。咳が続いた。開業医に行くと、胸のレントゲンを撮って、肺に影があるからと大学を紹介された。 大学の内科で精査すると肺癌であることが判り、外科に紹介され手術を受けた。外科で手術が終わると、放射線治療のために放射線科を紹介された。放射線治療が終わると、今度はホスピスを紹介された。ホスピスで余命一ヶ月言われた。このストーリーのどこが間違っているのだろうか?誰の責任だろうか?各担当の医師は誠実に自分の行なうことをしっかり行ない、次に担当すべき医師に託しているのだが、、、。自分の命に自分で責任を持つ、すなわち、死生観を持つことが求められている。
ホスピスとは何だろうか?ある人がこのように定義した。「患者にあと一日の命は与えないが、その一日に命を与える」。自分で経験した3名のお話を紹介する。
50歳半ばのギャンブラー(相場師)。頸部の癌患者。ある日、点滴を眺めて点滴のカロリーが43Calであることを見つけた。患者(筆談):「これで充分なのか?」 細井:「これで充分ですよ」 患者は泣いた。何とかしようと考えた。聖書の言葉に「鳥の声・野の花」という一節がある。空を飛ぶ鳥は自分で種を蒔くわけでもなく、収穫物を刈るわけでもない。それでも日々空を飛んでいる。野の花も明日は摘まれて炉に投げ込まれるかもしれない。それでもその日一日は可憐な美しさを誇って咲いている。つめり何を食べようが、飲もうか、何を着ようかと思い煩わずとも、その日その日に生きる力を神から与えられているものなのだ。それを話すと患者はまた泣いた。今度は彼の心の琴線に触れたのだった。その後意識が朦朧とするまで3週間、彼と毎日筆談した。
50歳代女性。小売店経営。大腸癌で肝転移あり。患者:「先生にとって人間とは何ですか?」 細井「人間とは、誰かにあらしめられるもの」 翌日見舞い客に患者は「ホスピスではこんなことも教えてくれるのよ。お金以外に大切なものがあることがわかった」と嬉しそうに話していたという。翌日亡くなった。
80歳目前の元女医。患者:「私は嫁にここに追いやられた」 嫁:「おばあちゃんとどう接したらいいか判らない」 元女医は昔ミッションスクールに通っていた。そこで毎日聖書を一緒に読んだ。その効果かどうか分からないが、あまり他人の悪口を言わなくなった。ある日の夜「世界の平和を祈って、私は眠ります」と言って床に就いた。翌日亡くなった。
これらは、通常の医師・患者の関係では生まれない会話である。人間同志の関係において成り立つ会話である。上記の3名とも、それまで自分を支えてきた価値観から新たな価値観を見出すことが出来た。自分の死を創った人たちだ。
私は外科医として18年間がんと闘ってきた。しかし、父が胃がんのために淀川キリスト教病院ホスピスで亡くなったことをきっかけに、外科医を辞めホスピス医となった。それ以降多くの患者さんの最期に関わることが赦された。こうしてホスピスで学んだ5つの事がある。
1)死は予期しない時にやってくる。
病気知らずに中高年となり、ある日がんを宣告され、怖れ戸惑うのが多くの現代人の姿である。何事も願うようにはならないものである。
2)病気で死ぬのではない。人間だから死ぬ。
人間の仕事は子孫を残す事であり、死は生物学的にプログラムされたことである。病気にならなくても死は訪れる。
3)死ぬことは、生きている時の最後の大仕事。
人間は生まれた時から、死に向かって歩んでいる。ある時から死に向かって歩みだしているわけではない。引越しに例えると判り易い。引越し前夜は徹夜になることもある。それくらい、死ぬ前にやっておくことは沢山ある。
4)生きれない時、死ねないときが来る。
ホスピスで痛みの治療や、心のケアを受けると、生き返るように思い、大きな希望を抱く。しかし病状はがんの進行と共に悪化する。その時に、「早く死なせて欲しい」「生きていても仕方がない」と呟くようになる。生きたいけれど生きれない、死にたいけれど死ねない。そんな時にその人がこれまで生きてきた姿が出る。人は生きてきたように死んでゆく。
5)生きているのでない、生かされているのだ。
死は平等にやってくる。頑張っている人にも、そうでない人にもやってくる。頑張っているから生きているとは思えない。何かしらの力で生かされているように思える。
医師として臨終の場面に立ち合う時、どこかに暖かみがあり、心が洗われるような時間を経験する。しかし、他方では切ない看取りの場面に遭遇することもある。ホスピスでは、人生最後の1ヶ月間を過ごして旅立って行く患者さんが多い。そのために、ホスピスの時間はその人の一生を凝縮した時間だといわれる。ホスピスでよい時間を過ごすためにはそれまでが肝心ということであろう。ホスピスができることは、患者さんの苦痛を軽減し、人生を振り返ってもらうことである。
私は外科医として18年、ホスピスで10年勤めた。外科医の経験とホスピス医のそれとを比べて、ホスピス医は外科医より患者さんを生かしていると、今思えるのである。人はホスピスで生きかえると思える。私達は「何か」を求めて、日々、あくせくと生活している。その「何か」がホスピスにはあるように思える。外科医は、例えるなら、患者さんに100kgの重しがかかっていると、切り刻んで50kgや30kgにしようとする。時には失敗して200kgにしてしまうこともある。ホスピス医は、100kgの重しを一緒に支えようとする。そんな違いを感じる。ホスピスには人間同士として向かい合う姿がある。
「患者の死」は、外科医にとっては「苦い経験」である。ホスピス医にとっては、「生きる力」になる。「いのち」は死ぬことでは終わらない。自分の死を創った人は、残された遺族、また連なるすべての人の心の中で生きている。その人たちが生きる力になる。
どうしたらそのような死を迎えることができるのか?「手放すことができる」人は、自分の死を創るように思える。何かを掴もう掴もうとする人は、何も得ることは出来ない。手のひらを天に向けて手放す人は、空から降ってくるものを得ることが出来る。外科医はある意味では、悪いところを切り取り現状を維持しようとする。現在に留まろうとする。これでは手放すことが出来ない。ホスピスでは、今の現状を引き受けて、悪いところも含めた新しい自分に気づくことが出来る。手放すことが出来るのだ。
養老孟司によると、人間の体は1年間で70%の細胞は替わってしまう。3年もすると殆んどの細胞は替わってしまう。変わること、拘らないことが自分の死を創ることにつながる。自分の死を創った人は遺された人の「いのち」を創る。これを実感出来た時に、人は安心して死ねるのであろう。その時、死は優しく我々を迎えてくれるに違いない。
【細井順氏 略歴】
1951年岩手県生まれ。
78年大阪医科大学卒業。
自治医科大学講師(消化器一般外科学)を経て、
93年4月から淀川キリスト教病院外科医長。
95年4月に、父親を胃がんのために、同病院ホスピスで看取った。その時に患者家族として経験したホスピスケアに眼からうろこが落ち、ホスピス医になることを決意
同ホスピスで、ホスピス・緩和ケアについて研修。
98年4月より、愛知国際病院で愛知県初のホスピス開設に携わる。
02年4月から、財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院緩和ケア部長として、
地域住民の生活に溶け込んだ新しいホスピスの建設を推進している。
04年10月 第27回日本外科学会(盛岡)市民講座で講演
「安心してがんの治療を受けるために~最新の治療法から終末期医療まで~」
現在、日本死の臨床研究会世話人
著書:『ターミナルケアマニュアル第3版』(最新医学社、1997年)(共著)
『私たちのホスピスをつくった 愛知国際病院の場合』(日本評論社、1998年)(共著)
『死をみとる1週間』(医学書院、2002年)(共著)
『こんなに身近なホスピス』(風媒社、2003年)
【後記】
「竹馬の友」と呼べる友人がいる。彼は私の一歳年上、2歳上の兄と私の間の学年である。当時盛岡に住んでいた私達兄弟と彼は、毎日お互いの家を行き来して遊んだ。私が幼稚園から小学1年生時代の3年間である。3人兄弟のような関係であった。
学生時代に3人で一緒に旅行した。彼の結婚披露宴に兄弟で招かれた。私の結婚式に参列してもらった。時を経て彼は外科医になり、新潟で学会があった時、一緒に飲んだ。大学の講師になりそれなりに活躍しているようであった。名古屋で眼科の学会があった時、一緒に飲んだ。その時には彼はホスピスで仕事をしていた。もとから彼はクリスチャンで、彼らしい選択と思った。その後彼は滋賀に移り、京都の学会の折に時々会った。
彼に会うといつも不思議な感覚を味わう。タイムスリップして一気に盛岡時代に戻ってしまう。互いに50歳を過ぎ、バーのカウンターで互いに「順ちゃん」「伸ちゃん」と呼ぶ。それ以外の呼び方をお互いに知らない。中年男性がそんな呼び合いをしながら、仲良さそうに会話をしているのだから、さぞや周囲の人からは変に思われたかも知れない。
そんな彼を新潟に呼んで講演会を開いた。「ホスピスに生きるひとたち」という演題で、約一時間の講演だった。最初は彼に講演など大丈夫かなと心配であったが、5分も経たないうちにそれは杞憂であることが判った。「ホスピスは、患者にあと一日の命は与えないが、その一日に命を与える」「病気で死ぬのではない、人間だから死ぬ」「死ぬことは、生きている時の最後の大仕事」『患者の死』は外科医にとっては『苦い経験』だが、ホスピス医にとっては、『生きる力』」、、、、、。
彼の講演は、間違いなく満員の聴衆を魅了した。嬉しかったが、正直チョッと不思議だった。なぜなら私にとって「順ちゃん」は、立派なホスピス医ではなく、今でも「やんちゃな遊び友達」であるからだ。
http://andonoburo.net/off/2209
【目の愛護デー記念講演会 2004】
(第103回(2004‐10月)済生会新潟第二病院眼科勉強会)
演題:『眼の話』
講師:藤井 青 (新潟医療専門学校教授;前新潟市民病院眼科部長)
期日:2004年10月13日(水) 17時~18時
場所:済生会新潟第二病院 10階 会議室
主催:済生会新潟第二病院眼科
『人類にとって眼とはなにか?』。文献に裏打ちされた豊富なデータや知識、ご自身で撮られた美しい新潟の風景写真をふんだんに使用し、集まった80名の聴衆を魅了しました。以下、講演の内容を私なりに、感想を交えてまとめてみました。
【講演要旨】
第1章 「昔の人は眼をどう考えていたか?」
豊富なスライドを用いて、で古代から人間と「眼」についての係わり合いについて解説。博識に圧倒された。
第2章 「人間の眼は精密なカメラ眼」
イカやタコの球状レンズ、サソリなどの外部レンズ、カタツムリなどの内部レンズと脊椎動物のカメラ眼を対比させ、人間の眼は精巧で、カメラに例えられることを解説。ここまではふんふんと聞く。
第3章 「あやふやな視覚」
精密であるはずの人間の眼が、実は頼りない。錯視について様々な例えで具体的に話された。同じ長さの2本の平行な直線、この両端に「><」と「<>」をつけると、途端に前者の線は後者よりも短く見える(ミューラリーの錯視)。末広がりの斜線の中に平行な直線を入れた場合、斜線間が広い方の直線が短く見える(ポンゾの錯視)。同じ長さの直線を逆Tの字に直角に描いただけで縦線が15%も長く見える(フィック図形)、、、、、、等々。
アナモルフォーシス(正面から見ると無意味な模様に見えるが、ある特定な見方をすると絵が現れてくる)は、レオナルド・ダ・ヴィンチにより最初に描かれたものとされているという。さらにメタモルフォーシス(一見普通の絵が、視点を変えてみると男性の顔が女性の裸体に変化したり、昆虫が人間に変わったりする。すなわち変身する)も紹介。日本にもアナモルフォーシス画は存在した。「鞘絵」は刀の鞘に映して見る、、、、、、。もうこの辺りからは、興味津々、メモを取る手がが止まってしまう。
第4章 「もう一つほしい第三の目」
今見ているものは真実だろうか?というタイトルで始まった。「第三の眼」などというと漫画の世界かと思いきや、実に奥の深い内容だった。流石(さすが)!「第三の眼」を持つ三眼の神としては、インド神話のシヴァ神が代表格である。ネパールのある地域では、今も眉間に第三の眼をつけた少女神「クマリ」が生き神様として崇められている。
オタマジャクシやハヤなどの魚類、カエルなどは両眼を摘出した後も光を感じている。第三の眼の知覚である。未分化の光感覚器を包括して「光受容器」と総称しているが、このうち「松果体;しょうかたい」だけを特に「第三の眼」と呼ぶ。松果体は、トカゲでは頭頂眼としてレンズや網膜が残っていて、今でも眼として認識されている。カエルではレンズが消失して、単に袋のような形になったため前頭器官と称されている。人間はじめ哺乳類では光受容体としての機能は消失し、ホルモン分泌専用器官のように見える。わずかに残されている照度計としての作用が、体内時計として働いている、、、、、、、。
最終章
哺乳類である人類では、松果体は見る器官としての「第三の眼」は失ってしまった。しかし心や精神、知恵、洞察力などとして間違いなく「第三の眼」は残っているし、必要とされている。複雑で分かりにくい現代社会の様々な現象を間違いなく見極めるために、「第三の眼」をしっかりと見開くことが、今の我々に求められている。
【藤井 青 先生 略歴】
昭和40年3月新潟大学医学部卒業。
東京大学医学部付属病院にて医療実地修練
新潟大学大学院博士課程で眼科学を専攻、大学院
新潟大学眼科教室勤務。医局長。
昭和48年9月から、新潟市民病院(眼科部長)勤務。
平成16年3月末日で定年退職。
同年4月から、新潟医療専門学校教授(視能訓練士科学科長)
また新潟県眼科医会副会長として活躍中。
【講演後】
参加者からの質問が相次ぎました。「眼内レンズ」は、何年くらいもつのか?白内障の手術は、入院ですべきか?外来手術で充分なのか?37歳男性片眼の白内障手術、手術すべきか?これからの白内障手術の将来は?白内障にならないようにする生活習慣とは?目にいい食物は?「メガネ」を掛けていると子供に怖がられるのだが、どうしたらよいか?網膜剥離の手術を受けたが再発が不安だ、、、、、、、等々。どんな質問にもひとつひとつ懇切丁寧に噛んで含めるように説明されていた藤井先生の姿を拝見し、お人柄を垣間見たような気がしました。若い眼科医に、是非学んで欲しいと思いました。
【参加者からの感想】参加された方々から感想をメールで頂きました。
・藤井先生の眼に関する博識については、「眼玉の道草」で驚かされたところですが、今回もまた、わかりやすく、さりげなく、眼の人類史における扱いや錯視という眼の機能の特徴、第3の眼などを説明していただき、普段、「見る」ことにしか関心がない私たちをハッとさせる講演でとてもよかったと思います。 また、白内障の嘘と本当の話は、57歳の私にとって、とても切実な話ですので勉強になりました。講演のあと、白内障に関する質問が相次ぎ、ひとつひとつの質問に丁寧に応えていただいたこともあって、一層、白内障の理解を深めることができました。(HY)
・今回は白内障など患者様の身近な?話題で非常にわかりやすくお話されていたのが印象的でした。又、質疑応答では普段は外来で聞きたいのに聞けない質問が出ていました。それらを丁寧に説明され、藤井先生のお人柄が垣間見えたようでした。(KI)
・眼科医の講演でアイ・トリック、第3の目の話を聞くのは、初めてでした。これら話は、日常生活から抜け出し何か忘れたことを思い出すよう感じであり興味深く聞きました。質問も興味深かったです。巷にいわれている「目によくなる食べ物」に結構興味があるものなのだなあとか、保育所の方が、「めがねをかけた人は怖がられるのか」という質問には、きっと日常の現場で子供と接するときにいろいろとご苦労があるのでは・・・と考えたりもしました。(SH)
講演と質問の時間を合わせると2時間以上に渡り『目の話』を拝聴しました。忙しい外来診療をしながらでは、とてもこのような時間をもつことが出来ません。『目』について様々なことを教えて頂きました。私の目論見どおり、藤井青先生の話に、参加者は皆、大満足でした。
【著書】
「目玉の道草」藤井青 著
出版社:文芸社
発行日:2004年2月15日
定価:1500円+税
【書評:藤井青著「目玉の道草」を読みて】岩田和雄(新潟大学名誉教授)
(新潟市医師会報2004年5月号)
最初のお話「目薬の木」を読み出したとたん、これはもう藤井青君の文章にほかならない、と思えるほどに特徴的な文体が展開する。前著「目玉の散歩」に続くエッセイ集である。藤井青君は、本年3月末をもって、定年となり新潟市民病院開設以来の眼科部長を辞することになったので、記念出版ということになろう。併せてお慶び申し上げたい。
挿入された挨拶状によると、最後の1年は多忙で、1夜がけのような文章になったと記しているが、どうして、中々の出来栄えだ。「道草」と言えば漱石となるが、それは神経衰弱の夫とヒステリーの妻と取り巻きの人々のいざこざを、いつ果てるともなく書き綴ったもの。藤井君の道草は、ほんとうの道端に生えている草を食うが如き実体験が核になっているので、とりわけ味わいも深い。
(途中略)
新潟大学眼科大学院生で、のちに浜松医大の生理学教授となった故森田之大氏の研究テーマであった「第三の眼」が、この本では、歴史的、文化的にポリフォーニックに取り上げられて面白い。目と眼の違いをとことんまで追及されているのは流石だ。
詳細は読んでいただくことにして、最後に患者さんに信頼され、愛される「目医者さん」でありたいと心から思っていると結ばれている。立派である。いつまでもこの魅力ある語り口で、あらたなエッセイを「目医者さん」の目で綴り続けていただきたい。
書評といったものは、賞賛の言葉に加えて、何か一言、評する人の見識を暗示しないと済まされないようなところがある。「目玉の道草」は完璧で、見事で、これ以上何も申すことはない。もしも、何か足りないところがあるとすれば”お色気”かな。これは余計なこと。
(2004年3月末日)