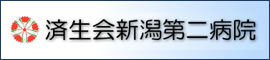第17回日本糖尿病眼学会 (2011年12月3日)
シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(東京国際フォーラム ホールB7-1)
------------------------------------
S-3 ベーチェット病による中途視覚障害の親を通して学んだこと
西田 朋美 (国立障害者リハビリテーションセンター病院 眼科)
【講演要旨】
誰に頼まれた訳でもないが、私の生い立ちが私を眼科医にしたように思う。私の父は、25歳でベーチェット病を発病し、30歳で完全失明した。父は、私たち家族の顔を全く知らないし、私も父の見えている時代を知らない。幼少時、父は盲学校で勤務しており、母が父の送り迎えをしていた。幼い私はよく同行し、盲学校の生徒さんや教職員の方々に大変可愛がってもらった。そんな頃、父は見えていないのかな?と思うことが増えてきた。父は、幼い私にも、ものの色や向きを尋ねたし、母といつも一緒に歩いているし、他の家のお父さんと違うことが多かったからだ。就学前、今でも鮮明に覚えているが、母に父はどうして見えないのか?と聞いたことがある。母は、「ベーチェット病という病気のせいよ。」と答えた。幼いながらも、「どんな病気なの?」と聞くと、母は、「原因が分からない病気よ。」と教えてくれた。その時の母との会話が大きなきっかけとなり、私は医師になろうと思うようになった。短絡的で幼い発想だが、眼科医になれば、父の病気が治せると考えていた。
その後、私は本当に医学部へ進学し、医師になった。しかも、大学卒業後、ベーチェット病を専門にしている大野重昭教授率いる横浜市立大学の大学院へ進学することができた。当時の私は、これでベーチェット病について取り組めると意気揚々としていた。しかし、その反面、疑問に思うこともあった。それは、大学時代や医師となった後の研修でも、種別を問わず、障害や福祉などに関して学ぶ機会がほぼ皆無だったことだ。父や周囲の方々の話を聞いていると、医療と福祉はとても近接しているように思えていたが、実際に医療の中に自分の身を置いてみると、意外なほどに福祉との接点がほとんど見えてこなかった。そのような疑問を感じながらも、当時の私にとっては、ベーチェット病に取り組めるということで、やっと長年の敵と向かい合えるような心境でもあった。
大学院修了後には、米国留学の機会も与えられ、研究を手がける医師として恵まれた環境にいたと思うが、やはり私にとっては、医師になった当初の疑問が逆に大きくなってきた。臨床経験を積むにつれ、「見えにくくなる」というテーマについて、患者と医師のやり取りに接する機会も増えた。ほぼ全ての患者は、見えないということは、恐ろしいことで、何もできないという、ネガティブな言葉で終始していた。それに対する医師側のコメントも「見えなくなったら、大変でエライことですからね」という程度の言葉で会話が終了しているのが大半だった。
私にとっては、何か違うと思うことが増える一方だった。身近で、幼少時から多くの視覚障害者が明るく、前向きに頑張っているのを知っている私にとっては、たとえ全盲になっても、こんなこともあんなこともできるという、前向きなコメントを患者にしてあげたいと思うようにもなってきた。つまり、私はたまたま身近に知る機会があったが、多くの患者や眼科医は、視覚障害者の日常を知る機会がないのだろうとも考えた。そして、医師こそ、障害や福祉について目を向けないと、包括的な本当の医療はできないのではないか?とも思えた。
振り返って考えてみれば、少なくとも私の時代には、各種診断書の書き方ひとつ大学時代や研修でも習ったことはないし、患者が見えにくくなったら、どういうところに行って、どのようなリハビリテーションを受ければいいのかなど、全く眼科の中でも学んだことはない。私も、父がいなければ、このような領域について、全く想像もできないし、わからないことばかりだっただろう。
「失明を 幸に変えよと 言いし母 臨終の日にも 我に念押す」
これは、父が詠んだ短歌である。父がいよいよ失明するのか!?という絶望の淵に立たされていた頃、祖母が入院中の父のところにお見舞いに来た。病状を聞いた祖母は、「失明はだれでも経験することのできるものではないよ。これを貴重な体験として、これを生かした仕事をしてはどうかね。たとえ、それが小さくても社会貢献につながれば生きがいになるのではないかね」という言葉をかけた。すぐには父も言葉を受け入れることはできなったようだが、徐々に祖母の言葉を理解することができ、それが視覚障害者として再出発を果たした父の大きな原動力になった。父は、盲学校勤務の後、自分と同様に中途視覚障害で再出発を目指す人のための施設で、定年まで長きに渡って勤めた。自分が担当する利用者の皆さんにも、折に触れて、祖母の言葉を紹介してきたようだ。今、私も縁が重なり、同系列の病院眼科で勤務をし、ロービジョンケアを必要とする患者と接している。
祖母の言葉は、そのまま私にも当てはまる。中途視覚障害の親を持つ私は、眼科医として何物にも変えがたい貴重な経験をさせてもらっていると思う。今、私は、患者がロービジョンだからと構えることなく、その方が以降の人生をどれだけ満喫できるか、患者に夢を与える眼科医としてサポートしていきたいと考えている。今は、この仕事を選ぶ礎を築いてくれた父と、これまで出会った多くの視覚障害者の方々に深く感謝している。
参考:第9回オンキヨー世界点字作文コンクール 国内部門 成人の部 入選佳作
横浜市 西田 稔 「忘れることのできない母の言葉」
http://www.jp.onkyo.com/tenji/2011/jp03.htm
【略 歴】
1991年 愛媛大学医学部 卒業
1995年 横浜市立大学大学院医学研究科 修了
1996年 ハーバード大学医学部スケペンス眼研究所 留学
2001年 横浜市立大学医学部眼科学講座 助手
2005年 聖隷横浜病院眼科 主任医長
2009年 国立障害者リハビリテーションセンター病院眼科 医長
現在に至る
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「TEAM 2011」3学会合同スリーサム
日本糖尿病眼学会シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(2011年12月3日16:30~18:00:東京国際フォーラム ホールB7-1)
オーガナイザー:
安藤 伸朗(済生会新潟第二病院)
大森 安恵(海老名総合病院・糖尿病センター
東京女子医大名誉教授、元東京女子医大糖尿病センター長)
S-1 1型糖尿病とともに歩んだ34年
南 昌江 (南昌江内科クリニック)
S-2 母を生きる 未熟児網膜症の我が子とともに
小川 弓子(福岡市立肢体不自由児施設あゆみ学園園長;小児科医)
S-3 ベーチェット病による中途視覚障害の親を通して学んだこと
西田 朋美 (国立障害者リハビリテーションセンター;眼科医)
S-4 夫と登る、高次脳機能障害というエベレスト
立神 粧子 (フェリス女学院大学音楽学部・大学院 音楽研究科)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
第17回日本糖尿病眼学会 (2011年12月3日)
シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(東京国際フォーラム ホールB7-1)
------------------------------------
S-4.「夫と登る、高次脳機能障害というエベレスト」
立神 粧子 (フェリス女学院大学・大学院 音楽芸術学科 教授)
【講演要約】
命が助かった喜びの後に訪れたものは脳損傷という難解な障害であった。2001年秋に倒れた夫の病名は解離性右椎骨動脈瘤破裂による重篤なくも膜下出血。コイル塞栓術、脳室ドレナージ術、V-Pシャント術を経て命は助かったものの、高次脳機能障害が残存した。長年ヨーロッパで世界最高峰の音楽家たちと楽器開発の仕事をしてきた夫が、自分から話すことも動くことも感じることもできず、1分前の記憶が留まらず、今いる場所の感覚がなくなり、簡単なことも混乱してできない。私たちの日常は一変した。喪失感に打ちのめされていた時、New York 大学付属Rusk 脳損傷通院プログラムを知った。
Rusk通院プログラムは、脳損傷に対する神経心理学リハビリテーションで世界一と言われる。主に前頭葉の認知機能不全に対して、対人コミュニケーションを中心とした全人的なアプローチによる機能回復訓練が行われる。この障害を、英語ではBrain Injury(脳損傷)、日本の行政用語では高次脳機能障害と呼んでいる。創設者で所長のBen-Yishay博士(2011年に退官)は、脳損傷はエベレストに匹敵する手ごわい障害と語った。2004年春から夫と私が訓練を受けた時、Ben-Yishay博士は、「私たちスタッフはエベレスト登山のためのツールや登り方を授けることができるが、登るのは君たちだ。訓練して自分の力で登りなさい。」と説明した。
当時日本でお手上げだった夫の症状は、1サイクルを経ただけでも日本の先生方が驚くほどの回復を見せた。Rusk通院プログラムの見事に構造化された訓練は神経心理ピラミッドを核として、各症状への戦略を身につけるために工夫・統合されている。神経心理ピラミッドは前頭葉機能の中でも主に認知の神経心理機能の働きを9つの階層に分けて表している。下から順番に以下のとおりである:1.訓練に参加する主体的意欲、2.神経疲労(覚醒・厳戒態勢・心的エネルギーの問題)、3.抑制困難症と無気力症(制御と発動性の問題)、4.注意と集中、5.情報処理(情報を処理するスピードと正確性の問題)、6.記憶、7.論理的思考力と遂行機能、8.受容、9.自己同一性。
ピラミッド型であることは、上位の機能はそれより下位の機能が働いていないとうまく機能しないことを示している。実際は諸機能が連動したり組み合わされて様々に複雑に絡み合うことになる。グループや個人での訓練、カウンセリングなどあらゆる角度から当事者は家族と共に症状と戦略を学ぶ。
Kurt Goldstein は、「患者が適正かつ主体的に参加して初めて、脳損傷のリハビリテーションは成功する」ため、「自分の問題をできるだけ詳細に理解させる」必要性を説いている。Goldsteinの療法哲学を受け継ぐBen-Yishay博士は次のように説明した。脳損傷を得て、「誰でもはじめは深い絶望を感じるだろう。しかしそこから自分で立ち上がってこなくてはいけない。自分の欠損に気づき、訓練の環境に順応しながら、訓練の必要性を理解する。そして欠損の補填戦略を学び、日常生活の中で様々な調整を行いながら、習慣化するまで練習する。そのあたりまで進むと、脳損傷を得た自分を受容できるようになる。」受容ができるようになったら、「脳損傷を得た自分」を新しい自分として認め、そこから再び自己を構築する必要がある。そこまで目指さないと、社会の中や家族の間において、自己の存在価値を自分で認めることは難しい。家族も同様である。脳損傷を得た患者とのかかわり方を学んで、この事実を受け入れ、家族の立場から自己を再構築することで、自分自身も幸せになるように考える必要がある。
「高次脳機能障害はエベレスト登山のように難しい」という話から始めた。Rusk 通院プログラムから伝授されたツールをまとめると次のようなことだった。
1.症状をよく知り、真に理解すること。
2.戦略の使い方を学び練習し、マスターして習慣化すること。
3.失敗から学ぶこと。
4.成功体験は、本人のみならず家族にとっても明日への活力だ。
5.感謝の言葉や気持ちを表すことによって、患者は相手への共感をもつことができるようになり、家族は苦労が報われる気持ちになる。
Ruskで夫が何かができるようになったとき、大喜びでBen-Yishay博士に報告に行くたびに博士からこう言われた。「Shoko, patience!(粧子、決して焦ってはいけない!)これは先の長い問題だ。いちいち一喜一憂せずにどっしり構えなさい。そして困難に耐える力を身につけなさい。」 夫も私もRuskでの訓練から、受動的ではない、能動的な生き方を教わったと感じている。 そしてRuskでの訓練を徹底的に学んだ私に、Ben-Yishay博士は門外不出だった資料の公開の許可を与えてくださり、その結果、2010年11月に医学書院から『前頭葉機能不全 その先の戦略』という本を出版することができた。
高次脳機能障害を持つことになった夫との生活から、症状を真に理解しなければ、相手を支援することはできないことを学んだ。また、夫を助けるばかりでなく、夫にも私を助けてもらうような関係にならなければ、これからの人生を共に幸せに過ごすことはできないだろう。真の自己同一性は、自分のためではなく、隣にいる人、それが家族であろうと社会の中の他人であろうと、自分の隣にいる人を幸せにすることではないか。現在も、夫との生活で毎日のように困難に直面する。しかし、Ruskから授かった戦略とツールによって、何とか一歩ずつ、二人でこのエベレストを前に進んでいきたいと思っている。
【略 歴】
1981年 東京芸術大学音楽学部卒業 音楽学士号取得
1984年~86年 国際ロータリー財団奨学生として米国シカゴ大学大学院に留学
1988年 シカゴ大学大学院人文学科修了 音楽学修士号取得
1991年 南カリフォルニア大学大学院演奏研究修了 音楽芸術博士号取得
1993年 フェリス女学院大学 専任講師
1998年 フェリス女学院大学 助教授
2006年 フェリス女学院大学 教授
現在に至る
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「TEAM 2011」3学会合同スリーサム
日本糖尿病眼学会シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(2011年12月3日16:30~18:00:東京国際フォーラム ホールB7-1)
オーガナイザー:
安藤 伸朗(済生会新潟第二病院)
大森 安恵(海老名総合病院・糖尿病センター
東京女子医大名誉教授、元東京女子医大糖尿病センター長)
S-1 1型糖尿病とともに歩んだ34年
南 昌江 (南昌江内科クリニック)
S-2 母を生きる 未熟児網膜症の我が子とともに
小川 弓子(福岡市立肢体不自由児施設あゆみ学園園長;小児科医)
S-3 ベーチェット病による中途視覚障害の親を通して学んだこと
西田 朋美 (国立障害者リハビリテーションセンター;眼科医)
S-4 夫と登る、高次脳機能障害というエベレスト
立神 粧子 (フェリス女学院大学音楽学部・大学院 音楽研究科)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
第17回日本糖尿病眼学会 (2011年12月3日)
シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(東京国際フォーラム ホールB7-1)
------------------------------------
S-2.「母を生きる 未熟児網膜症の我が子とともに」
小川 弓子 (福岡市立あゆみ学園 園長 小児科医)
【講演要旨】
平成18年5月に1冊の本が出版されました。「視力3cm~それでも僕は東大に~」という本です。視力および色覚に障害をもつ私の長男 明浩が成人を機に出版した本です。抜粋を紹介します。「弱視であるがゆえに、これから進んでいく道のりを見失ったり、道幅がよく見えずにはみ出てしまったりすることも多々あるでしょう。それでも、みんなのおかげで、きっと私は頑張れます。今の私を作ってくれた、すべての人たち、これまで私を育ててくれてありがとう。私を誇りに思ってくれてありがとう。私を支えてくれてありがとう。私のそばにいてくれてありがとう。私は元気です。これからも頑張って生きていきます。そのための力をくれたこと、ほんとうにありがとう」
私は書店でこの本を手に取った時、涙でほとんど読み進めることができませんでした。私はけっしていい親でも、りっぱな親でもなかった。仕事を最優先にして、早産。その後の子育てでも、障害のある子どもと向き合えず、子どもに対する期待、見栄、そして現実を受け入れる勇気、忍耐等々自分自身の気持ちと闘うのに必死だった未熟な弱い親でした。ただただ目が悪くとも「見せてあげたい」「経験させてあげたい」「いきいきと生きて欲しい」「人生の楽しみを知って欲しい」という必死の思いだけで療育を開始していきました。単眼鏡、ルーペなどの補装具訓練、そして知識を補うための膨大な本と拡大作業、ピアノ、折り紙、切り絵、字の練習。いいと思うものを息子に与えようとする私の気持ちは、もしかすると空回りもし、子どもにとって負担だったかもしれない。きっと辛いこと、悔しいこともいっぱいだったに違いない。そんな私の手探りの子育てだったのに、息子が自分を卑下せず感謝の気持ちを持って成人となったことは、有り難く、また多くの支えてくれた人たちのお陰と感謝の気持ちで一杯です。
「身体が悪くとも立派に生きている人間はおる、そのように育てればいい」といった祖父。「私が代わってでも育てちゃる」といった祖母。「障害があることと幸せ、不幸せは全く別のことです」と諭してくれたカウンセラー。「あなたの必死さが通じないはずはない」と励ましてくれた友人。「変えられるものを変えていく勇気と、変えられないものを受け入れていく冷静さと、そしてそれを見分けられる知恵を私にください」「親はこどもと代われないが最高の応援団にはなれる」「生きるとは運命を引き受けること」「笑顔があればきっと大丈夫」といった本や歌の中の言葉達。そして「明浩の人生は明浩のものだが、明浩だけのものではない、家族みんなで支えていく」といった主人。障害に遭遇したけれど、これらの多くの人の励ましや人生を生きるメッセージに私たちは出会い、力をもらいました。人は弱い、けれど支えがあれば強く大きく変わっていくこともできると、心から思います。
今、息子は1人の社会人として大都会東京で、将来の夢をかけてITベンチャー企業を起こしています。就職に際して「僕は目が悪いから、どんなに立派な会社のビルか、どれほど会社のロゴマークが社会にあふれているか見えない。僕にとって大事なのは、握手してくれる温かい手、肩をたたき一緒にやろうと言ってくれる誠実な言葉、気持ち。この価値観を作ってくれたのは生まれたときからつきあってきたこの視力だよ。」といってこの選択をしました。なまじ目が見える私は立派な物、大きな物、きれいな物に心惹かれますが、視覚障害の息子は本質をのみ見つめて生きて行こうとしているようです。そこには視覚障害があるからこその豊かな価値観があるのかもしれません。
「辛い」という言葉があります。この言葉は驚くほど「幸せ」という言葉に似ているとある本に書いてありました。もしかすると辛いことのすぐ傍に幸せはあるのかもしれません。辛いからこそほんの小さなことに喜びを感じたり、感謝の気持ちが生まれたりもするでしょう。辛いからこそ寄り添ってくれる人、励ましてくれる人、心配してくれる人の優しさが身に染みることもあるでしょう。そして、その人々の支え合い、生まれた絆こそが幸せに導くのかもしれません。
この文章を目にされた方々の中の一人でも、障害や病気など困難を抱える人の「辛い」状況にも小さな「幸せ」を感じられるように支えとなってくださることを祈りながら、筆を置きます。
【略 歴】
1983年 島根医科大学(現島根大学医学部)卒業
九州大学医学部付属病院 小児科勤務
1984年 福岡市立こども病院勤務
1985年 東国東地域広域国保総合病院 小児科勤務
1986年 福岡市立子ども病院勤務
1987年 長男(視覚障害児)出産を機に育児・療育に専念
1994年 福岡市立心身障害福祉センター 小児科に復職
2002年 福岡市立肢体不自由児通園施設あゆみ学園 園長就任
現在に至る
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「TEAM 2011」3学会合同スリーサム
日本糖尿病眼学会シンポジウム 「患者さん・家族が語る、病の重さ」
(2011年12月3日16:30~18:00:東京国際フォーラム ホールB7-1)
オーガナイザー:
安藤 伸朗(済生会新潟第二病院)
大森 安恵(海老名総合病院・糖尿病センター
東京女子医大名誉教授、元東京女子医大糖尿病センター長)
S-1 1型糖尿病とともに歩んだ34年
南 昌江 (南昌江内科クリニック)
S-2 母を生きる 未熟児網膜症の我が子とともに
小川 弓子(福岡市立肢体不自由児施設あゆみ学園園長;小児科医)
S-3 ベーチェット病による中途視覚障害の親を通して学んだこと
西田 朋美 (国立障害者リハビリテーションセンター;眼科医)
S-4 夫と登る、高次脳機能障害というエベレスト
立神 粧子 (フェリス女学院大学音楽学部・大学院 音楽研究科)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
報告3 公開講座2011 「高次脳機能と視覚の重複障害を考える~済生会新潟シンポジウム」
日時:2011年2月5日(土) 開始15時~終了18:00
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
教育講演3 座長:安藤 伸朗 (眼科医;済生会新潟第二病院)
演題:「前頭葉機能不全 その先の戦略
~Rusk脳損傷通院プログラムと神経心理ピラミッド~」
講師:立神 粧子 (フェリス女学院大学音楽学部および大学院音楽研究科教授)
【講演要旨】
2001年秋、夫が仕事中に突然解離性くも膜下出血で倒れ、後遺症として高次脳機能障害が残った。2年ほど大きな改善は見られず悶々としていたなか、2004年大学からのサバティカルの1年を利用して、New York大学リハビリテーション医学Rusk研究所の通院プログラムに参加した。Y.Ben-Yishay博士が率いるRusk研究所は脳損傷通院プログラムの世界最高峰と言われている。
Ruskの訓練は、神経心理ピラミッドを用いたホリスティックなアプローチである。Ruskでは器質性による前頭葉機能不全を前提としている。認知機能を9つの階層に分け、ピラミッドの下が症状の土台であり、その基本的な問題点が改善されていなければ、ピラミッドのそれより上の問題点の解決は効果的になされないとする考え方で、ピラミッドの下から訓練は行われる。9つの階層とその説明は下から以下のとおりである。
Ⅰ.「訓練に参加する自主的な意欲」
自分に前頭葉の機能不全があることに気づき、その問題に立ち向かうために自らの意思で参加するという強い思い。
Ⅱ.「神経疲労Neurofatigue」
「覚醒」「警戒態勢」「心的エネルギー」に関する欠損。脳損傷による脳細胞の欠損のために、日常生活のすべてが以前より困難となり、脳損傷者は常に神経が疲労しやすくなっている。
(1)「無気力症Adynamia」
心的エネルギーが過少であることによる問題。基本的に「自分から~をする」ことができない。
1:自分から何かをする発動性の欠如、
2:発想の欠如、思いの連鎖がない、
3:自発性の欠如、無表情、無感動。
(2)「抑制困難症Disinhibition」
心的エネルギーが過度であることによる欠損。自分で次の諸症状を意識し、抑制することができない。
1:衝動症、2:感情の調整不良症、3:フラストレーション耐性低下症、4:イライラ症、5:激怒症、気性爆発症、6:多動症、7:感情と認知の洪水症。
Ⅳ.「注意力と集中力Attention & Concentration」
選択的注意とその注意力を維持する集中力に関する問題。
Ⅴ.「コミュニケーション力と情報処理Communications & Information Processing」
情報のスピードについてゆくことと情報を正確に受信し、人にわかるように発信することに関する問題。
Ⅵ.「記憶Memory」
出来事を習得したり覚えておくことができなくなる記憶の問題と、自分に欠損があるということの気づきが途切れる問題。記憶断続症。
Ⅶ.
(1)「論理的思考力Reasoning」
1:言われたことや書かれたことをまとめたり、同類に分類できる力である「収束的思考力、まとめ力」の問題と、
2:異なる発想を思いついたり臨機応変に対応できる力である「拡散的思考力、多様な発想力」の問題。
(2)「遂行機能Executive Functions」
日常生活における以下の能力に関する問題。
1:ゴール設定、2:オーガナイズ(分類整理)する、3:優先順位をつける、4:計画を立てる、5:計画通りに実行する、6:自己モニターする、7:トラブルシュート(問題解決)する。
Ⅷ.「受容Acceptance」
自分に機能不全があり人生に制限がついたという事実を認識して受容できること。真の受容には下位の階層のそれぞれの症状に対する戦略を自ら使い、自己を高める努力が伴う。そういうことの必要性を真に理解すること。
Ⅸ.「自己同一性Ego-identity」
脳損傷を得ても、「自分が好きな自分」でいるために、以下の過去・現在・未来の自分を再統合し、障害を得た新しい自己を再構築すること。
1:発症前に何かを達成できた自分、
2:障害を得た自分に必要な訓練や努力に現在進行形で取り組んでいる自分、
3:機能不全による限界を認識しつつ将来こうなりたいと思う自分。
神経心理ピラミッドの働きの大まかな説明は以上である。Ruskではこれらすべての階層の問題のひとつひとつに戦略(対処法)がある。月曜日から木曜日までの朝10時から午後3時まで、対人コミュニケーションや個別の認知訓練、カウンセリングまでをも含む構造化された時間割の中でシステマティックな訓練が行われる。こうした訓練と戦略のおかげで、絶望的だった夫との生活は奇跡的に改善され、希望が持てる人生を歩みだすことができた。
【略歴】
1981年 東京芸術大学音楽学部卒業
1984年 国際ロータリー財団の奨学生として、シカゴ大学大学院に留学
1988年 シカゴ大学大学院にて音楽学で修士号取得、博士課程のコースワーク修了
1988年 南カリフォルニア大学大学院へ特待入学
1991年 南カリフォルニア大学大学院にてピアノ演奏(共演ピアノ)で音楽芸術博士号取得
1993年 帰国後、フェリス女学院大学音楽学部および大学院音楽研究科の専任講師
~現在 フェリス女学院大学音楽学部および大学院音楽研究科教授、音楽芸術博士
http://www.ferris.ac.jp/music/bio/m-04.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
1985年 シカゴ・コンチェルト・コンペティション優勝
1988~91年 コルドフスキー賞、最優秀演奏家賞受賞
1992年~現在 ベルリン・フィル、ロンドン響、バイエルン放送響、フィレンツェ歌劇場、MET歌劇場などの欧米の主要オーケストラの首席奏者や歌手たちと国内外で共演。世界各地でリサイタル多数。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
ご主人の小澤富士夫氏は、東京芸術大学のトランペット科を卒業後、プロの演奏家として活躍。その後ヤマハで新製品の研究開発業務に携わり、ヤマハ・フランクフルト・アトリエの室長として長年ヨーロッパに赴任。
帰国後の2001年、仕事中にくも膜下出血を発症、後遺症として高次脳機能障害(記憶障害、無気力症、認知の諸問題)が残る。
高次脳機能障害を治すためサバティカルを利用して、1年間ご主人とともに米国に滞在し、ニューヨーク大学Rusk研究所「脳損傷通院プログラム」に通う。ご主人は奇跡的に回復し、一人で大阪に出張できるほどになった。
*「ニューヨークRusk研究所の神経心理ピラミッド理論」
2006年 『総合リハビリテーション』(医学書院)4月、5月、10月、11月号に、「NY大学・Rusk研究所における脳損傷者通院プログラム」を治療体験記として発表。以来Rusk研究所の通院プログラム、神経心理ピラミッド、機能回復訓練などに関する講演を行う。
『前頭葉機能不全 その先の戦略:Rusk通院プログラムと神経心理ピラミッド』2010年11月医学書院より出版。
医学書院のHPに以下のように紹介されている 〜 「高次脳機能障害の機能回復訓練プログラムであるニューヨーク大学の『Rusk研究所脳損傷通院プログラム』。全人的アプローチを旨とする本プログラムは世界的に著名だが、これまで訓練の詳細は不透明なままであった。本書はプログラムを実体験し、劇的に症状が改善した脳損傷者の家族による治療体験を余すことなく紹介。脳損傷リハビリテーション医療に携わる全関係者必読の書」。
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=62912
報告2 公開講座2011 「高次脳機能と視覚の重複障害を考える~済生会新潟シンポジウム」
日時:2011年2月5日(土) 開始15時~終了18:00
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
教育講演1 座長:安藤 伸朗 (眼科医;済生会新潟第二病院)
演題:高次脳機能障害とは?
講師:仲泊 聡 (国立障害者リハビリセンター病院;眼科医)
【講演抄録】
1. 高次脳機能障害の定義
学術用語としての高次脳機能障害は、脳損傷で生じる認知・行動・情動障害全般を指し、記憶障害・社会的行動障害・遂行機能障害・注意障害という高頻度で生活へ影響が特に大きい主要症状の他に半側空間無視・失語症・失行症・失認症などがある。その特徴の一つとして病識の欠如があり、これがさらに社会生活復帰への支障を大きくしている。一方、行政用語としての高次脳機能障害は、学術用語で挙げた症状に以下の条件がつく。
1) 実際に日常生活または社会生活に制約がある
2) 脳損傷の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている
3) 先天疾患・周産期における脳損傷・発達障害・進行性疾患を原因とするものは除外
4) 身体障害として認定可能な症状を有するが主要症状を欠く者は除外(たとえば、失語症だけでは、音声・言語・咀嚼機能障害に入るため除外される)
高次脳機能障害者支援の手引き(改訂第2版)には診断基準が記されている。これは国リハのホームページから申込書ダウンロードが可能。
(http://www.rehab.go.jp/ri/brain_fukyu/kunrenprogram.html)
2. 主要症状
1) 記憶障害
・物を置いた場所を忘れたり同じことを何回も質問するなど、新しいことを学 習し、覚えることがむずかしくなる
・社会生活へ復帰する際の大きなハードルとなってしまうことが少なくない
2) 社会的行動障害
・すぐに他人を頼るような素振りをしたり子供っぽくなったりする
・我慢ができず、何でも無制限に欲しがる
・場違いの場面で怒ったり笑ったりする
・一つのものごとにこだわって、施行中の行為を容易に変えられず、いつまでも同じことを続ける
3) 遂行機能障害
・行き当たりばったりの行動をする
・指示がないと動けない
これは、目標決定、行動計画、実施という一連の作業が困難になることで、すなわち、見通しの欠如、アイデアの欠如、計画性・効率性の欠如ということができる。
4) 注意障害
・気が散りやすい
・ 一つのことに集中することが難しい
そもそも注意とは何か。これは「意識内容を鮮明にするはたらき」と説明されている。対象を選択する。選んだ対象に注意を持続する。対象以外へ注意を拡大する。対象を切り替える。複数の対象へ注意を配分するなどが注意のはたらきだ。注意障害の患者を眼科で診るときは、以下の配慮を要する。
・ほとんどの眼科検査で集中力が不足して十分な検査ができないことが多い
・視力検査は短時間で一回の検査を終え、日を替えて続きを行なうのがよい
・視野検査では眼疾患が存在しなくても全体的な沈下をきたすことがある
3. 他の高次脳機能障害の症状
1) 半側空間無視
・自分が見ている空間の片側を見落としてしまう障害
・食事で片側のものを残したり片側にあるものにぶつかったりする
・線分二等分試験や模写課題などで検査される
2) 失語症(行政用語としては高次脳機能障害に入らない)
・うまく会話することができない
・その中には、単に話すことができなくなることだけでなく、人の話が理解できない、字が読めない、書けないなどの障害も含まれている
・音声・言語・咀嚼機能障害の3級または4級に入る
3) 失行症
・動作がぎこちなく、道具がうまく使えないなど、手足は動くのに、意図した 動作や指示された動作ができない
・マッチを擦って煙草に火をつけるといったような系列を有する行為を意図的 に行うことができなくなる
4) 失認症
・視覚失認…物全般がわからない
・純粋失読…文字がわからない
・相貌失認…顔がわからない
失認症は、症状が視覚に関わることが多いため、患者自らが眼科を受診する。いわば、視覚の高次脳機能障害ということもでき、ロービジョンの範疇に入るものと思われる。しかし、その対策は一筋縄ではいかない。まして、高次脳機能障害の主要症状に視覚障害が重なったら、その対応はさらに困難であるということは明らかである。今後の検討が望まれている。
【略歴】
1989年3月 東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業
1991年4月 同大学眼科学講座助手
1995年7月 神奈川リハビリテーション病院眼科診療医員
2003年8月 東京慈恵会医科大学医学部眼科学講座講師
2004年1月 Stanford大学留学
2007年1月 東京慈恵会医科大学医学部眼科学講座准教授
2008年2月 国立身体障害者リハビリテーションセンター病院第三機能回復訓練部長
2010年4月 国立障害者リハビリテーションセンター病院第二診療部長
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
教育講演2 座長:安藤 伸朗 (眼科医;済生会新潟第二病院)
演題:「高次脳機能障害と視覚障害を重複したB氏のリハビリテーション」
講師:野崎 正和 (京都ライトハウス鳥居寮;リハビリテーション指導員)
【講演要旨】
B氏の4年間に及ぶリハビリテーション期間の内、前期(2007年8月~2008年3月の9か月)の取り組みについて報告した。
Ⅰ B氏のプロフィール
1.基本情報
40代男性、S市在住、妻・娘と同居。
2.生活歴・職業歴
教師として20数年間勤務。野球部の監督や同和教育・生徒指導の担当者として活躍していた。
3.疾病・診断名
脳梗塞(2006年10月)・全盲・軽度の高次脳機能障害。前頭葉・右側頭葉・両後頭葉・脳梁に広範囲の損傷。
4.高次脳機能障害の症状
易疲労性、集中力の低下、注意障害、記憶障害(前向健忘)、空間認知障害、遂行機能障害などがあった。
5.訓練開始時点での強み
孤立感、孤独感が強く精神的に混乱しているが、真面目で前向きな性格や、知性や判断力が健在であることを感じさせる言動も見られた。家族の支援もしっかりしていた。
Ⅱ B氏のリハビリテーションの経過
『前期の課題』
安心できる環境とゆっくりした時間の流れの中で、適度で適量な刺激を提供すること。全盲+記憶障害+空間認知障害は非常に厳しい条件だが、何とかして日常生活でのADL自立をめざす。
『前期の状況』
B氏も奥さんも、切羽詰まった状態でわらをもすがる思いで鳥居寮に来られた。本人の孤立感・孤独感は非常に強いと思われる。現状は世界も能力も縮小した状態にあるが、潜在的能力はあり、徐々に拡大していく可能性は大きい。この段階での行動上の困難は大きいが、指導員との関係が中心であり比較的環境調整が容易なため、歩行訓練士でも対応が可能だったと考えられる。
『前期の支援方針』
毎日朝夕に職員の打ち合わせをして、状況の確認と対応の統一を図る。初期には易疲労性に留意し休憩を多く取り、また注意障害を考慮して伝えることは一度にひとつかふたつに留める。感情と結びついた記憶は残りやすいため、出来れば楽しい記憶にするように務める。予定した訓練をこなすことより、B氏の語りをゆっくり聴き、受け止めることのほうが重要であるという視点をもつ。
『B氏に対して実施した、主に認知にかかわる訓練技法』
・エラーレスラーニング:迷う前にタイミングよくB氏にとって分かりやすい話し方で正しい答えを提示する。
・構造化:日課や家具の配置、移動ルートなど、さまざまなことをわかりやすくシンプルにすること。
・環境調整:施設での人間関係や家族に対する支援などもふくめて、B氏が落ち着けるような環境を作ること。
・スモールステップ&シェイピング(段階的行動形成):行動をわかりやすい小さな単位に分けて考える、それをもとに、行動を作り上げていくこと。逆シェイピングという技法もある。
・過剰学習:確実に誤りがなくなり自信がつくまで繰り返し練習すること。
・手掛かりの活用:触覚的なわかりやすい手掛かりを設置することで、手続き記憶の強化を図る。
・記憶の強制は避ける:自然な形で記憶力を使うようにしていく。
・ポジティブ・フィードバック:良いところを見つけて伝える。少しずつでも自分で出来ることが増えると、自己効力感・自己肯定感を高めることにつながる。
・散歩の活用:季節の風を感じること。感覚入力の豊かさが脳に対する良い刺激になる。
・般化:鳥居寮で出来るようになったことが、自宅でも出来ることを目指す。
Ⅲ まとめ
高次脳機能障害と視覚障害を重複した方のリハビリテーションを進めるために、また当事者や支援者を孤立させないために、多くの人たちが経験や意見を交流できるネットワーク作りが必要ではないだろうか。
【略歴】
1950年生まれ。岡山県津山市出身
立命館大学文学部卒業。
1979年京都ライトハウスに歩行訓練士として入職(日本ライトハウス養成9期)
以来歩行訓練士として31年間同じ職場に勤務。
(2011年3月末定年 その後は嘱託で仕事を続る予定)
真冬の新潟に全国11都府県から120名が集い、外の寒さを吹き飛ばすような熱気に包まれ、公開講座「高次脳機能と視覚の重複障害を考える~済生会新潟シンポジウム」を、盛況のうちに終了することが出来ました。この度、講師の先生に講演要旨をしたためて頂きましたので、ここに報告させて頂きます。
特別講演 座長:永井 博子(神経内科医;押木内科神経内科医院)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
演題:「重複障害を負った脳外科医 心のリハビリを楽しみながら生きる」
講師:佐藤 正純
(もと脳神経外科専門医;横浜市立大学付属病院
医療相談員:介護付有料老人ホーム「はなことば新横浜2号館」)
【講演要旨】
障害を負うまでの私は概ね順調な人生を送ってはいましたが、それでも秀才揃いの受験校に入学して自身の限界を見せ付けられた挫折、国立大学医学部に入学するまでの1年間の浪人生活、その在学中の父の早世など、若いうちに抗えない運命に立ち向かうための心の鍛錬をする機会があったのは幸せだったのかもしれません。
横浜市大救命救急センターに医局長として勤務して、多くの患者さんの生死に立ち会ったことから、医療の限界と医のあずかり知らぬところで神に支配されている人の生死を実感したことは、私の死生感にも大きな影響を与えました。
脳挫傷による1か月の昏睡から覚醒した時、友人はおろか家族の顔も確認できないほど視覚は失われ、太陽が東から昇ることも1年が365日であることも忘れているほど記憶は失われていたのに、ピアノの前では指が自然に動いてジャズのスタンダードナンバーが弾けたことは残存能力の証明となり、心の支えにもなりました。
視覚と高次脳機能の重複障害への適切な対応がされないまま社会復帰は不可能と判断されてリハビリセンターを退院しましたが、「これ以上、何をお望みですか?」と言われて、それを挑戦状と感じて自らのリハビリプログラムを立て始めたことが自立に繋がったようです。
私にとってのリハビリテーション、すなわち全人間的復権の根本は、働き盛りの37歳で障害を負った自分がこのままで社会復帰もできずに人生を終えたくはないという人生の哲学、そして、自身のそれまでの技術と人脈を生かすとすれば、医学知識と臨床経験を生かした教育職で社会復帰を目指すべきではないかという目的。最後にその目的を達成する手段として音声読み上げソフトと通勤のための独立歩行の技術が必要と気づいてその訓練の場所を探したことが社会復帰に繋がりました。特にパソコンに記憶された情報を読み直す反復訓練は脳の可塑性をもたらして記憶障害の克服に役立ちました。
受傷6年後に教壇に上がって最初の講義を終えた時、生きていて本当によかったと思えた自分は、そこでリハビリテーション(人間的復権)の一段階を達成して初めて障害受容もできたのだと思っています。
私が今まで精神的な支えとしてきたことは、諦めるのではなく明らめる(障害を負った今の自分の可能性を明らかにする)こと。リハビリの内容を音楽や鉄道マニアといった自分の趣味などの楽しみに結びつけ、小さな結果の達成を喜んでリハビリを楽しむように心がけたこと。過去の自分を捨てて新しい自分を構築するのではなく、過去の経験と現在の可能性を重ね着して豊かな人生(重ね着人生)を築けば良いと思ったこと。瀕死の重傷から神様の導きで生かされた自らを『Challenged』(挑戦するよう神から運命づけられた人)と信じて、自分に与えられた仕事は神様から選ばれて与えられた試練と考えて決して諦めないと誓ったこと、などです。
これからも医師は一生勉強、障害者は一生リハビリと唱えて、常に楽しみと結びつけ、達成感も確認して心のリハビリを楽しみながら、より高い復権を目指した人生を進んで行きたいと思っています。
【佐藤正純先生の紹介】
1996年2月、横浜市立大病院の脳神経外科医だった佐藤正純先生(当時;37歳)は、医者仲間と北海道へスキー旅行に行った。スノーボードで滑っていて転倒、頭部を強打し意識不明、ヘリで救急病院に運ばれた。頭部外傷事故で大手術の末、1ヶ月後に奇跡的に意識を取り戻した。しかし、待っていたのは、皮質盲(視覚障害)、記憶障害(高次脳機能障害)、歩行困難(マヒ)という三重苦であった。
趣味の音楽を手始めに懸命なリハビリを続け、6年後の2002年、三重苦を乗り越え医師免許を活かして、医療専門学校の非常勤講師として再出発した。今でもリハビリを重ねながら講師以外に、重度障害を負った障害者のリハビリ体験について語る講演活動を行い、さらには横浜伊勢佐木町のジャズハウス「first」で健常者に交じってジャムセッションのピアニストとして参加している。
「障害を負ったからといって人生観を変える必要はありません。昔の自分に新しい自分を重ね着すればいい。1粒で2度美味しい人生を送れて幸せです。」と佐藤先生は語る。
参考:http://www.yuki-enishi.com/challenger-d/challenger-d19.html
【略歴】
佐藤正純 (さとう まさずみ)
1958年 6月 神奈川県横浜市生まれ
1984年 3月 群馬大学医学部医学科卒業、
4月 横浜市立大学付属病院研修医
1986年 6月 横浜市立大学医学部脳神経外科学教室に入局
神奈川県立こども医療センター、横浜南共済病院、
神奈川県立足柄上病院の脳神経外科勤務を経て
1992年 6月 横浜市立大学救命救急センターに医局長として2年間勤務
1996年 2月 横浜市立大学医学部付属病院脳神経外科在職中にスポーツ事故で重度障害
1999年12月 横浜市立大学医学部退職
2002年 4月 湘南医療福祉専門学校東洋療法科・介護福祉科非常勤講師として社会復帰
2007年 4月 介護付有料老人ホームはなことば新横浜2号館医療相談員として復職
湘南医療福祉専門学校救急救命科 専任講師
筑波大学附属視覚特別支援学校 高等部専攻科理学療法科 非常勤講師
神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリ学科ゲスト講師
などを兼任して現在に至る。
・視覚障害をもつ医療従事者の会(ゆいまーる)副代表
http://www.yuimaal.org/
杉並区障害者福祉会館障害者バンド「ハローミュージック」バンドマスター
公開講座「高次脳機能と視覚の重複障害を考える~済生会新潟シンポジウム」
日時:2011年2月5日(土)15時~終了18:00
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
【公開講座プログラム】
14:30 開場 機器展示
15:00~特別講演
座長:永井 博子(神経内科医;押木内科神経内科医院)
演題:「重複障害を負った脳外科医 心のリハビリを楽しみながら生きる」
講師:佐藤 正純
(もと脳神経外科専門医;横浜市立大学付属病院
医療相談員:介護付有料老人ホーム「はなことば新横浜2号館」)
16:10~教育講演
座長:安藤 伸朗 (眼科医;眼科医済生会新潟第二病院)
1)演題:高次脳機能障害とは?
講師:仲泊 聡(国立障害者リハビリセンター病院;眼科医)
2)演題:「高次脳機能障害と視覚障害を重複した方へのリハビリテーション」
講師:野崎正和(京都ライトハウス鳥居寮;リハビリテーション指導員)
3)演題:「前頭葉機能不全 その先の戦略
~Rusk脳損傷通院プログラムと神経心理ピラミッド~
講師:立神粧子 (フェリス女学院大学)
17:30 討論
18:00 終了 参加者全員で会場の後片付け
報告:【目の愛護デー記念講演会 2010】
(第174回(10‐08月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
演題:「今昔白内障治療物語」
講師:藤井 青 (新潟県眼科医会会長、前新潟市民病院眼科部長)
日時:平成22年8月11日(水)16:30~18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要旨】
白内障は眼球内の水晶体が混濁する病気です。主因は加齢ですが、赤外線の被爆、オゾン層の破壊など環境破壊による過度な紫外線被爆、職業現場における紫外線やレントゲン線の過度な被爆、恒常的な高温環境などの影響も注目されています。二次的な原因はある程度予防できるとしても、主因である加齢を完全に抑えることが出来ない以上、長寿高齢化に伴って、手術適応症例は増加します。更に、運転免許証がどうしても必要な職業や生活環境の増加が手術適応を拡大しています。
一方、「白内障の手術をすると、眼鏡なしで遠くも近くもよく見えるようになる」「白内障手術は短時間で出来る簡単な手術」などという、誤った風評が眼科医療現場に様々な問題を起しています。白内障手術は本当にそんなに簡単で全く危険のない手術なのでしょうか? もう完成した手術で、今後の進歩は望めないので、少しでも見難くなったら急いで受けた方が良い手術なのでしょうか?
風評に惑わされ、誤った判断に陥る危険を回避するためには、白内障手術に対する先人達の大変な努力と苦労の跡を辿り、現在の高度な手術に至る道程を振り返ってみることも有意義ではないかと思います。昔のことは確実な文献が少なく、伝承や物語に近いところがあります。そのため、タイトルを「今昔白内障治療物語」とさせて頂きました。
白内障に対する外科的治療は、これを手術といってよいかは甚だ疑問ですが、紀元前800年頃(約3000年前)から行われていたと言われます。尤も当時は、白内障を混濁した液が瞳孔の奥にたまったものと考えられていたようで、この濁った液が流れ出る道を針で作り、眼球の中の硝子体に流して瞳孔を透明にするという方法です。
白内障が水晶体の混濁と判明したのは、ようやく1685年になってからのことです。フランスの眼科医・アントアーヌ・メートルー・ジャンが手術中、圧下させた物体(液でなく)が硝子体中でなく瞳孔から前房へ移動したことがきっかけです。いずれにしても、濁りを眼外でなく、眼球内に墜下する方法で、大変不確実で、危険なものでした。
当時のインドにおける白内障手術についてはCelsus (チェルスース)の記載があります。「患者には手術などはしない。薬を塗るだけと言い聞かせる。頭を助手がしっかり抑える。左手で上眼瞼を抑えて、下方視させる。眼球に針を刺し虹彩または瞳孔を通して水晶体の周囲へ刺入する。瞳孔がきれいになった時点で、手の指などを見せ数えさせる。24時間眼帯し、その間に、隣村へ逃げる」という大変なものでした。
日本の白内障手術はインドのベンガル地方からエジプト、更にヨーロッパ、中国を経て、10世紀頃に伝えられたとされています。疾病をテーマにした絵巻物『病草子』にも墜下法を行っている恐ろしい絵が描かれていますが、実際には、南北朝~江戸時代になって漸く医療としての形が出来てきたようです。それには、1774年『解体新書』や杉田玄白らの「眼目篇図」、1815年の杉田立卿(玄白の子)の『眼科新書』が白内障手術の進歩に大きく貢献したとされますが、江戸時代の手術記録(土生玄昌)『白内翳手術人名』によると、3年前失明したという60余歳の商人に1851年に施行した白内障手術は、手術回数7(8)回、入院期間85日とあり、確実に濁りをとるということの大変さが伺われます。
濁りを確実にとるという意味では、1864年に開発された「水晶体全摘出術」が白内障手術一つの完成といえましょう。しかし、様々な術中、術後合併症が起こり、大変だったようです。そのため、実際には、その後の約100年間は「水晶体全摘出術」でなく、「水晶体嚢外摘出術(白内障線状摘出術)」が行われました。この手術の術中合併症を少なくするには、眼球壁(角膜縁)に短時間で十分に大きな、早期に前房の消失しない綺麗な手術創をつくることが必要でしたが、このための素晴らしいナイフが考案されたからです。このナイフのデザインはコモ湖で眼科医仲間と寛いでいたグレーフェが突然思いついたもので、グレーフェ刀と命名されました。この手術刀について、「どう思いますか?」と訊ねたグレーフェに、ホルネルは「誰にもまだわからない。でも、これはシャンペンで祝うべきだ」と答えたといいます。
1922年に行われた、クロード・モネの白内障手術に係るフランスの眼科医ジェームス・G・ラヴィンの調査資料に、執刀した眼科医コーテアの記録があります。「白内障を手術するためメスを入れ、出来るだけ多くの水晶体を洗い出した。その晩、前房が改善され、大変安心した」とあり、手術は成功したのですが、縫合は全くしないか、行ったとしても一糸だけで術後10日間の絶対安静が要求されました。実際の術後安静の状態については、モネの義理の息子の記述があります。「1~2時間おきに外用薬を点眼する時以外は完全な闇の状態。枕は使用禁止。頭が動かないように両脇に砂袋が置かれた。ベッドで水平に寝かされ、手は体の脇に伸ばして身動きできない状態を保たねばならなかった。付き添いは患者が動かないように常に見守り、精神に異常を来たさないように話しかける必要があった」ということです。術後の屈折異常(強い遠視)を矯正する眼鏡も慣れるのが困難で、モネはいろいろ不満を述べています。そんなに昔ではない20世紀に入ってからの話です。
その後、水晶体全摘出術は手術器具と術式の改善により、かなり安全な手術になりました。濁りが全くなくなるため、当時の嚢外摘出術に比べれば格段に視機能の改善が高く、しばらくは水晶体全摘出術が全盛となりました。また、分厚い眼鏡レンズに対する対策としてコンタクトレンズの開発が寄与しました。
再び、水晶体全摘出術から「計画的嚢外摘出術(改善された嚢外摘出術)」へと、術式が変更され、現在は「超音波乳化吸引術」が主流です。これらの進歩は、手術器具に加え「手術機械」や「手術用顕微鏡」の開発に負うところが大きいのですが、術後視機能の飛躍的向上という点では「眼内レンズ」の開発・進歩を特筆しなければなりません。
眼内レンズは画期的な開発です。もともとの場所に代用レンズを挿入するわけですから、見え方は自然で、術後屈折異常の矯正法として最も理想的であることは議論の余地がありません。このレンズの発想は1766年に遡ります。有名なイタリア人小説家カサノバの回想録にこんな記述があります。「ヨーロッパを巡回していた眼科医Tadiniから、箱の中のレンズを見せられた。「虹彩の後ろの水晶体のところへ埋め込むつもりだ」ということです。その話をドレスデンの眼科医Cassmataに伝えた。早速Cassmataガラスレンズを試作し眼内に入れたが、重いため眼底に沈んでしまったそうです。
実際に使用できるようになったのは、20世紀も後半になってからのことです。その後も色々な問題があり、改善が試みられています。その経過を以下に列挙してみます。
1949 英国のRidley:Ridleyレンズ:水晶体に類似した形状で作成したが、重く安定性がなかった。 → そこで、光学部と支持部に分ける形状にして軽量化をはかった。
1952 前房レンズ(隅角部固定)が開発されたが、水泡性角膜症を多く発生し、眼内レンズは行ってはいけない手術とまで評価を下げた。
1967 虹彩支持レンズ(Binkhorst)の開発:水泡性角膜症が減少しIOLは有用と再評価された。白内障嚢内(全)摘出術後の虹彩支持レンズは嚢胞様黄斑浮腫起こしやすい。
→ 白内障嚢外摘出術が再評価されるようになった。
→ 従来の白内障嚢外摘出術ではなく水晶体皮質の完全除去が要求されるようになった。
Shearingはオープンループの前房レンズを後房レンズとして使用。
→ IOLによる合併症の軽減。
現在主流の手術には、単焦点後房レンズ(後房foldableレンズ)が用いられていますが、付加価値IOLとして、表面処理レンズ(異物反応抑制)、色覚を自然にするための着色(黄色)レンズ、光障害対策のUVカット、明視域の拡大のために多焦点レンズも開発されています。手術手技の進歩と手術機械の進歩、眼内レンズの進歩、術後乱視の軽減・対策、術後屈折予測値の正確な測定などの進歩、などが相呼応して、白内障手術は目覚ましい進歩発展を遂げました。
では、「白内障手術+眼内レンズ挿入術(水晶体再建術)」は本当に完成した手術で、今後の進歩は望めないのでしょうか。少しでも見難くなったら、早く手術を受けた方が良いのでしょうか?この答えはなかなか簡単ではありません。個々の患者さんによって異なる様々な要件を考慮し、総合的に検討する必要があります。
少し前のことではありますが、1993(平成5年)の吉行淳之介著『目玉』の一節をご紹介したいと思います。「ある文学賞の授賞式で出席者名簿に署名していたらいきなり大きなものが被さってきて、私の頸を両側から絞めてきた。こいつめ、こいつめ、という声が耳もとでひびいた。ぼくはこんな眼鏡をかけているのに、なにもなしで、けしからん。埴谷雄高(はにや ゆたか)氏だった。あらためて眺めると埴谷さんの眼鏡の左には度の強い凸型のレンズが入っていた」 昭和60年6月のことである。
眼内レンズが認可されたのを待って白内障手術を受けた吉行淳之介氏と、その一寸前に白内障の手術を受け、眼内レンズ挿入術を受けることが出来なかった埴谷雄高氏の対話です。なんとも悩ましい問題ですが、これからも起きてくると思われる問題です。
【略歴】
昭和40年 新潟大学医学部卒業。
昭和41年 東京大学医学部付属病院にて医療実地修練
昭和45年 新潟大学大学院医学専攻科(眼科学)終了。
昭和48年 新潟市民病院眼科科長(現眼科部長)
新潟大学講師(医学部非常勤、現在にいたる)
平成8年 潟市民病院地域医療部長(眼科部長兼任)
平成12年 新潟市民病院診療部長(眼科部長兼任)
平成16年 新潟医療技術専門学校 教授(視能訓練士科 学科長)
平成19年 新潟医療技術専門学校退職
(現在) 新潟県眼科医会会長
にいつ眼科名誉院長, ふじい眼科名誉院長
【後記】
白内障手術の歴史について紀元前800年の頃から始まり、現代の白内障手術まで、どこで手に入れられたのか、図や写真を多く挿入され、見ごたえ聞きごたえのある講演でした。眼科医である私でも知らないことが多くあり、話に引き込まれました。そして3000年に及ぶ白内障手術の歴史を学び、今なおチャレンジの中にいることを知ることが出来ました。
医療の現場では、「トライ&エラー」は許されないはずですが、医学や医療、特に手術が進歩する場面には、時に「トライ&エラー」が必要になります。第31回日本プライマリ・ケア学会学術会議の特別講演で永井友二郎氏が以下のように述べています。「われわれがよりどころとしている現代医学は、たいへん高いレベルに進歩しているといわれ、その事実もたしかにあるが、同時に、医学は完成したものでなく、開発途中にあり、どぎつい表現をすれば、医者はいつも病人に欠陥商品を売りつづけています。しかも、医者はこのことをやめるわけにゆかず、それを売り続ける義務さえあります、これが現実なのです。」
今日行った最新の白内障手術は、明日には古いものとなるというリスクをいつもはらんでいます。患者の要求が高まれば高まるほど、以前であれば術後に分厚いメガネで矯正しても視力を回復できればOKだった時代から、乱視の少ない手術、そして眼内レンズの時代に代わり、眼内レンズも小切開・非球面・着色・紫外線カット、そして多焦点と変遷してきています。
今回参加された皆様の中にも、実際に現在白内障と診断されている方、白内障の手術を勧められ迷っている方、白内障手術を施行した方などが含まれ、講演後の質疑応答も盛り上がりました。
いつ白内障手術に踏み切ればいいのか?、、、こんな一見簡単な疑問に答えるにも、実は多くのことを考慮しなければならないとうことを、患者さんに理解して頂かなければなりません。とても短い診療時間では全てをお話しできません。今後もこうした機会を通じ、多くの方々に正しい医療情報を提供していきたいと思います。
最後になりますが、どんな質問にも丁寧にお答え下さった藤井先生に、心より感謝致します。
報告:「明日の眼科を考える 新潟フォーラム2009」
日時;2009年11月21日(土)
開場:14時 14時30分~18時00分
場所;済生会新潟第二病院 10階会議室
特別講演
「網膜色素変性とiPS細胞」
高橋 政代 (神戸理研)
「人工の眼は可能か?」
仲泊 聡 (国立障害者リハビリセンター病院)
『特別講演』
「網膜色素変性とiPS細胞」
高橋 政代 (神戸理研)
理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
網膜再生医療研究チーム チームリーダー
神戸市立医療センター中央市民病院眼科 非常勤医師
先端医療センター病院眼科 客員副部長
【講演要旨】
我々はES細胞あるいはiPS細胞由来の視細胞や網膜色素上皮細胞を用いた網膜再生治療開発を目指している。すでにヒトiPS細胞から視細胞および網膜色素上皮細胞の分化誘導法を開発した。臨床応用のためには今後それぞれの細胞特有の様々な問題を解決する必要がある。
iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の移植は、すでに純化という問題をクリアし、しかも拒絶反応がないと考えられるため、現在は実際の細胞の品質管理やプロトコール作りなどの手続きに焦点が移行する。一方、視細胞移植に関しても最近ES細胞由来細胞の移植で網膜変性モデルマウスを治療できることが報告された。視細胞については、移植細胞純化のための検討や、さらに視細胞変性には移植される側の網膜の炎症反応などの環境を制御することが移植細胞の生存率を高め神経回路網を再構築するために重要である。
以上のように、網膜細胞移植は効果が確認され、現在は具体的に移植細胞の質の確保やどのような症例に応用するかという議論を始める時期にあると考える。
研究は着実に進んでいるが、それでも視細胞移植では7年後に光を見せるのが目標という状況で、一般的な治療となるまではまだ年月が必要である。再生医療の報道が与える印象と実際とのギャップが患者を苦しめることにもなっている 実際の診療では、網膜色素変性で受診した人の10%弱のみが医療を必要としていたが、ほとんどは医療ではなく情報やケアが必要な状態であった。現在実際に向き合う網膜色素変性患者にとって、何が必要かを考えると再生医療研究などによる希望もよいが、疾患の正しい知識と疾患の受容、そして道具だけでない適切なケアが最も重要であることがわかる。
【略歴】
昭和61年 京都大学医学部卒業、京都大学眼科研修医
昭和63年~平成4年 京都大学医学部大学院
平成4年~平成13年 京都大学医学部眼科助手
平成7年~平成8年 アメリカソーク研究所留学
平成13年~平成18年 京都大学病院探索医療センター助教授
平成18年~ 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
神戸市立医療センター中央市民病院眼科非常勤医師
平成20年~ 先端医療センター病院眼科客員副部長
【後記】
網膜色素変性の理解から、最先端の研究まで判り易くお話ししてくれました。細胞を移植することによって、疾患で失われた網膜機能を再生させるプロジェクト。
再生医療を成功させるためには、基礎側からのアプローチだけではなく、臨床側からのアプローチ、すなわち対象となる疾患の深い理解も重要。「医療側が与えたい情報と、患者側が欲しい情報とでは相違がある」「見えないことを母親が可哀想 と思うこと」の問題の指摘も印象に残りました。
iPS細胞を利用した網膜色素変性の治療が、近い将来確立できることを期待します。
http://www.cdb.riken.jp/jp/01_about/0105_annual02.html
*****************************
『特別講演』
演題 「人工の眼は可能か?」
講師 仲泊 聡 (国立障害者リハビリセンター病院)
【講演要旨】
私たちの脳の中には眼の網膜の各部位と対応関係のある領野が複数あり、これがいわゆる視覚野になっていることがわかってきました。その中に後頭葉の最後端のところに網膜の中心窩からの情報が届くところがあって、これを中心窩投射皮質といいます。この部分を電気で刺激すると視覚を感じることが知られていて、70年代にはドーベルがこれを利用した人工視覚装置を開発しました。しかし、ドーベルが2004年に亡くなり、その後はそのような研究は残念ながら立ち消えになっています。
その一方で、アメリカとドイツを中心に網膜を刺激するタイプの研究が発展し、日本でも阪大や東北大でこの網膜刺激型の特殊なタイプが開発されてきています。南カリフォルニア大学のヒュマイアンは、すでに60電極の網膜刺激装置を網膜色素変性症で全盲の患者の眼にいれ、その患者はコントラストの高い大きな形なら判別できるようになっています。また、チュービンゲン大学のツレンナーは16+1500電極のものを入れ、視力が0.018になったと語っています。
このように人工視覚もここへきてかなりの進歩がみられ実用可能な範囲に突入しはじているのがわかります。しかし、手術の安全性、電極の耐久性、交換可能性、解像力、広い安定した視野というユーザーサイドから見た理想的な人工視覚にはまだまだのようです。
さらに、疾患限定ではないものとなると結局はドーベルの最初の発想に帰り、脳内への直接入力が必要となります。現在、私はこれをより安全性が高く解像力がよくなるものとして脳内光刺激型の人工視覚に賛同しています。本講演の最後にそのコンセプトについて簡単に説明しました。
究極のロービジョンケアは失明の治療であると考え、これからも「あきらめない」をキーワードに仕事を続けていきたいと思います。
【略歴】
平成元年5月 東京慈恵会医科大学付属病院長 眼科研修医
平成3年4月 東京慈恵会医科大学眼科学講座助手
平成7年7月 神奈川リハビリテーション病院派遣 眼科診療医員
平成9年7月 神奈川リハビリテーション病院 眼科診療医長
平成15年4月 神奈川リハビリテーション病院 眼科診療副部長
平成15年10月 東京慈恵会医科大学眼科学講座助手 眼科診療医員
平成15年12月 東京慈恵会医科大学眼科学講座講師 眼科診療医長
平成16年1月 Stanford大学留学(visiting scholar)
平成17年4月 神奈川リハビリテーション病院 眼科診療副部長
平成19年1月 東京慈恵会医科大学眼科学講座准教授
平成20年2月 国立身体障害者リハビリテーションセンター病院
第三機能回復訓練部部長
【後記】
人工眼研究の歴史から現在の最新の情報まで、広範なお話を判り易くお話ししてくれました。
バイオハイブリッド型人工眼、光を受け取る緑藻類(りょくそうるい)の遺伝子等、わが国の研究も進んでいることが判りました。
http://www.io.mei.titech.ac.jp/research/retina/index-j.html
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=235403&lindID=4
*****************************
『シンポジウム 明日の眼科を考える』
司会: 西田 朋美 (国立障害者リハビリセンター病院)
安藤 伸朗 (済生会新潟第二病院)
シンポジスト
田中 正四 (新潟県胎内市;当事者)
木原 暁子 (マイクロソフト社;当事者)
清水 美知子 (埼玉県;歩行訓練士)
川瀬 和秀 (岐阜大学;眼科医)
コメンテーター
高橋 政代 (神戸理研)
仲泊 聡 (国立障害者リハビリセンター眼科)
シンポジスト
田中 正四
(新潟県胎内市;当事者)
私達患者が眼科を受診する時大きなアドバルーンを持って受診します。そのアドバルーンは(不安)と(希望)と言う二つのバルーンです。経験のない目の異常に、患者の心はバクバク状態で医師の前に立ちます。まさに(不安)バルーンは、パンパン状態です。一方、現代医学医療の進歩は目覚しくその情報は新聞・テレビ・ネット等により患者の耳に届きます。患者はそれらの情報に期待をふくらませるのです。しだいに見えなくなる現実に患者のあせりが加わり、なにげない医師の言葉や、治療法が示されない現実に失望を感じ、私のバルーンは大きく揺れ動き縮小拡大を繰り返すのです。
患者の最大の望みは、もう一度ものを見る事につきます。妻や成長した娘達そして、さずかった孫達の姿や顔が見たいのです。病気の将来を承知し理解しながらも(希望)バルーンの中の夢を持続したいのです。この様な眼科受診の経験から今後の医療に次の事柄を望みます。
一つには、病気の原因と現象、その対策と将来についてより明確で判りやすい説明が必要ではないでしょうか。さらには、失明につながる診断となった時には、早期の生活訓練の提案を望みます。病院・訓練機関・行政まで一環した訓練施設・内容の提案ができれば視覚障害者の自立に大きく貢献できるものと信じています。
私はこの7年間、NPO法人や、ボランティアに参加し心に残る体験をしました。すなおになる事、出来るようになった事に喜びを見い出す事。これらを体験し、同じ障害者と接する中から(なにくそ)バルーンをかかげることができました。今後は、同じ障害を持つ仲間と共に社会貢献ができればと考えています。
略歴
1952年 新潟県越路町(現長岡市)生まれ
1968年 日立製作所入所
1974年 移転により中条町(現胎内市)に転居
2002年 右目緑内障発症
2003年 慢性腎臓疾患により人工透析開始
2004年 左目多発性後極部網膜色素上皮症・網膜中心静脈閉塞症発症
2006年 ㈱中条エンジニアリング退職
現在視覚障害一級・腎機能障害一級
*************************************************************
シンポジスト
木原 暁子
(マイクロソフト社;当事者)
私は2003年まで見えていた中途視覚障碍者です。体調不良と手術がきっかけとなり全盲となりました。
目の手術は左右合わせて4回受けてきましたが、どの手術も不安と緊張が大きくありました。左目の手術直後は麻酔と緊張の影響で、飲み物を飲んでも嘔吐してしまったほどです。
視力を保持したいという希望の気持ちと、失明してしまうかもしれないという不安から直前まで悩んだ右目手術は、網膜剥離予防と白内障改善のためと聞いていましたが、改善には及ばずその後の私に大きな影響を与えました。
眼科治療は多かれ少なかれ人生を変動させるものだと思います。その眼科治療が人生に大きく影響するならば、その後人生をenjoyできるものが技術の進歩で開発されることを願っています。
また患者の失明と同時に離れてしまいがちな医師にこそ、その後も人生を歩む私たち患者には情報(訓練施設や最新治療など)というtriggerを与えてほしいと思います。
略歴
1980年11月 若年性(1型)糖尿病発症
1999年 9月 派遣会社入社
2003年 2月 右目手術にて全盲となる
5月 退院後障害手帳取得,生活訓練受講
2003 12月 左足裏大やけどにより入院(8か月間)
2005年 8月 退院後再度生活訓練受講
2006年 7月 マイクロソフト株式会社入社~現在に至る
*************************************************************
シンポジスト
清水 美知子
(埼玉県;歩行訓練士)
今回のシンポジウムでは、さまざまな事柄に触れましたが、最も伝えたかったは、「ケア」と「リハビリテーション」は違うということです.
昨今の「ロービジョン」ヘの関心の拡大とともに、「ロービジョンケア」を実施する眼科医療機関が増えています。そのような医療機関の中には、屈折異常、視力、視野などの視覚機能の評価とそれに基づいた眼鏡類の処方に加えて、書字読字、生活動作、安全な歩行などの訓練やカウンセリングなどを行うところもあります.
いうまでもなく「訓練」や「カウンセリング」は「ケア」ではありません。そこで行われているのは「ロービジョンリハビリテーション」です。ケアの主体はケアの提供者です.リハビリテーションの主体は障害のある人自身です.
「ロービジョンケア」を「ロービジョンリハビリテーション」と同義に使用することで、患者あるいは障害の残った人の主体性、その方々の生活、心理的な問題などリハビリテーションの重要な中味がなおざりにされるのではないかという危惧を持ちます.
「ロービジョンリハビリテーション」は「ロービジョンケア」を内包しますが、その逆ではないと考えます.
略歴
歩行訓練士として、
1979年~2002年 視覚障害者更生訓練施設に勤務、
その後在宅の視覚障害者の訪問訓練事業に関わる。
1988年~新潟市社会事業協会「信楽園病院」にて、
視覚障害リハビリテーション外来担当。
2003年~「耳原老松診療所」視覚障害外来担当。
http://www.ne.jp/asahi/michiko/visionrehab/profile.htm
*************************************************************
シンポジスト
川瀬 和秀
(岐阜大学眼科)
演者は眼科医となり20年が経過した。この20年間で白内障の手術の進歩は目覚ましいものがある。技術的な進歩により生活可能な視機能維持や視機能の獲得が可能となる治療が増えたことは嬉しい限りである。しかし、これらの技術をもってしても生活に不自由を感じている患者の数はむしろ増えている。最近のロービジョンケアのシンポジウムやセミナーの開催は、眼科医が、視機能障害の進行が止まった医学的な治癒だけで治療が終わらないことの大切さにやっと気付き始めた証拠である。この件に関して、今後のロービジョンケア教育やロービジョン学会の在り方が問われているのは確かである。
さらに次の20年で、眼科医療がどのように進歩するのか楽しみである。高橋先生や仲泊先生のお話のように網膜移植や人工眼の開発も急ピッチで進められている。講演では、明後日の眼科診療として、私の専門の緑内障における、将来的に導入が期待される診断や治療法、基礎研究について紹介し、今日の眼科診療として、現在の眼科診療を見直し、明日の眼科診療として現在の治療では及ばない部分のロービジョンケアを中心としたお話をした。
最後に現在の技術で作成可能な、光学的な技術を使用した補助眼鏡による歩行支援システムの開発を紹介した。
略歴
1988年 順天堂大学医学部卒業
1988年 岐阜大学医学部眼科学入局
1993年 ミシガン大学研究員
1997年 文部省内地研究員(山口大学眼科)
1999年 アイオワ大学眼科研究員
2001年 岐阜大学医学部眼科講師
2002年 岐阜大学医学部眼科助教授
2005年 大垣市民病院眼科医長
2007年 岐阜大学医学部眼科准教授 現在に至る
【シンポジウム後記】
田中正四さん~「希望」「不安」「なにくそ」アドバルーン、とてもインパクトがありました。心に響きました。
木原暁子さん~糖尿病網膜症で失明してから再就職に至るまで、出会った方々に感謝と語りました。感動。
清水美知子さん~ケアとリハビリは違うことを指摘してくれました。「当事者主権」「エンパワメント」「インフォームド・デシジョン」「リハビリはマインドリセット」、多くのことを、考えさせられる講演でした。
川瀬和秀先生~患者の訴えを聞くことが重要(患者さんがどう見えているのか、医者は知らない、聞いていない)。緑内障の治療は、眼圧や視野だけではない。視野から不自由さを推測することが大事。最新の緑内障診療の情報を交えたお話でした。
田中さん・木原さんのお話から、医者が患者に説明することの大事さ、改めて感じました。打ち合わせはしていませんでしたが、講演やシンポジストに共通していたことは、「諦めない」ということだったようです。患者も、家族も、医者も諦めない。諦めないことは実は苦しいことですが、進歩はこうした中から生まれてくると信じます。
同じテーマを、全国各地から集まった、いろいろな職種の方々と、同じ会場で一緒に、語り合うことが出来たことが最大の収穫でした。
【【フォーラム総括】】
人工眼・再生医療という最先端の眼科医療の講演と、患者さんの生の声を交えたシンポジウムを通して、「明日の眼科の、夢と現実を考える」という、チョッと欲張りな企画でした。
眼科医・医療関係者と患者さんと家族、および教育・福祉関係者を対象に、遠くは島根県・和歌山県・兵庫県・京都府、近くは福島県・山形県など全国から98名+盲導犬4頭(新潟県外23名、新潟県内23名、新潟市内52名;事前登録)。関係者、当日参加を加えると110名を超える人数になりました。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
「明日の眼科を考える 新潟フォーラム2009」
日時;平成21年11月21日(土)
開始14時30分~終了18時30分
場所;済生会新潟第二病院 10階会議室
特別講演
「人工の眼は可能か?」
座長: 鶴岡 三恵子 (西葛西・井上眼科)
講師: 仲泊 聡 (国立障害者リハビリセンター病院)
「網膜色素変性とiPS細胞」
座長: 安藤 伸朗 (済生会新潟第二病院)
講師: 高橋 政代 (神戸理研)
シンポジウム 「明日の眼科を考える」
司会: 西田 朋美 (国立障害者リハビリセンター病院)
安藤 伸朗 (済生会新潟第二病院)
シンポジスト
田中 正四 (新潟県胎内市;当事者)
木原 暁子 (マイクロソフト社;当事者)
清水 美知子 (埼玉県;歩行訓練士)
川瀬 和秀 (岐阜大学;眼科医)
コメンテーター
高橋 政代 (神戸理研)
仲泊 聡 (国立障害者リハビリセンター眼科)
主催 「明日の眼科を考える 新潟フォーラム」
世話人
安藤 伸朗 (世話人代表;済生会新潟第二病院)
川瀬 和秀 (岐阜大学)
白木 邦彦 (大阪市立大学)
鶴岡 三恵子 (西葛西・井上眼科)
仲泊 聡 (国立障害者リハビリセンター病院)
西田 朋美 (国立障害者リハビリセンター病院)
報告:済生会新潟第二病院眼科 公開講座2008『細井順 講演会』
(第144回(08‐2月)済生会新潟第二病院眼科勉強会)
演題:「豊かな生き方、納得した終わり方」
講師:細井順(財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院ホスピス長)
期日:平成20年2月23日(土) 午後4時~5時半
場所:済生会新潟第二病院 10階会議室
【講演要旨】
4年前の2月、スキーから帰ってきて血尿がでた。疲れたせいかなと軽く考えていたが、その後も一週間に一度くらいの割で血尿は続いた。痛みのない血尿は、外科医として常識的には癌を考える。しかも、すでに血尿が出ているということから早期の癌ではないと考えた。一方、ホスピス医としての経験から、手術や化学療法をめいっぱいにやった患者さんより、治療らしい治療をしないでがんと共存して過ごしてきた人の方が楽に死ねる。このような二つの経験から、私は慌てないで様子をみようと考えた。
3月も後半になり(血尿が出てから1ヶ月半経過)、排尿の度毎に汚く濃い色の血尿がでるようになった。満足に排尿することができず、これでは仕事にならない状態となった。仕方なくCT検査を受けた。その結果、右腎臓に直径8cm大の腫瘍が写っていた。最初に思ったことは、手術をしたら簡単に取れそうだということだった。がんではないかもしれないと直感的に思ったが、泌尿器科医の友人に相談してこれはがんだと納得した。患者さんのフィルムならがんと診断したはずなのに、自分のことになると悪いことは否認することに気づき、これが、がん患者の気持だと理解できた。
家族にがんが見つかり、手術を受けることを打ち明けた時、当時高校3年の息子は、「ワァー、でかいな。素人でも判るわ」。妻は「お葬式はどうする?」という反応であり、私としては楽になった。ある意味、スーッとした。
これまで、がんは患者さんの問題であったが自分の問題となって気づいたことがあった。ホスピスに入れるのでホッとした(癌でなければホスピスには入れない)。また本(今度は闘病記)が書ける。やっぱり家族の支えが一番。そして手術がこんなにも大変だという経験を出来たこと。医療者の一言の有難さ、怖さを経験できたこと。特に「がん」があってもなくても同じことという気持になれたことが大きかった。
手術前に「患者の気持ち」という一文をしたため、主治医に渡すことにした。何故なら命を左右するような手術にはしたくなかった。外科医はとかく無理をしたがる。ついついやりすぎてしまうことがある。私は今やっている仕事を続けたい。手術して仕事が出来る状態(血尿を止める)にして欲しいことを主治医に告げた。こんなことをして嫌われたらとも思い、多少の勇気は必要だったが、、、。通常取り交わしている手術の同意書は、主治医からの一方的な押し付けであることが多い。自分の存在を大切にして、こういう手術を受けたいと患者サイドから申し出することは大事なことだと思っていた。
ホスピスの仕事を一人の患者さんの事例を紹介して、お話しする。76歳男性。前立腺癌、腰椎に転移があり腰痛があった。初診時は、苦痛に顔をしかめ、「ワニに食いつかれて、振り回されているように痛む」と訴えた。鎮痛剤を処方した。翌日、回診時「戒名」についてお話を伺った。(普通ならまだそんな話は早いと言うところかもしれない)私は「ほう、私にも教えてくれますか?、なるほどいい戒名ですね」。翌々日、痛みについてお尋ねすると、「すっかりよくなりました。この病院に来てキリストに出会ったようです」。この患者さんからホスピスの治療とはどういうものか教わった。がん患者の痛みは、身体的苦痛のみでなく、社会的苦痛(仕事や家庭)、精神的苦痛(不安や苛立ち)のみでなく、スピリチュアルペイン(人生の意味や死の恐怖等々)も 関係する。がん患者の痛みには鎮痛剤ばかりではなく、傾聴も重要な治療手段である。このおじいさんはホスピスで「キリストに出会う」という象徴的な言葉で生きかえったことを表現した。
ホスピスで生きかえることができる理由を「ホスピスの秘密」と名付けて紹介したい。
1)『You are OK.』 これまで患者さんが経験してきた治療や生き方を受け止めることである。一般的には病院というのは悪いところを見つけるために行くところである。ホスピスではそうではなく、 You are OK (あなたは、それで大丈夫)と言うことも 必要である。今ここで出会えたのも、あなたがこれまで頑張ってきたから、、、。
2)外科的に治すという事は、癌を小さくすることであるが、ホスピスでは一緒に患者さんの重荷を担いで上げることである。患者さんとの一体感。自分のパフォーマンスをするのではなくて、自分を殺して患者を浮かばせる。生きているということは、誰かに支えられているということを実感する。
3)『お互いさま』のこころ。今日という時間を共有している。死にゆくという点では、患者さんも医療者もない。時期が少しずれているだけである。そう思うとケアをすることは、結局将来の自分のためだと思われてくる。
4)『死を創る』。その人が亡くなると、私の中にその人のいのちが受け継がれている。そういう意味では、ホスピスはいのちのたすきリレーの場所でもある。
死にゆく人を支えるには、誠実・感性・忍耐・謙遜・祈りが必要。「今日はご飯が食べられません」という患者に、「おかゆにしましょう」では感性がない。その言葉の奥に秘められた患者さんの気持を聴き取ることが大切である。食べられないほど弱ってしまったという不安や孤独な思いを聴き取ることが必要である。まずはよく患者の悩みを聴くことである。
2007年の世相を表す言葉として「偽」が選ばれた。そんな世相の中でホスピスはオアシスの役割を担っている。ホスピスを動かしている力は先程の言葉(誠実・感性・忍耐・謙遜・祈り)である。この世の名声、金銭、栄誉で動いているのではない。死を前にしたとき、この世の価値観では戦えない。オアシスだからこそ、先程紹介した患者さんのように生きかえる。
ホスピスは死にゆくところと理解している人たちが多いと思うが、死にゆくことは、本人にも、家族にもケアにあたるスタッフにも決して容易いことではない。ホスピスの役割は、最期まで「よい生」を続けられる環境を整えることである。その中で患者さん・家族が主役となって「よい生」が叶えられて「よい死」が創られると感じる。
「豊かな生き方、納得した終わり方」を考えた時に浮かぶキーワードがある。『症状のコントロール』、『人生の満足感』、『死生観の確立』、『家族の支え』の4つである。このうち、ホスピスでできることは、最初に挙げた症状のコントロールだけである。ホスピスまでの人生が、ホスピスでの過ごし方を決めている。近頃の問題として、家族関係の希薄さがホスピスケアにも影響を及ぼしている。最後に大阿闍梨(だいあじゃり)の言葉を紹介しよう。「仏さまは、ぼくの人生を見通しているのかもしれないね」という一節を見つけた。修行の極みに達した生き仏と言われる人物の一言である。何ともホッとして、気持が落ち着く言葉だろう。我々を包んで、運んでいる大きな翼があることを覚えたい。
【質疑応答】
質問:死にたくない、悔しい、苦しいと思う死は、「望ましくない死」なのだろうか? 「望ましくない死」を避けがたく迎える方、その家族にも満足感、敬意を抱いて頂きたいと思うし、現に何とか抱いて頂いているとも思うが・・・。
—————————————–
答え:本人にとって納得できる死を迎えられるような環境を整えることしかホスピスではできません。本人が納得できなければ、その納得できないことに付き合うのです。決して納得できるように説得するわけではありません。人は生きてきたように死ぬと言いますから、普段の生き方がポイントでしょう。ホスピスでは、9回裏ツーアウト満塁での逆転サヨナラ満塁ホームランをねらっているわけではないのです。
質問:がんになって、突然、生の意味が語られることになる違和感は? 終末期以前で、病前期で、どうやって「豊かな生き方」を得ていくべきか?
——————————————
答え:「豊かな生き方、納得した終わり方」を考えた時、4つのポイント『症状のコントロール』、『人生の満足感』、『死生観の確立』、『家族の支え』があります。そのうち、ホスピスでできることは『症状のコントロール』(痛みからの解放)だけで、他の3点はホスピスまでに考えるテーマです。普段から終わりを意識した生き方を続けないとホスピスだけでは手遅れという場合も多々あります。昔からメメント・モリ(死を想え)という言葉があります。50才になったら人生の棚卸しをすることが薦められます。不用になったものを捨て、これから必要なものだけを残すことです。
ホスピスは not doing, but being と言われる世界ですから、ホスピスに入りさえすれば「よい死」が待っていると短絡的に考えていると、失望します。そもそも死にゆくことは自分の問題で、医療の問題ではないからです。
質問:「豊かな生き方、納得した終わり方」には多くの手助け、コストが必須ではないのか?
——————————————
答え:日本ホスピス緩和ケア協会の資料から、豊かな経営をしているホスピスはありません。赤字を出さないように四苦八苦しているのが現状です。しかし、ホスピスの数は増加傾向にあり、経営的理由で閉鎖するところは数カ所だったでしょうか。
ホスピスを動かす力は、誠実、謙遜、感謝、信頼、祈りなどですから、常識的な経営感覚では説明できない何かがあるのでしょう。私どものホスピスでも決して安泰ではありませんし、ホスピス賛助会を設けて寄付を募っています。ボランティアの働きももちろん大切です。これは誤解しないでください。ホスピスの労働力としてボランティアを使っているという意味ではありません。ボランティアとして活動する方にとってプラスになることが、ホスピスにとってプラスになるのですから。
質問:細井先生のホスピスはボランティアを入れていますか? もし入っていたらどんなボランティアですか?
——————————————
答え:ボランティアの方が活躍しています。しかし、まだ少ない人数なので、ティーサービスを担当してもらってます。また、季節の行事の準備(この季節なら雛人形の飾り付けや後かたづけ)などです。今後、人数も増えて、もっともっと充実した活動を行っていただきたいと願っています。ボランティアはホスピスに潤いを与えてくれます。
質問:ホスピスは見学できるのでしょうか?
—————————————–
答え:見学はできます。しかし、見学者のためのプログラムを作っているわけではありません。建物の見学が中心です。地域に開かれたホスピスのためには、これも今後の課題の一つです。
質問:ホスピスでの一日の流れなど詳しい生活が知りたい。
—————————————–
答え:ホスピスは痛みなどを少なくして、患者さんと家族に悔いのない1日を過ごして貰うための環境を整えることが役割です。家族にも参加してもらい、家庭での1日をホスピスで実現して貰います。従って所謂介護施設のように食事の時間、お風呂の時間、レクレーションの時間などのプログラムが用意されているわけではありません。
【細井順氏 略歴】
1951年 岩手県生まれ。
78年 大阪医科大学卒業。
自治医科大学講師(消化器一般外科学)を経て、
93年4月 淀川キリスト教病院外科医長。
95年4月 父を胃がんのために、同院ホスピスで看取る。
患者家族として経験したホスピスケアに眼からうろこが落ち、ホスピス医になることを決意。
同院ホスピスで、ホスピス・緩和ケアについて研修。
98年4月 愛知国際病院でホスピス開設(愛知県初)に携わる。
2002年4月 財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院緩和ケア部長。
04年4月 腎臓がんで右腎摘出術を受ける。
06年10月 自らの闘病経験をふまえ患者目線の院内独立型ホスピスが完成。
現在ホスピス長として患者の死に寄り添いながら、ホスピスケアの普及と充実のための啓発活動にも取り組んでいる。
現在、日本死の臨床研究会世話人
著書:『ターミナルケアマニュアル第3版』(最新医学社、共著1997年)
『私たちのホスピスをつくった 愛知国際病院の場合』(日本評論社、共著1998年)
『死をみとる1週間』(医学書院、共著2002年)
『こんなに身近なホスピス』(風媒社、2003年)
『死をおそれないで生きる~がんになったホスピス医の人生論ノート』(いのちのことば社、2007年)
財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院のHP
http://www.vories.or.jp/
【後記】
90名を超す大勢の方々に参加して頂きました。
難い演題でしたが、細井先生は柔和な表情で、時に関西弁を交え、にこやかに語ってくれました。患者の心持は、繊細である。医療者の一言が心に響く。「患」という字は、串ざしの心とも読める。手術の同意書は医師からの押し付けになってはいないか?終わりを意識した生き方が大事、、、。講演もよかったのですが、最後の質疑応答も実のあるものでした。
著書『死をおそれないで生きる~がんになったホスピス医の人生論ノート』に以下のくだりがあります。患者さんや家族の持つ悩みは、ホスピスで過ごすわずかの間に解決できるはずがない。解決に至らなくても、共に悩みを分かち合うことは出来る。分かち合うことが解決の糸口になる。
今回語られたのは「ホスピス」でしたが、心のケアという点では一般の医療の中に取り入れるべきものも多いと感じました。そしてこれまでの自分の生き様を考えるいい機会になりました。
『済生会新潟第二病院眼科 市民公開講座2007』
シンポジウム 「患者として思う、患者さんを想う」
稲垣吉彦(患者;有限会社アットイーズ 取締役社長、千葉県)
荒川和子(看護師;医療法人社団済安堂 井上眼科病院、東京)
三輪まり枝(視能訓練士;国立身体障害者リハセンター病院)
コメンテーター
櫻井真彦(眼科医;埼玉医科大学総合医療センター教授)
日時:平成19年11月11日(日) 10時~12時半
場所:済生会新潟第二病院 10階会議室
今年の市民公開講座は、稲垣吉彦さんという一人の患者さんが著した「見えなくなってはじめに読む本」の内容に即して構成しました。稲垣さんは、大学卒業後銀行に就職しますが、ぶどう膜炎を患い、緑内障のため視力を失います。仕事を辞め、離婚、、、。でも今は取締役社長として活躍中です。どうしてこの困難を克服できたのでしょうか? 今回、稲垣さん、眼科主治医、看護師、視能訓練士にお話を伺いました。
「見えなくなってはじめに読む本」紹介URL
http://www.kigaruni-net.com/k01-2.html
「死刑宣告」の章に、執刀医として櫻井真彦先生(眼科医;現在、埼玉医科大学総合医療センター眼科教授)が登場します。『たっぷりと時間をかけて私の目の現状や手術の方法、治療計画や回復の見込みなど、知識がない私にも理解できるように理路整然と説明した』。「眼科医に望むこと」の章の一文を紹介します。『医師の患者に対する中途半端な気配りや優しさはいらない。ある意味冷酷であったとしてもその病気が治る病気なのか、それとも治らない病気なのか、初期段階できちんと宣告されたほうが、結果として患者を救うことになるのではないだろうか』。
看護師として登場するのが、荒川和子氏(井上眼科病院 看護部長)です。「私が看護師に望むこと」の章に以下の記載があります。『当事者のケア以上に家族のケアは看護師の重要な役割かもしれない。眼科の看護師が苦悩する当事者を間近で見守るという役割は、まさに家族と対等である。家族の苦悩を開放するためのカウンセリングこそ眼科看護師の重要な役割の一つではないだろうか』。
三輪まり枝氏(視能訓練士;国立身体障害者リハセンター病院)は、「見えることと読めること」の章に、同世代の明るい感じの視能訓練士として登場します。左目の中心に針の穴ほどの視野しか残っていないため、それまで新聞の文字など読めるはずもないと思っていた稲垣さんに、読めるようになるコツを優しく伝授してくれます。眼鏡の装用、書見台の利用、照明を明るくすること、残された視野が横長であることから縦書きの文字を横書きにして読むこと、拡大読書器の使用、、、。文字を読めた時の感動が紹介されています。『執刀医から見えるようにならないことを宣告されて以来、二度と読めないと思い込んでいた新聞を、予想外に読めることを知った私は、まるで旧友と再会できたかのように、この後しばらくの間時間を忘れその新聞を読みふけっていた』。
各演者の話の詳細を紹介します(長文です)。
【講演要旨】
「患者として思う」
稲垣 吉彦(患者:有限会社アットイーズ 取締役社長)
======================
私がぶどう膜炎「原田病」という病気を発症して、15年になります。この病気を発症する以前は、ほとんど病気には縁のない生活を送っていた私は、発症当時、自分自身が視覚障害者になることなど微塵も考えることはありませんでした。炎症が強いときには、自分でもちょっと見づらさを感じるものの、炎症が少し治まれば見え方は発症前と何ら変わらず、仕事を含め日常生活に何の影響もなく、当然完治するものと思いこんでいました。その後緑内障を併発し、発症から3年ほどで視覚障害者手帳を取得することになりました。
こんな私が、今一人の患者として思うことは、まず自分の健康にもっと関心を持つべきだということです。もっと早く行動を起こしていたら、これほどまで見えなくならずに済んだかも知れません。また、見えなくなった今でも、定期的に受診を続けることで、自分の目の状態を常に把握することができています。長年、ぶどう膜炎という病気とつきあっている中で、どのようなときに、もしくはどんなことをしたら炎症が強まり、見えづらくなるのか、自分なりにわかるようになりました。わかったからと言って、見えるようになるわけではありませんが、自分なりに理由付けができるだけでも、余計な不安は軽減されます。
第2には、何よりも情報が欲しいということです。自分の目の状態が医学的に見てどのような状態なのか、どうしたら少しでも見えやすくなるのか、見づらさを補う方法、利用できる福祉サービスの情報など、様々な情報をタイムリーに与えてもらえたら、生きていく希望も沸いてくる気がします。もっと身近なことでいえば、町中を歩いていて、そこに段差があるとか、車が停まっているなどという情報も、我々視覚障害者にとっては大切な情報です。
見えなくなったということは、悲しいことですが、私はそういう結果になってしまったことを、誰のせいでもなく、自己責任であると思っています。そうなってしまった自分が、生きていることに感謝しつつ、残された人生を楽しむためにも、家族や医療スタッフをはじめ、回りのみなさまから様々な情報を与えていただければと思っています。
「患者を想う」
荒川和子(看護師:井上眼科病院/東京)
======================
看護とは、人が本来持っているその力を引き出し、その人らしく生きることを支援することです。
看護師として以下のことを実践しています 1)目的意識を持って患者さんの話を傾聴する 2)情報提供:社会福祉制度の知識 3)視覚にかわる手がかりの活用:見えなくてもできるという成功体験 4)歩行訓練の基本を指導 5)家族への支援:家族の戸惑いを受け止める。
看護師が、見えないシュミレーション体験はケアを行なう上で有効です。そしてロービジョンの知識を持ち、患者さんに何が必要かを判断できることも大事です。
以下、実際の症例を紹介します。
Aさんは50歳代の女性で清掃業の仕事をしていました。家族は娘さんと二人暮らしでしたが現在は一人暮。独身の弟さんがキーパーソンです。以前から緑内障と言われていましたが、放置していました。入院する2か月前急に視力低下を自覚。知人の勧めでやっと受診し、医師から緊急入院を勧められても経済的理由から入院しませんでした。3日後に再診を約束して帰りましたが再診日に来ないため、担当医が自宅に電話をしました。やっと再来した時は、視力はさらに悪化し、両眼ともに視力は(0.01)でした。
看護師はまず、入院してきたAさんとのコミュニケーションを築く努力をしました。「入院できてよかった!不安だったでしょう?」と声をかけ、病気のこと、入院中の生活のこと、これからの生活のことも看護師が一緒に考えていくことをはっきり伝えました。
Aさんの反応を観察しながら、少しづつ入院中のリハビリテーションを始めます。食事が一人でもこぼさずに食べる事ができる、トイレに行く、薬を飲む、着替えをするなど一人でもできることを体験しておくことが必要でした。
医師の診断は「視力回復なし」でした。弟さんに本人への説明をどうしたらよいかを相談しました。弟さんは自分は面倒見ることが出来ないので本人にはっきり言ってほしいと希望しました。看護師は弟さんの希望を伝え、告知の場には看護師も同席し告知後のメンタルケアをさせて欲しいと医師に申し入れをしました。
医師は、「これからもっと良くなって、また自転車に乗ったりするように回復することは難しいです。これからの事は看護師さんも力になってくれるのでよく相談していきましょう。身体障害者手帳の申請もしましょう」と説明。
看護師は、「まず、地域の福祉課に相談しましょう」と提案し、地域のケースワーカーに連絡。ケースワーカーがAさんと面談し、生活保護の申請、家に帰らないで病院から生活訓練所に入れるように手続きをしました。そして、訓練後は生活保護規定のアパートを借りる用意があることまでの説明をして患者さんを励ましてくれました。連携が大切です。
「患者さんを想う」
三輪まり枝(視能訓練士:国立身体障害者リハセンター病院/所沢)
======================
「もし、私や家族が患者さんだったら、どうしてほしいだろう?」私は、ロービジョンケアにおいて患者さんと接する時に、このように自分の身に置き換えながら対応することを心がけています。
国立身体障害者リハビリテーションセンターのロービジョンクリニック:眼科医師、視能訓練士、生活訓練専門職、ケースワーカーの4職種がチームを組んで、ロービジョン患者さんの相談に応じています。
ロービジョンケアの手順:
1)「どのような見え方をしているか」という残存視機能を把握することが大切です。視力や視野の程度、斜視や眼球運動障害の有無、羞明の程度など、患者さんの目の状況を正確に知ることが基本となります。
2)「どんなことで困っているか」というニーズの聞き取り:その際にコーチング手法などの「聴く技術」です。ニーズを聞きだしながら、患者さんと一緒に問題点の整理をし、必要なケア内容を検討します。もし、患者さんが黄班変性症などにより、物を見ようとするちょうど中心が見えない場合は、視線を動かして見やすい場所で見る「偏心視」を獲得しているかどうかの確認を優先します。獲得していない場合、必要に応じて偏心視獲得の訓練を行います。
3)聞き取ったニーズに合わせた補助具の選定:補助具を2週間ほど貸し出し、その結果、日常生活に役立つものであれば処方され、合わなければ再選定を行います。見えにくさを補う補助具~文字や遠方が見えにくい場合は、拡大効果を得るための拡大鏡等。まぶしさがある場合は、羞明を軽減させる遮光眼鏡や帽子等。視野が狭い場合は、文字を読む際の行換えをスムーズにさせるタイポスコープ等。二重に見える場合は、プリズムや遮蔽するためのオクルーダーなど。各々の補助具の特徴を理解して選定することが重要です。
ロービジョンケアでは、こちら側からの一方的なサービスの提供だけではなく、患者さんからお教えいただくことも多々あります。これからも患者さんとの出会いを大切にしながら、少しでも見やすい環境を整えるお手伝いをして参りたいと思っております。
【後記】
110名収容できる会場が、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・長野・山形等、新潟県内外からの参加者で満員になりました。患者さんの話を聞く講演会、医師による講演会はよくありますが、患者さんとその治療に関わった医師・看護師・視能訓練士が一堂に介する企画、好評でした。
稲垣さんは、はじめに肉声で自己紹介をしました。吃驚しました。マイクを通すと視力が不自由な方はスピーカーの方向に演者がいると錯覚するためだそうです。なるほどと、のっけから感心しました。講演では情報が欲しいと強調されました。情報には、医学的情報のみでなく、ロービジョン的知識・社会福祉制度等さまざまな情報と、障害者への気配りも含まれていたように感じました。
荒川さんには、眼科看護師としての立場から患者ケアを語って頂きました。医学の中で眼科学はすごく発展していますが、一方、看護学の中で眼科看護という分野は未開拓であるように思います。今後ますますこの領域の発展に期待したいと思いました。
医者は治療の専門家ですが、その後のフォロー(治療から社会復帰への道のりへの手助け)が『ロービジョンケア』という分野です。三輪さんは、視能訓練士の立場からロービジョンケアの実際について、具体的にお話してくれました。
非常に困難な状況から稲垣さんが見事に立ち直った要因として、第1に患者さん自身が諦めなかった「患者の思い」、第2に治療に携わった医師が「責任を持って治療」に当たったこと、第3に看護師・視能訓練士が「患者さんの不自由さに想いを馳せてケアしたこと」(すなわちロービジョンケアなのですが)が挙げられると感じました。
質疑応答の中で、櫻井先生の「『患者さんが最大の師である』ということを再認識した」というコメントが印象的でした。