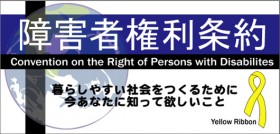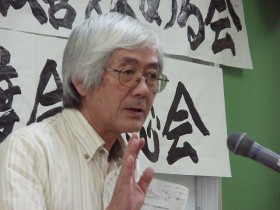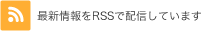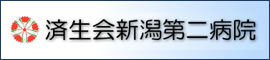「新潟盲学校弁論大会 イン 済生会」
日時:平成27年7月8日(水)16:30~17:30
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
注)終了時間がいつもより30分早いです
注)今回は、ネット配信による実況は致しません
(1)「僕の父」 中学部3年
(2)「夢は地道にコツコツと」 高等部普通科3年
【発表の紹介文】
「僕の父」
新潟県立新潟盲学校 中学部3年
僕は大切な家族があります。でも、僕は寄宿舎に泊まっているので、毎日は会えません。その家族の1人、父のことをみなさんに聞いてほしいと思います。寄宿舎から帰省したときのお風呂での様子、休日にいろいろなところへ連れて行ってくれること、父へのお願いなど、僕の大好きな父のことをお話します。
「夢は地道にコツコツと」
新潟県立新潟盲学校 高等部普通科3年
私には、二年間話すことができなかったことがあります。それは、高校受験の時のことです。私はたくさんの不安を抱えていました。しかし盲学校に入学して、その不安は吹き飛んでしまいました。その時の私の気持ちや、高校生活のこと、そして今私が抱いている将来の夢について、お話ししたいと思います。
【今後の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年8月1日(土) 開場;13時30分 研究会14時~18時
新潟ロービジョン研究会2015 「ロービジョンケアに携わる人達」
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
主催:済生会新潟第二病院眼科 要:事前登録
主催:済生会新潟第二病院眼科
http://andonoburo.net/on/3629
平成27年8月5日(水)16:30~18:00
第234回(15‐08月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「人生いろいろ、コーチングもいろいろ
高次脳機能障害と向き合うこと、ピアノを教えること」
立神粧子 (フェリス女学院大学教授)
平成27年9月9日(水)16:30~18:00
第235回(15-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題:街歩きを通して考える社会の視覚障害者観と当事者の心理
講師:清水美知子(フリーランスの歩行訓練士)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年10月10日(土)午後
済生会新潟第二病院 眼科公開講座2015「治療とリハビリ」
会場:済生会新潟第二病院10階会議室
要:事前登録
講演予定者
五味文(住友病院)
高橋政代(理研)
立神粧子(フェリス女学院大学教授)
http://andonoburo.net/on/3607
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年10月14日(水)16:30~18:00
【目の愛護デー記念講演会 2015】
(第236回(15-10)済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
演題未定
藤井 青 (ふじい眼科)
平成27年11月11日(水)16:30~18:00
第237回(15-11)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
郷家和子(帝京大学)
演題:「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」
講師:吉野 由美子 (視覚障害リハビリテーション協会)
日時:平成27年06月03日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【抄 録】
リハビリテーションという言葉の定義は、元々がキリスト教における「波紋を解き、身分を回復する」という意味から派生して「再び相応しい状態に戻す」の意味から、人生の半ばで何らかの障害を負った方たちに対して、生活や社会活動において失われた機能を回復させるための様々なサービスと規定されていますが、私がここでお話しする視覚障害者に対するリハビリテーションは、幼い頃からの視覚障害者や中途視覚障害者等すべての方たちの生活を向上させるためにおこなわれている医療・福祉・教育に関わる広範囲なサービスについて取り上げて、我が国におけるその歴史的展開について言及したいと思います。
また、私の話す視覚障害リハビリテーションの歴史は、視覚障害(ロービジョン)と肢体障害という重複障害を持った当事者として67年生きてきたことと、約40年間視覚障害リハビリテーションを我が国に普及させようと努力してきた私自身の経験から「これが我が国の視覚障害リハビリテーションの発展の重要ポイント」だと思ったことをピックアップして述べさせていただきたいと思います。少し偏った視覚障害リハビリテーションの歴史になるかもしれませんが、今後の我が国の視覚障害者に対するサービスの未来を考える時の一つの問題提起として聞いていただければ幸いです。
【プロフィール】
1947年 東京生まれ 67歳
1968年 東京教育大学(現筑波大学)付属盲学校高等部普通科卒業
1974年 日本福祉大社会福祉学部卒業後、名古屋ライトハウスあけの星声の図書館に中途視覚障害者の相談業務担当として就職(初めて中途視覚障害者と出会う)
1991年 日本女子大学大学院文学研究科社会福祉専攻終了(社会学修士) 東京都立大学人文学部社会福祉学科助手を経て1999年4月から2009年3月まで高知女子大学社会福祉学部講師→准教授 高知女子大学在任中、高知県で視覚障害リハビリテーションの普及活動を行う。
2009年4月より任意団体視覚障害リハビリテーション協会長(現在に至る)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【今後の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年7月
第233回(15‐07月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
新潟盲学校弁論大会 イン 済生会 (予定)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年8月1日(土) 午後
新潟ロービジョン研究会2015 「ロービジョンケアに携わる人達」
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
主催:済生会新潟第二病院眼科
要:事前登録
主催:済生会新潟第二病院眼科
http://andonoburo.net/on/3569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年8月5日(水)16:30~18:00
第234回(15‐08月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「人生いろいろ、コーチングもいろいろ
高次脳機能障害と向き合うこと、ピアノを教えること」
立神粧子 (フェリス女学院大学教授)
-----------------------
参考:新潟ロービジョン研究会2011 2011年2月5日(土)
『前頭葉機能不全 その先の戦略』立神粧子
http://andonoburo.net/on/3495
-----------------------
平成27年9月9日(水)16:30~18:00
第235回(15-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題:街歩きを通して考える社会の視覚障害者観と当事者の心理
講師:清水美知子(フリーランスの歩行訓練士)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年10月10日(土)午後
済生会新潟第二病院 眼科公開講座2015「治療とリハビリ」
会場:済生会新潟第二病院10階会議室
要:事前登録
講演予定者
五味文(住友病院)
高橋政代(理研)
立神粧子(フェリス女学院大学教授)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年10月14日(水)16:30~18:00
【目の愛護デー記念講演会 2015】
(第236回(15-10)済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
演題未定
藤井 青 (ふじい眼科)
平成27年11月11日(水)16:30~18:00
第237回(15-11)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
郷家和子(帝京大学)
演題:「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会に参加して」
講師:遁所 直樹(社会福祉法人 自立生活福祉会事務局長)
日時:平成27年05月13日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【抄 録】
障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく、Convention on the Rights of Persons with Disabilities)とは、あらゆる障害者(身体障害、知的障害及び精神障害等)の、尊厳と権利を保障するための人権条約です。
この条約は、21世紀では初の国際人権法に基づく人権条約であり、平成 18年12月13日に第61回国連総会において採択されました。日本国政府の署名は、平成 19年9月28日です。平成 25年12月4日、日本の参議院本会議は、障害者基本法や障害者差別解消法の成立に伴い、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准を承認しました。日本国の批准は平成 26年1月20日付けで国際連合事務局に承認されています。
現在、新潟市では、「障がいの有無に関わらず、誰もが暮らしやすく、市民一人ひとりが尊重される共生社会の実現」を目指し、本市独自の障がい者差別解消を図る「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例」の制定に向け、検討を重ねているところです。
来年度新潟市議会に承認を受けたのちに条例として成立することになりますが、その内容について現在の状況をお話ししたいと思います。
【プロフィール】
新潟大学大学院博士課程1年時頚椎 4番5番骨折頚髄損傷
平成10年から介護老人保健施設ケアポートすなやま勤務
平成12年から NPO法人自立生活センター新潟勤務
平成23年から社会福祉法人自立生活福祉会事務局長
新潟市障がい者施策審議会委員
(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会委員
【参考】
遁所さんが勉強会でお話するのは、今回が4回目です。これまでの講演要旨を以下に記します。
第91回 2003年12月10日
「期待せずあきらめず」 遁所 直樹
新潟市障害者生活支援センター分室
http://andonoburo.net/on/3537
第121回 2006年4月12日
「なぜ生まれる無年金障害者」遁所 直樹
NPO法人自立生活センター新潟 副理事長
兼 新潟学生無年金障害者の会 代表
http://andonoburo.net/on/3546
第188回 2011年10月12日
「NPO法人から社会福祉法人へ ~ 自立生活福祉会、今からここから」
遁所 直樹
社会福祉法人自立生活福祉会 事務局長
http://andonoburo.net/on/3551
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/section/ophthalmology/study.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【今後の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年6月3日(水)16:30~18:00
第232回(15‐06月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」
吉野由美子 (視覚障害リハビリテーション協会)
平成27年7月
第233回(15‐07月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
新潟盲学校弁論大会 イン 済生会 (予定)
平成27年8月1日(土) 午後
新潟ロービジョン研究会2015 「ロービジョンケアに携わる人たち」
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
主催:済生会新潟第二病院眼科
講演予定者
加藤聡(日本ロービジョン学会理事長)
仲泊聡(国立障害者リハビリセンター病院)
多和田 悟(盲導犬訓練士)
西脇 友紀(国立障害者リハビリセンター病院)
橋本伸子(看護師/石川県)
他
平成27年8月5日(水)16:30~18:00
第234回(15‐08月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「人生いろいろ、コーチングもいろいろ高次脳機能障害と向き合うこと、ピアノを教えること」
立神粧子 (フェリス女学院大学教授)
-------------------------
参考:新潟ロービジョン研究会2011~2011年2月5日(土)
『前頭葉機能不全 その先の戦略』立神粧子
http://andonoburo.net/on/3495
平成27年9月9日(水)16:30~18:00
第235回(15-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題:街歩きを通して考える社会の視覚障害者観と当事者の心理
講師:清水美知子(フリーランスの歩行訓練士)
平成27年10月10日(土) 13時30分開場 14:00~18:00
済生会新潟第二病院 眼科公開講座2015「治療とリハビリ」
会場:済生会新潟第二病院10階会議室
講演予定者
五味文(住友病院)
高橋政代(理研)
立神粧子(フェリス女学院大学教授)
平成27年10月14日(水)16:30~18:00
【目の愛護デー記念講演会 2015】
(第236回(15-10)済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
演題未定
藤井 青 (ふじい眼科)
演題:知る・学ぶ、そしてユーモアを忘れずに挑戦していくことの大切さ
―「慢性眼科患者」の経験から私が学んだこと―
講師:阿部直子(アイサポート仙台 主任相談員/社会福祉士)
日時:平成27年4月8日(水)16:30~18:00
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
【抄 録】
両目のまぶたに先天的な症状を持って生まれた私は、生後まもなくの頃から眼科とのおつきあいが始まりました。以来、40数年経った今も年数回の眼科受診を続けながら日常生活を送っています。
紆余曲折の末に辿り着いた大学院教育学研究科で学んだことが活かせる職種の職員募集が仙台市の市政だよりに載っていることを私に教えてくれた教官のおかげで、大学院修了後はさまざまな障害を持つ方の生活相談支援を担う部署に相談員として就職しました。人よりけっこう遅い「社会人1年生」のスタートを切ったわけですが、たまたま同じ時期に始まった仙台市の地域リハビリテーションモデル事業で視覚障害者支援に関するプロジェクトのいわば「現場スタッフ」の仕事も担当させていただくことになりました。これがきっかけで、さまざまな視覚障害者の生活設計・生活再建、あるいは眼科の患者さんやその家族が直面する心の動揺や葛藤を整理していく過程にソーシャルワーカーとしてかかわる現在の仕事につながりました。
「自分の体験だけでモノゴトのすべてを考えてはいけない」とは思いつつも、ものごころつく頃からの眼科での患児・患者としての経験から得たこと、社会全体からみればマイノリティ(少数者)であるロービジョンの状態で育ち生活してきた体験から学んだことが現在の仕事に少なからぬ影響を与えていると気づき、自分でも「人生ってオモシロイものだな」と苦笑してしまうことがしばしばあります。
今回は、そんな1人の患者、ロービジョン者として経験してきたことをもとにして、眼科での慢性的な疾患を持つ患者への対応の在り方や視覚障害という特徴とうまくつきあうために求められることなどについてお話しできたらと考えています。
【略 歴】
兵庫県出身。関西と関東を行き来しながら子ども時代を過ごす。
1995年 同志社大学文学部文化史学専攻卒業
2001年 東北大学大学院教育学研究科教育心理学専攻修士課程修了
2001年 (財)仙台市身体障害者福祉協会に仙台市太白障害者生活支援センター相談員として入職
この間、仙台市地域リハビリテーションモデル事業運営協議会ワーキンググループ委員(2002年~2004年)、中途視覚障害者への地域リハビリテーションシステム研究事業ワーキンググループ委員(2004年~2005年)を経験。
2005年 視覚障害者を支援する会(現在のNPO法人アイサポート仙台)に仙台市中途視覚障害者支援センター相談員として入職
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。下記のいずれでも視聴できます。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
http://nitsc.eng.niigata-u.ac.jp/saiseikai/
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/section/ophthalmology/study.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【今後の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年5月13日(水)16:30~18:00
第231回(15‐05月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされ
いかされる新潟市づくり条例検討会に参加して」
遁所 直樹 (社会福祉法人 自立生活福祉会事務局長)
平成27年6月3日(水)16:30~18:00
第232回(15‐06月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」
吉野由美子 (視覚障害リハビリテーション協会)
平成27年7月
第233回(15‐07月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
新潟盲学校弁論大会 イン 済生会 (予定)
平成27年8月5日(水)16:30~18:00
第234回(15‐08月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「人生いろいろ、コーチングもいろいろ
?高次脳機能障害と向き合うこと、ピアノを教えること?」
立神粧子 (フェリス女学院大学教授)
-------------------------
参考:新潟ロービジョン研究会2011~2011年2月5日(土)
『前頭葉機能不全 その先の戦略』立神粧子
http://andonoburo.net/on/3495
平成27年9月9日(水)16:30~18:00
第235回(15-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
清水美知子(歩行訓練士;埼玉県)
平成27年10月14日(水)16:30~18:00
【目の愛護デー記念講演会 2015】
(第236回(15-10)済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
演題未定
藤井 青 (ふじい眼科)
演題:「視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―」
講師:岸 博実(京都府立盲学校教諭・日本盲教育史研究会事務局長)
日時:平成27年03月11日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
済生会新潟第二病院眼科で、1996年(平成8年)6月から毎月行なっている勉強会の案内です。参加出来ない方は、近況報告の代わりにお読み頂けましたら幸いです。興味があって参加可能な方は、遠慮なくご参加下さい。どなたでも大歓迎です(参加無料、事前登録なし、保険証不要)。ただし、お茶等のサービスもありません。悪しからず。
【抄 録】
日本の盲人は“記憶”と“手技”を駆使して職業を獲得してきた。徳川時代には「自治」を経験し、教育機関も設けた。明治以降の盲教育は、西欧の知見に触発されつつ、日本的な特性を持って構築された。教育目的に掲げられた「自助」論を問い直す必要があろう。
まず、明治以降の<教育権>思潮を小西信八の言説と教員組織の営みを通してなぞり、「盲・ろう教育の義務化と分離」が希求された経緯と、特別支援教育の課題を考える。
次に、視覚障害当事者の営為を振り返る。好本督や鳥居嘉三郎による「同窓会」・「日本盲人会」の結成が点字新聞等の発行へとつながった。高等教育を志した青年の先駆性、木下和三郎『盲人歩行論』の先見性にも光を当て、「自己実現」追求の意義を確かめる。
さらに、「人類の文字が東西ともに凹字から始まったのはなぜか」の考察を入り口に、「紙と平らな文字(墨字)」時代の明と暗をみつめ、凸字から点字へと飛躍した画期的な展開をおさえる。「文字の世界の新人」である点字の魅力と将来像を吟味する。
最後に、新潟ゆかりの先人たち-小西信八が示した点字を最初に読みこなした小林新吉、高田訓矇学校を興した大森隆碩たち、『玄海』(辞書)や『内国地図』(教科書)を点訳した東京盲唖学校訓導・大森ミツ-に思いを馳せたい。
<高田盲学校史料>の中から埋もれた希少資料を紹介し、新潟の視覚障害教育史資料の保存及び活用への期待を述べたい。
【略 歴】
1972年(昭和47年) 広島大学教育学部卒業
1974年(昭和49年)~ 京都府立盲学校教諭
2011年(平成23年)~ 点字毎日・点字ジャーナルに盲教育史連載
2012年(平成24年)~ 日本盲教育史研究会事務局長
2013年(平成25年)~ 滋賀大学教育学部非常勤講師
6月 盲人史国際セミナーinパリで招待講演を担当
2014年(平成26年)7月 第23回視覚リハビリテーション研究発表大会で講座を担当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。下記のいずれでも視聴できます。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
http://nitsc.eng.niigata-u.ac.jp/saiseikai/
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/section/ophthalmology/study.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【今後の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年4月8日(水)16:30~18:00
第230回(15‐04月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「知る・学ぶ、そしてユーモアを忘れずに挑戦していくことの大切さ
―『慢性眼科患者』の経験から私が学んだこと」
阿部直子(アイサポート仙台 主任相談員/社会福祉士)
平成27年5月13日(水)16:30~18:00
第231回(15‐05月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされ
いかされる新潟市づくり条例検討会に参加して」
遁所 直樹 (社会福祉法人 自立生活福祉会事務局長)
平成27年6月3日(水)16:30~18:00
第232回(15‐06月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」
吉野由美子 (視覚障害リハビリテーション協会)
平成27年7月
第233回(15‐07月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
新潟盲学校弁論大会 イン 済生会 (予定)
平成27年8月5日(水)16:30~18:00
第234回(15‐08月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
立神粧子 (フェリス女学院大学)
平成27年9月9日(水)16:30~18:00
第235回(15-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
清水美知子(歩行訓練士;埼玉県)
演題:「視覚障害者の化粧技法について~ブラインドメイク・プログラム~」
講師:大石華法(日本ケアメイク協会)
日時:平成27年02月4(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
済生会新潟第二病院眼科で、1996年(平成8年)6月から毎月行なっている勉強会の案内です。参加出来ない方は、近況報告の代わりにお読み頂けましたら幸いです。興味があって参加可能な方は、遠慮なくご参加下さい。どなたでも大歓迎です(参加無料、事前登録なし、保険証不要)。ただし、お茶等のサービスもありません。悪しからず。
【抄 録】
化粧は社会人女性としての「身だしなみ」であると言われている.身だしなみとは,自分自身の容姿を整える心がけとこれから会う人への思いやりを意味しており,化粧とは女性の美しさと優しさ,上品さや裕福さを象徴するアイテムになっている.
2000年から2014年までの化粧の有用性に関する研究として,化粧には心理的・生態的効果があり,女性の社会性を促進し,QOLを高める効果があると報告されている.また女性を精神面でも支え,社会的コミュニケーションを円滑にするという重要な役割を担っていると示唆されている.
近年,化粧社会のなかで視覚に障害があることで化粧に不自由を感じている女性はこれらを理由に化粧を諦める傾向にある.他者からの化粧評価が低いと自信を失い,化粧を施すことに不安を感じている女性が少なくない.これらは外出の減少,人や社会との交流減少に影響を及ぼしている.
演者は,2010年に鏡を見なくても化粧が綺麗にできる化粧技法「ブラインドメイク・プログラム」を考案したことで視覚に障害のある女性が自分自身で化粧することが可能となった.化粧が綺麗にできるようになった女性からは「自信をもって外出し,人や社会に交わることに対して前向きになった」「自己肯定感,満足感,幸福感を得ることができた」と高い評価を得ている.ブラインドメイクは,“視覚障害者”ではなく,一人の“女性”として当事者や社会が認識・再認識することに意義を求めている.
【略 歴】
1995年,中央大学 法学部法律学科 卒業
2010年,大阪中央理容美容専門学校 卒業
2012年,日本福祉大学 福祉経営学部 卒業
2013年,日本福祉大学大学院 社会福祉学研究科 在学中
日本ケアメイク協会 会長(2010年~)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/section/ophthalmology/study.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【今後の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年2月28日(土)15時開場 15:30~17:00
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
『済生会新潟第二病院眼科 公開講座2015「細井順講演会」』
「生きるとは…『いのち』にであうこと~死にゆく人から教わる『いのち』を語る~」
細井順(ヴォーリズ記念病院ホスピス希望館長;滋賀県近江八幡市)
平成27年3月11日(水)16:30~18:00
第229回(15‐03月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―」
岸 博実(京都府立盲学校教諭・日本盲教育史研究会事務局長)
平成27年4月8日(水)16:30~18:00
第230回(15‐04月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「知る・学ぶ、そしてユーモアを忘れずに挑戦していくことの大切さ―『慢性眼科患者』の経験から私が学んだこと」
阿部直子(アイサポート仙台 主任相談員(社会福祉士))
平成27年6月10日(水)16:30~18:00
第232回(15‐06月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「我が国の視覚障害者のリハビリテーションの歴史」
吉野由美子 (視覚障害リハビリテーション協会)
平成27年7月
第233回(15‐07月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
新潟盲学校弁論大会 イン 済生会 (予定)
平成27年8月5日(水)16:30~18:00
第234回(15‐08月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
立神粧子 (フェリス女学院大学)
平成27年9月9日(水)16:30~18:00
第235回(15-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
清水美知子(歩行訓練士;埼玉県)
平成27年10月14日(水)16:30~18:00
【目の愛護デー記念講演会 2015】 (予定)
(第236回(15-10)済生会新潟第二病院 眼科勉強会)
「視覚障がい者としての歩み~自分と向き合いながら、社会と向き合いながら」
青木 学(新潟市市会議員)
日時:平成27年01月14(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
済生会新潟第二病院眼科で、1996年(平成8年)6月から毎月行なっている勉強会の案内です。参加出来ない方は、近況報告の代わりにお読み頂けましたら幸いです。興味があって参加可能な方は、遠慮なくご参加下さい。どなたでも大歓迎です(参加無料、事前登録なし、保険証不要)。ただし、お茶等のサービスもありません。悪しからず。
【抄 録】
小学6年の時、網膜色素変性症のため視力を失いました。その後、新潟盲学校中学部に入学し、高等部を卒業するまでの6年間をそこで過ごしました。その間、見えない状態で生活することにも慣れ、好きな音楽や野球部の活動に勤しみながら、楽しく学校生活を送っていました。ただ高校生になったころから、盲学校の外の世界はどんなところなのか。もっと多くの人と出会って、もっと広い世界を見てみたいという気持ちが強く湧き上がってきました。しかしそのようなことを思っても、目の見えない自分に何ができるわけでもないと常に自分の気持ちを押さえつけていました。
そのような時、高校3年の担任の先生との進路相談の際、先生から「外の世界を見てみないか。」と言われ、それがきっかけとなり、京都の大学への進学、アメリカ留学そして帰国後の市議会議員選挙への立候補へと繋がっていきます。こうした経験の中で、「見えない」ということに対する自分の中での捉え方、社会との向き合い方が大きく変わっていきます。
日本でも障害者の権利条約が批准され、差別解消法も制定されました。また新潟市においても、現在差別解消を目的とした条例づくりが進められています。こうした動きを踏まえながら、障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされ、共に生きていける新潟市を築いていくため、さらに活動を進めていきたいと思っています。
【略 歴】
1966年 旧亀田町(現新潟市)に生まれる。小学6年の時に失明。
新潟盲学校中・高等部、京都府立盲学校専攻科普通科を経て、京都外国語大学英米語学科。
1991年 同大学卒業。米国セントラルワシントン大学大学院に留学。
1993年 同大学院終了。帰国後、通訳や家庭教師を務めながら市民活動に参加。
1995年 「バリアフリー社会の実現」を掲げ、市議選に立候補し初当選を果たす。
2011年 5期目の再選を果たし、2年間副議長を務める。
現在議員の他、社会福祉法人自立生活福祉会理事長、新潟市視覚障害者福祉協会会長、県立大学非常勤講師としても活動中。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。下記のいずれでも視聴できます。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
http://nitsc.eng.niigata-u.ac.jp/saiseikai/
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/section/ophthalmology/study.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【次回以降の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年2月4日(水)16:30~18:00
第228回(15‐02月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の化粧技法について~ブラインドメイク・プログラム~」
大石華法(日本ケアメイク協会)
平成27年2月28日(土)15時開場 15:30~17:00 @事前登録
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室 『済生会新潟第二病院眼科 公開講座2015「細井順講演会」』
「生きるとは…『いのち』にであうこと~死にゆく人から教わる『いのち』を語る~」
細井順(ヴォーリズ記念病院ホスピス希望館長;滋賀県近江八幡市)
http://andonoburo.net/on/3348
平成27年3月11日(水)16:30~18:00
第229回(15‐03月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―」
岸 博実(京都府立盲学校教諭・日本盲教育史研究会事務局長)
平成27年4月8日(水)16:30~18:00
第230回(15‐04月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「知る・学ぶ、そしてユーモアを忘れずに挑戦していくことの大切さ―『慢性眼科患者』の経験から私が学んだこと」
阿部直子(アイサポート仙台 主任相談員(社会福祉士))
平成27年9月9日(水)16:30~18:00
第235回(15-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
清水美知子(歩行訓練士;埼玉県)
第226回(14‐12月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題:視覚障害児者の福祉・労働・文化活動への貢献 ~盲学校が果たした役割~
講師:小西 明(新潟県立新潟盲学校)
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
日時:平成26年12月10日(水)16:30~18:00
済生会新潟第二病院眼科で、1996年(平成8年)6月から毎月行なっている勉強会の案内です。参加出来ない方は、近況報告の代わりにお読み頂けましたら幸いです。興味があって参加可能な方は、遠慮なくご参加下さい。どなたでも大歓迎です(参加無料、事前登録なし、保険証不要)。ただし、お茶等のサービスもありません。悪しからず。
【抄 録】
平成26年2月19日「障害者の権利に関する条約」が発効し、 我が国において障害者等が積極的に社会参加できることや、相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型社会の形成への取り組みが、今後一層進展するものと期待されています。教育では、こうした共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための様々な施策が推進されています。
さて、「障害者の権利に関する条約」発効に伴う国内法の整備により、障害児者に関わる法制度改革がなされました。明治11年(1878) 日本ではじめての盲学校、京都盲唖院の開校から現行法制度に至までの過程で、全国盲学校は教育に留まらず、視覚障害児者のためのトータルサポートセンターとしての役割を担ってきました。具体的には、相談・補助具活用などの視覚障害者福祉、三療や音曲などの職業教育、三療以外の職業開拓、公立点字図書館設置運動、視覚障害者のスポーツ振興など、ニーズに応じて支えてきた歴史があります。
前回、平成24年1月は新潟盲学校の学校要覧をもとに、在籍者数、教職員数、眼疾患、教育内容、学校行事等について概観しました。今回は、新潟盲学校が視覚障害児者の教育を担うと共に、福祉、労働、文化の牽引役として果たしてきた内容を時系列で紹介し、今後の盲学校(視覚特別支援学校)の在り方を展望します。
【略 歴】
1977年 新潟県立新潟盲学校教諭
1992年 新潟県立はまぐみ養護学校教諭
1995年 新潟県立高田盲学校教頭
1997年 新潟県立教育センター教育相談・特殊教育課長
2002年 新潟県立高田盲学校校長
2006年 新潟県立新潟盲学校校長
@新潟県立新潟盲学校
http://www.niigatamou.nein.ed.jp/index.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。下記のいずれでも視聴できます。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
http://nitsc.eng.niigata-u.ac.jp/saiseikai/
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/section/ophthalmology/study.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【次回以降の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成27年1月14日(水)16:30~18:00
第227回(15‐01月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障がい者としての歩み~自分と向き合いながら、社会と向き合いながら」
青木 学(新潟市市会議員)
平成27年2月4日(水)16:30~18:00
第228回(15‐02月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の化粧技法について~ブラインドメイク・プログラム~」
大石華法(日本ケアメイク協会)
平成27年2月28日(土)15時開場 15:30~17:00
『済生会新潟第二病院眼科「細井順講演会」』
演題:生きるとは…「いのち」にであうこと~死にゆく人から教わる「いのち」を語る~
講師:細井順(ヴォーリズ記念病院ホスピス希望館長;滋賀県近江市)
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室(予定)
平成27年3月11日(水)16:30~18:00
第229回(15‐03月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―」
岸 博実(京都府立盲学校教諭・日本盲教育史研究会事務局長)
平成27年4月8日(水)16:30~18:00
第230回(15‐04月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
阿部直子(アイサポート仙台)
第225回(14‐11月)済生会新潟第二病院 眼科勉強会
演題:「世界一過酷な卒業旅行から学んだ、小さな一歩の大切さ」
講師:岡田果純(新潟大学大学院自然科学研究科専攻修士課程2年)
日時:平成26年11月5日(水)16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【抄 録】
私は1999年6月、小学校3年生の時に1型糖尿病を発症し、以来15年間毎日インスリン注射をしています。発症当時の主治医が「インスリン注射をしていれば、なんでもできるよ」と言う言葉をくれました。その言葉通り、バスケ、スキー、マラソンと様々なことに挑戦してきました。糖尿病になったおかげで、両親を始め周囲の人の温かい存在に気付くことができました。そして、病気が多くの出会いをもたらせてくれました。特にサマーキャンプと言われる糖尿病の子供が集まるキャンプでできた同じ病気の仲間は、今でも心強い存在です。
大学では、アルバイトに旅に、新しい世界を知ることが楽しくなっていきました。そんな時、世界一過酷と言われる砂漠マラソンに挑戦するという先輩の話を聞きました。7日間、自給自足で250kmを走る。聞いた瞬間、「面白そう!」と思い、挑戦を決めました。挑戦を決めてから本番を迎えるまでは、長かったようで短く、苦しかったようで楽しかったです。とにかく、自分にできる小さなことを積み重ねました。トレーニングは3km走るところから。血糖値のコントロールについてもたくさんの人にアドバイスをもらいました。
迎えた本番も、小さな1歩の積み重ね、30cm足を前に出すことの繰り返しでした。250kmを完走したゴールの瞬間、体中から溢れて来たのは感謝の気持ちでした。どんな困難にも、有難いという気持ちを持つ。これが私の固い信念となりました。
【略 歴】
1990年 長野県生まれ 新潟県妙高市育ち
1999年 1型糖尿病発症
2009年 新潟県立高田高校卒業
2013年 アタカマ砂漠マラソン(Atacama Crossing 2013)完走
新潟大学卒業
2014年現在 新潟大学大学院修士課程2年
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。下記のいずれでも視聴できます。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
http://nitsc.eng.niigata-u.ac.jp/saiseikai/
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/02/ganka/index5.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【次回以降の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成26年12月10日(水)16:30~18:00
第226回(14‐12月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害児者の福祉・労働・文化活動への貢献 ~盲学校が果たした役割~」
小西 明(新潟県立新潟盲学校 校長)
平成27年1月14日(水)16:30~18:00
第227回(15‐01月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障がい者としての歩み~自分と向き合いながら、社会と向き合いながら」
青木 学(新潟市市会議員)
平成27年2月4日(水)16:30~18:00
第228回(15‐02月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の化粧技法について~ブラインドメイク・プログラム~」
大石華法(日本ケアメイク協会)
平成27年2月28日(土)15時開場 15:30~17:00
会場:済生会新潟第二病院 10階会議室
『済生会新潟第二病院眼科「細井順講演会」』
演題:生きるとは…「いのち」にであうこと
~死にゆく人から教わる「いのち」を語る~
講師:細井順(ヴォーリズ記念病院ホスピス希望館長;滋賀県近江市)
平成27年3月11日(水)16:30~18:00
第229回(15‐03月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―」
岸 博実(京都府立盲学校教諭・日本盲教育史研究会事務局長)
平成27年4月8日(水)16:30~18:00
第230回(15‐04月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
演題未定
阿部直子(アイサポート仙台)
案内:第224回(14‐10月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「目の愛護デー記念講演2014」
演題:「視力では語れない眼と視覚の愛護」
講師:若倉雅登 (井上眼科病院;名誉院長)
日時:平成26年10月8日(水)17:00 ~ 18:30
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演抄録】
「目の愛護デー」が近くなると、「目を大切に」「視力を大切に」といった標語が目につくようになる。 そこで眼球の構造やそこに生じる、ドライアイや白内障や、緑内障など、聞きなれた眼の疾患を思い起こす人も多いだろう。眼科の領域は実は非常に広い。
私は神経眼科、心療眼科を専門として40年近く診療を続けてきている中で、快適な視覚を得るためには、眼球と脳の精緻な共同作業が必要なことを学んできた。しかも、左右眼のバランスは、その機能を発揮する上で非常に大切で、逆にアンバランスは眼精疲労の原因になるだけでなく、日常視、日常生活に甚だしい支障をもたらし、高度な場合には心の問題も惹き起こす。ここには左右眼それぞれの視力がいかに良好でも起きる可能性のある問題が存在し、「目」というと、「視力」のことばかり考える眼科医や、一般人にとっては大きな落とし穴となる。このような例は、決して珍しいことではなく、不都合の原因として気付いてないだけのことが多い。
本講演では事例を実際にわかりやすく紹介しながら、眼と視覚の健康について改めて考えてみたい。
【略歴】 若倉雅登(わかくらまさと) (2014年4月現在)
1976年3月 北里大医学部卒
1980年3月 同 大学院博士課程終了
1986年2月 グラスゴー大学シニア研究員
1991年1月 北里大医学部助教授
1999年1月 医)済安堂 井上眼科病院 副院長
2002年1月 医)済安堂 井上眼科病院 院長
2012年4月 医)済安堂 井上眼科病院 名誉院長
ほかに現在:北里大学医学部客員教授、東京大学医学部非常勤講師
日本神経眼科学会理事長、日本眼科学会評議員など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の勉強会の一部は、「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力によりネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。下記のいずれでも視聴できます。
http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai
http://nitsc.eng.niigata-u.ac.jp/saiseikai/
当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『済生会新潟第二病院 眼科勉強会』
1996年(平成8年)6月から、毎月欠かさずに続けています。誰でも参加出来ます。話題は眼科のことに限らず、何でもありです。参加者は毎回約20から30名くらいです。患者さん、市民の方、医者、看護師、病院スタッフ、学生、その他興味のある方が参加しています。眼科の外来で行いますから、せいぜい5m四方の狭い部屋で、寺子屋的な雰囲気を持った勉強会です。ゲストの方に約一時間お話して頂き、その後30分の意見交換があります。
日時:毎月第2水曜日16:30~18:00(原則として)
場所:済生会新潟第二病院眼科外来
*勉強会のこれまでの報告は、下記でご覧頂けます。
1)ホームページ「すずらん」
新潟市西蒲区の視覚に障がいのある人とボランティアで構成している音声パソコン教室ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~suzuran/saisei.html
2)済生会新潟第二病院 ホームページ
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/02/ganka/index5.html
3)安藤 伸朗 ホームページ
http://andonoburo.net/
【次回以降の済生会新潟第二病院眼科 勉強会 & 研究会】
平成26年11月5日(水)16:30~18:00
第225回(14‐11月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「世界一過酷な卒業旅行から学んだ、小さな一歩の大切さ」
岡田果純(新潟大学大学院自然科学研究科専攻修士課程1年)
@第1水曜日です
平成26年12月10日(水)16:30~18:00
第226回(14‐12月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害児者の福祉・労働・文化活動への貢献 ~盲学校が果たした役割~」
小西 明(新潟県立新潟盲学校 校長)
平成27年1月14日(水)16:30~18:00
第227回(15‐01月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障がい者としての歩み~自分と向き合いながら、社会と向き合いながら」
青木 学(新潟市市会議員)
平成27年2月4日(水)16:30~18:00
第228回(15‐02月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の化粧技法について~ブラインドメイク・プログラム~」
大石華法(日本ケアメイク協会)
平成27年3月11日(水)16:30~18:00
第229回(15‐03月)済生会新潟第二病院眼科勉強会
「視覚障害者の求めた“豊かな自己実現”―その基盤となった教育―」
岸 博実(京都府立盲学校教諭・日本盲教育史研究会事務局長)