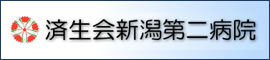報告:第87回済生会新潟第二病院眼科勉強会 清水美知子
日時:2003年8月20日(水) 16:30~18:00
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
演題 「Coming-out Part 2 家族、身近な無理解者」
演者 清水美知子(歩行訓練士)
【抄録】
今回は家族について考えます.家計を支えていた父、家事を仕切っていた母、あるいは夫、妻、娘、息子がある日障害を負うと、家計の状況や家族の役割分担など一変します.家族という運命共同体の中で、家族は当事者の自立の支援者にも、阻害者にもなりえます.どちらの場合も、関係が密であるだけに当事者の将来に多大な影響を及ぼします.それだからこそ家族が強力な支援者としてあり続けてもらうために、家族の悲しみ、悩み、苦労を理解し、支援することが大切なのです.つぎにあげたのは家族が抱える悩みの例です.
母が障害者であることを恋人に打ち明けられない娘. 娘が白杖を突いて隣近所を歩くのを許さない母. 依存的な夫と、”優しい妻” 被介護者、被扶養者となり、戸惑い、自信を喪失した夫 障害のせいなのか、怠惰なのかいつまで経っても動こうとしない夫にいらだつ妻 公的サービスを拒否して妻に介護を求める夫 妻のどう介助したらよいかわからず戸惑う夫 妻と夫の間に起きた地位の逆転 家計と介護を握ったものの専制
【肩書きと略歴】
歩行訓練士
信楽園病院視覚障害リハビリ外来担当
1979年から23年間視覚障害者更生施設施設長
【後 記】
今回講師の清水さんは、昨年9月のこの会で「Coming-out」という題で話してくれました。その趣旨は、障害を持った人は、社会に出て自分たちのことを他の人に知らしめなければ、社会を変えることは出来ないというものでした。今回はその続編です。「家族」には「温かさ」がある。とても強い繋がりがある。困った時にまっ先に支えてくれる第1候補である。まさに外海の荒波から護ってくれる「防波堤」である。でも、、、、一方では、外に社会に出て行こうとする障害者のプロセスを、阻んでしまうのではないかという話でした。
「家族」は、知らず知らずに「(柔らかな)檻」を作っている。例えば、、、、この子には一人で外出なんかとても無理だ。私が生きている間は、何でも私がやってあげる、、、、、。
「家族」は、同じ価値観を共有するが、障害に対しては、障害を持つ本人の受け入れと、家族の受け入れには「ズレ」がある。
「家族」との縁は、切り捨てられない。他人であれば嫌な思いをさせる人とは付き合わないようにする事も出来るのだが、、、、
「家族」は、時に自尊心を低下させる態度を取ることがある(誰も気付いてはいないが)。横柄な態度をとる、何かと指図をする、過保護になる、怒る、、、、、、。
例えば、こんなこともある。姑と上手くいかなかった嫁さんが障害を持つ事になり、何でも姑の言うことを受け入れなければならなくなった。好き放題なことをやっていたご主人が、障害を持ってからは奥さんの言いなりになる。大学を卒業し、家をでてアパートに暮らすといっていた息子が、家に暮らすようになった。母が障害者であることを恋人に打ち明けられない娘、娘が白杖を突いて隣近所を歩くのを許さない母、被介護者、被扶養者となり、戸惑い、自信を喪失した夫、、、、、、、。
でも実は「家族」も苦しんでいる。今後の家族関係はどうなるのだろうか?収入は、ローンはどうなるのだろうか?先の見通しが立たない。自分自身の時間が無くなってしまう、障害のせいなのか、怠惰なのかいつまで経っても動こうとしない夫にいらだつ妻、公的サービスを拒否して妻に介護を求める夫、妻をどう介助したらよいかわからず戸惑う夫、、、、、。
「家族」が感じる罪悪感もある。あの人さえいなければ、もっと自由な時間が持てるのにと感じてしまう自分が嫌だ。障害者を持つ家族が出来ることは、何か特別なことをするのでなく、いつも傍にいて耳を傾けて悩みを聴くこと。そのためには、時には休む、自分自身の時間を持つ、自分の事も相手の事も責めない。障害を持つ人の家族への接し方は、家族も苦しんでいる事を知る、何でもやってもらうのではなく(これは自分でやるという)ケジメを作る、助言を受け積極的に参加する、「こうしないで下さい」ではなく「こうして下さい」という発想を持つ。
講演終了後、参加者の方からも多くの意見や感想がありました。家族との関わり合いは、建前ではなく本音でないと話せない話題だけに、熱のこもった勉強会になりました。
報告 第86回(03-07) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会
“新潟盲学校生徒による弁論大会in 済生会”
日時: 平成15年7月9日(水) 16:30~18:00
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
1)『最初のひとこと』 大渕真理子 中学部2年生
2)『発想の転換で、いろいろとできる』 星野慎矢 高等部普通科2年生
3)『ざる頭』 小野塚厚司 高等部専攻科3年生
=================================================
1)『最初のひとこと』大渕真理子 中学部2年生
昨年の夏、「視覚障害者のためのアメリカ文化交流とホームステイ」に参加。空港に降り立ったとたん、周囲は英語ばかり。頭の中は真っ白になり、憂鬱だったが「Nice to meet you」の一言が言えた。あとは楽しい旅行となった。最初の一言を自分から言い出す勇気を持ちたい。
2)『発想の転換で、いろいろとできる』星野慎矢 高等部普通科2年生
自分は今まで物事に取り組む際、「一つの方法、人と同じ方法」というのにこだわって、他のやり方をしようとしなかった。つまずいてはあきらめ、そんな自分に嫌悪感を抱いていた。しかし、級友の一言、音声パソコンを知ったこと、料理等で、一つの方法にこだわるのではなくて、発想を転換することで道が拓けるということを体験し、前向きに取り組めるようになった。
3)『ざる頭』小野塚厚司 高等部専攻科3年生
登校途中にある園芸センターの垣根に咲こうとする「卯の花」を見て、専攻科入学当初へと思いが及ぶ。水を入れても貯まらない「ざる頭」を水に漬けっぱなしにするように、ひたすら勉強しようと決意した2年前を思い出し、今年最後となる「垣根の花」との再会を前に、一歩一歩目標に向かって進もうという思いを新たにする。
報告:第84回(2003‐5月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会 栗原隆
演題:「共感とケアの成り立ち」
講師:栗原隆 (新潟大学教授;生命倫理)
日時: 平成15年5月14日(水) 16:30~18:00
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要約】
1 他人の痛みは分かるか? 心はどこに存在するのか
他人の痛みは分からない。私の歯が痛む時、隣の人は快適に過ごしているかもしれない。私の足が痛くて、歩くのさえ辛い時、ひょっとすると足を引きずっていることで、足が痛そうだということが察知されることもあるかもしれないが、それでさえ、私の足の痛みを他人は感じることはない。ひょっとすると、あなた自身は人間でも、他人はアンドロイドかもしれない、いやロボットかもしれないし、異星人かもしれない。私たちは他人については何一つ自分のことのように知ることができない。それでいて、おおむね経験上、周囲の人々が自分と同じ人間であると想定して、振舞っている。それはある種思い込みかもしれない。なぜかというと、私がワイシャツの胸ポケットに入れておいた小銭がポケットに開いた穴から落ちて、体を滑り落ちてゆくのを止めようとおなかを抱きかかえた時、人は、私が腹痛に苦しんでいると思うかもしれない。目でウインクしたのに、単にゴミが入ったと思われるかもしれないからである。
私たちは、他人の痛みを何ら体験することはできないが、ある程度は、その身振りや仕草、さらには言葉で訴えるものから、自分の体験を振り返って、それに基づいて類推する。主観的な根拠に照らし合わせての類推であるからして、相手に生じている事態を言い当てることもあるかもしれないが、外れることもある。私たちは、他人を類推することしかできないのかもしれない。痛みだけでなく、相手の気持ちだってそうである。たとえ、言葉でコミュニケーションを図る時でさえ、相手を理解したと思っていても、実は自分の理解でしかない。そのことは次の俳句の例から明らかである。
古寺に 斧こだまする 寒さかな
わが恋は 空の果てなる 白百合か
実は、この俳句はコンピュータで文字を配列しただけのものなのである。きわめて簡単なプログラムだというが、デモンストレーションしているところに来た客が、「ヒヤヤッコ」と入力したらたちどころに、
冷奴 我が影にさす 酒の酔いと答えたという。
それを見ていたご婦人が、それでは私もと「夏草や」と入力したら、コンピュータは今度は
夏草や 盛り過ぐらむ 身の嘆き
と応じたという嘘のような本当の話が報告されている(『理想』一九八三年一二月号水谷静夫「国語研究と計算機」)。
たとえば、この場合、文字列が俳句だと思われようと思われまいとに関わらず、作者というものが存在していると見なす立場もあろう。そうした立場では実際の作者はコンピュータ、あるいはプログラマーということになるかもしれない。こうした立場をさしあたり、作者についての「実体論的把握」と整理しておこう。
これに対して、作品というものは読まれることによって初めて成立するのであって、作者とは厳然と実体のように存在しているのではなくて、読まれ、作品と見なされてこそ作者というものが、俳句の背後に虚焦点のように想定されるのであるからして、文字列を読み取り、解釈して、理解して、思いや感慨を抱いて、作品を作品たらしめるのは、実は読み手自身の心情や思想や体験に他ならないとする立場も可能である。こうした立場によれば、作者は読み手になる。これをさしあたり、作者についての「関係論的把握」と呼んでおこう。
私たちは、自分なりにその言葉の羅列を、俳句だと解釈して、そのうえで、作者の気持ちを類推しているのである。普通なら、理解したと思う言葉によるコミュニケーションでさえ、これである。相手への思いやりというものがいかに不確かなものであるか、ということはもって瞑すべしである。
心というものは、ある存在者、人間なりコンピュータなりペットなり、相手そのものに内在している何らかのものだ、と心を想定する立場は実体論的な把握だと言えよう。これに対して、心とは他の存在者との関わりの場において成立する解釈の対象なのだ、とする立場は関係論的な把握ということになろう。
〈心〉だけではない。たとえば、〈情〉とか〈共感〉、〈思いやり〉などというものも、私たちは持ち合わせているわけでは決してない、ただ、その場の状況において、そのように受け取られることがある。〈心ある〉行為や〈情け深い〉応対、相手への〈共感〉の表明だと、相手に受け取られるところにおいて、〈心〉が現出する、というわけである。
2 共通感覚と体性感覚
近代に入って成立した市民社会では、不特定多数の人間の交流が生じることによって、これまでの倫理とは違う価値観が生まれることになった。「共感」や「同情」という観念も市民社会時代を迎えるに当たって、新たに生まれた感覚だった。確かに、古代ギリシア以来、コモン・センスの観念はあった。ところがそれは、決して社会の中で人々が共通に抱くセンス・感覚という意味ではなかった。むしろ、「もともとコモン・センスは、諸感覚にわたって共通で、しかもそれらを統合する感覚、私たち人間のいわゆる五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に相わたりつつそれらを統合して働く総合的で全体的な感得力「(中村雄二郎『共通感覚論』岩波書店七頁)のことだったと言われている。
こうした共通感覚、それぞれの感覚を統括する共通感覚として想定されていたのは何であったか。そもそも五感の間で優位な位置を占めているのは、今では視覚だと思われているが、中世までは聴覚であったとされている。聴覚→触覚→視覚、という順だったというのである。「一方で、キリスト教会がその権威をことばという基盤の上においており、進行とは聴くことであるとしていたからである。聴覚の優位は一六世紀においても、神学に保障されてまだ強かった。『神の言葉を聴くこと、それが信仰である』『耳、耳だけがキリスト教徒の器官である』とルターも言っている」(前掲書五四頁)。理性は、感性や気力さらに常識に比べて、人間の能力の中で最も高次なものと見なされているが、ドイツ語の理性はVernunftであって、つまり聴解する(vernehmen)に由来することばである。ところが、「近代文明は、触覚と結びついた形での視覚優位の方向では発展せずに、むしろ触覚と切り離されたかたちでの視覚優位の方向で展開された」(前掲書五五頁)。印刷術や遠近法、機械論的な自然観は、視覚優位の文化の産物であった。印刷術は「知」の組み換えをじつげんして、遠近法は「主体」の成立を促すことになった。機械論的な自然観は自然を対象化することを通して、人間による自然の解明、克服、征服を可能ならしめた。
しかし、視覚は本当に五感の中で優位にたつ認識能力なのであろうか。この問題は実に、近世哲学を貫いた枢軸の基本問題だったのである。すなわち、私たちの外側に広がる空間において外見として見えるものは、見るだけでそのように認識されるものかどうか、ロック、バークリ、ライプニッツ、ヴォルテール、コンディヤック、ディドロらがそれぞれに解釈を加え、さらにはルソーやヘルダーなどをも巻き込んだモリヌークス問題で検討された主題である。視覚だけで認識することができるのか、それとも外界の認識に触覚の働きを無視できないのか、という論争だと言い換えてよい。先天盲の開眼手術後の認識をめぐって、球と立方体を弁別できるかどうかを実験した結果、ロックやバークリーは視覚的認識に先立つ触覚の重要性を語ったのに対して、ライプニッツは視覚の優位性を肯定的に捉えた。ディドロは触覚の重要性を認めつつも、視覚だけで見えるとしたのに対して、ヘルダーによっては空間表象における触覚の根源性が語られもした。「遠近法」による視野の主体的な構成の問題と並んで、近世哲学の枢軸をなした問題であった。
本来、共通感覚というのは、一人の人間における互換に共通する感覚のことであったが、その中の一つ、触覚を媒介として私たちは、他者や自然との共感が可能になるならば、〈心〉なるものを持ち合わせていないわたしたちにとって、まさしく〈ふれあい〉は〈心〉を感じさせ、他者との共感を結ぶものだと言えよう。もちろん〈手当て〉はそうした〈触れ合う心〉を最大限に実現するものである。
3 市民社会における道徳様式の変貌
そもそも思想史を振り返ってみるに、触覚の重要性が見直されるようになったのは、不特定多数の人々が交流しあう市民社会の成立期で、「共感」概念が新たな意味合いを帯びるようになったのも、時代を同じくしているのである。一八世紀にエジンバラの医学校の教授であったジョン・グレゴリーは、その著『医師の義務と資質に関する講義』(一七七二)において、共感概念を用いて患者の利益を最大限に考えて行動するように、美徳と関連付けたのである。
ヒュームは『人性論』でこう述べている。「かりにもし私がかなりこわい外科手術に立ち会うとすれば、確かに手術の始まる前においてすら、手術具の準備・秩序よく並べられた包帯・熱せられた手術刀・患者及び付添い人の心配と憂慮のあらゆる表徴、それらは私の心に大きな効果を及ぼして、憐憫と恐怖とのもっとも強い心持を喚起しよう。いったい、他人のいかなる情緒も直接には我々の心に現出しない。我々はただ、他人の情緒の原因あるいは結果を感知するだけである。これらから我々は情緒を推論する。従って、これらが我々の共感を生起するのである」(ヒューム『人性論(四)』岩波文庫一八六頁)。すなわち他人の心情を類推する能力のことを「共感」と呼んでいるわけである。
ヒュームは「共感」に道徳的な心情の基礎を求めている。「この同じ{共感の}原理が美的心持〔ないしは情操〕を産むのみならず、多くの場合に道徳的心持〔ないし情操〕を産むのである。〔例えば正義の徳がそうである。いったい、〕正義ほど敬重される徳はなく、不正義ほど忌み嫌われる悪徳はない」(前掲書一八七頁)。市民社会での生活においては「正義」は必要不可欠な倫理である。それは個人個人によって違っていては、正義とは呼ばれない。自分と他人の壁を超え、身内・知人・友人の枠を超えて、普遍的な価値観であってこそ初めて、正義たり得るのであるから、そのために「共感」能力が求められることになる。「我々自身の利害や友人の利害に関わりない社会的善福は、ただ共感によってのみ快感を与える。従って、共感こそ、あらゆる人為的徳に対して我々の払う敬重の源泉である道理になる。こうして、共感は人性の甚だ強力な原理であること、共感は我々の美的鑑識に非常な影響を及ぼすこと、共感はすべての人為的徳における我々の道徳的心持〔ないし情操〕を産むこと、これらの点は明らかである」(前掲書一八八頁)。
こうした共感の成り立ちをヒュームは次のように説明している。「他人の現在の不幸が私に強く影響したとする。そのとき、想念の活気は単に直接の対象に局限されない。(……)該人物のあらゆる事情について、過去と現在と未来とを問わず、可能的と蓋然的と絶対確実とを問わず、生気ある観念を私に与える。この生気ある思念によって、私はそれらの事情に関心をもち、それに参与する。そして、私が該人物のうちに想像するすべてのものに適合した共感的な動きをわたしの胸のうちに感じるのである」(ヒューム『人性論(三)』岩波文庫一六六頁)。すなわち、他人に共感するためには、それも目の前に見えない事情にまで共感するためには、相手に対する「関心」、そして自らの側には「想像力」が必要だ、というわけである。
ヒュームに連なるアダム・スミスは、その著「道徳感情論」で、たとえ「人間がどんなに利己的なものと想定されうるにしても、あきらかにかれの本性のなかには、いくつかの原理があって、それらは、彼に他の人びとの運不運に関心をもたせ、彼らの幸福を(……)彼にとって必要なものとする」(アダム・スミス『道徳感情論(上)』岩波文庫二三頁)として、そうした原理を「哀れみ(ピティ)」と「共感(シンパシー)」に見定めている。「われわれは、他の人びとが感じることについて、直接の経験をもたないのだから、彼らがどのような感受作用を受けるかについては、われわれ自身が同様な境遇においてなにを感じるはずであるかを心にえがくよりほかに、観念を形成することができない」(前掲書二四頁)として「想像力」の働きを重視している。「われわれの想像力が写しとるのは、かれのではなくわれわれ自身の、諸感覚の印象だけなのである。想像力によってわれわれは、われわれ自身をかれの境遇に置くのであり、われわれは、自分たちがかれとまったく同じ責苦をしのんでいるのを心にえがくのであり、われわれはいわばかれの身体にはいりこみ、ある程度かれになって、そこから、かれの諸感動についてのある観念を形成するのであり、(……)なにか感じさえするのである」(前掲書二五頁)。利己的でありながら、合理的な人間たちの集う市民社会にあって、個別実体たちを繋ぐ唯一の絆とも言うべきものが、この「想像力」だったと言えよう。
4 ケアの成り立ち
「共感」は、実体としての〈心〉を持ち合わせず、しかも、他者の痛みや心情を類推するしかできない私たちにとって、他者の〈心〉を想定し、かつ自分の〈心〉を表明する能力、つまり「関係論的な把握」を可能にする能力だ、と言えよう。
今日の医療の現場では、患部や病巣の治療に主眼を置く「キュア」に対して、患者を善人格的な存在として捉えて看護する「ケア」は、「キュア」が実施不可能な病状を迎えることもあるのに比して、たとえ患者がどのような状態に陥ったとしても、実行できることから、その重要性が指摘されている。
また、つぎのように、医療の実施体制の組み換えを迫るものとしても期待されている。すなわち、「ケアの倫理は、病の了解がその中心を得て、人間へと統合されることを不可欠とみなす。そうでなければ、患者中心の医療、全人的ケア、医療のうちへの人間性の回復といったことは不可能だからである。したがって、われわれは少なくとも心身統合の、そしてそこから出発すると言う意味では心身合一の医療を構想する必要がある」(松島哲久「現代医療における倫理性の復権」世界思想社刊『生命倫理学を学ぶ人のために』二一九頁)。
キャロル・ギリガンの『もう一つの声』(一九八二)は、今日の私たちの間での「ケア」を考える上で大きな一石を投じた書である。妊娠中絶と言う具体的な問題に即して女性達から聞き取り調査を実施した結果から、彼女は、男性と女性の性差に基づく「ケアの倫理」を明らかにした。つまり、道徳的な葛藤状況に陥った時に、女性は、具体的な人間関係の親密さ・疎遠さを軸に対処する傾向があるのに対して、男性は、平等・不平等を道徳の軸にすえる傾向が強いというのである。女性は人間関係を保持し、より強化する方向で道徳的な葛藤状況を解決しようとするのに対して、男性は、道徳的な葛藤を権利主張の対立と捉えて、「公正」や「自律」を重視するのだそうである。彼女はこうした女性の倫理を「ケアの倫理」と、そして男性の倫理を「正義の倫理」と呼ぶ。
正義は、人間一人ひとりを絶対的に自立した主体として捉え、「自律」に倫理の実体を求める。これに対して、ケアは、他者への共感のうえに成り立つ。その意味では、倫理性の実体論的な把握と、関係論的な把握と言い換えても良いかもしれない。正義では原理が大切で、ケアでは関係が大切だとも言えよう。正義では、相互の権利が重要視されるなかで、公正さが〈合法性―非合法性〉を尺度に測られようし、ケアでは、不均衡な関係において〈境遇の良否と慈愛の配分〉による全体としての調和がもたらされるのかもしれない。正義にあっては、普遍的な原理が支配するが、ケアにあっては、個別具体的な対処が重要視されよう。正義にあっては、利己性は合理性をまとわなければならないが、ケアにあっては、利己性は生きるという観点で許容される、など。
小括
痛みを、確かに私は感じている。そして、誰もこの痛みを共有することはできない。と言っても医療従事者は私の仕草を見て、私が痛がって、痛みに堪えかねていることを「想像」できる、ようである。どの程度の痛みであるか、まで。そのとき、痛みは私と医療従事者の関係を結ぶ形で表現されているのであろう。〈心〉も似た状況にある。私たちは実体としての〈心〉を持ち合わせてはいないようである。しかし、〈心無い〉振る舞いもあれば、〈心温まる〉言葉もある。大森荘蔵は次のように述べている。「私の『心』というものがあるとすれば、この『ここにいる私』と『そこに見える風景』が作るこの全状況が『心』であるいがいにはない。『私の内に』ある心などはどこをさがしてもないのである」(大森荘蔵『物と心』東京大学出版会七二―七三頁)。心が想定されるとすれば、それは、関係論的な観点からのみに他ならない、そして、共感やケアというものが成り立つとすれば、実態的にこれが共感だ、これがケアだ、というものはなく、むしろ、それも関係論的な観点からに他ならない。この「ここにいる私」と「そこに見える相手」が作るこの全状況にこそ、共感やケアの成り立ちが立ち現われていると言うことができよう。
【略 歴】
万代小学校三年まで新潟市、長岡高校、新潟大学人文学部哲学科を卒業、東北大学大学院文学研究科(修士課程)、神戸大学大学院文化学研究科(博士課程)を修了した後、神戸大学大学院文化学研究科助手、神戸女子薬科大学非常勤講師を経て、1991年から新潟大学教養部助教授、1996年から人文学部教授。専門は、生命倫理学、環境倫理学、近世哲学(ドイツ観念論)。
【後 記】
参加者の方から感想が届いています。
・「心の話」とても楽しく不思議な栗原ワールドに、はまりました。「心」ってほんとにどこにあるのでしょう?目に見える物が全てで、「心なんて無い」と聞かされても、ナタラジャの美味しいカレーと、楽しいお話しで、無いはずの「私の心」は、確実に元気ななりました。タージマハールの写真も宝物です。ありがとうございました。
・栗原先生のお話は、日頃私たち教師が行っている「子どもの行動の見取り」について大きな警鐘を鳴らしていただいたように感じました。とかく教師は子どもの一面のみを見て評価しがちです。しかし、今回の栗原先生のお話を伺って、子どもを様々な角度から見取る力を身に付けたり、多くの教師で一人の子どもについてディスカッションしたりしなければならないと感じました。これからの勉強会がますます楽しみです。
・私の勉強不足ということもあり、難しかったような気がします。ただ痛感させられたのは、先生もメールに書かれていましたが、「こころ」は受け取り側の問題でもあるということが、すごい印象に残りました。今まで、『こちら側が「こころ」を開いているのに、相手が壁を作ってしまって、「こころ」通じ合わすことができない。』と思っていたのは、実は自分の中で、勝手に「こころ」開いていると思い込んでいただけで、実は、私の方が「こころ」開いていないと思っていたのかもと、改めて反省しております。
報告:第80回(2003-01)済生会新潟第二病院眼科勉強会 宮坂道夫
演題:『ファミリーハウス』
講師:宮坂道夫(新潟大学医学部准教授)
日時:平成15年01月08日(水) 16:30 ~ 18:00
場所:済生会新潟第二病院 眼科外来
【抄 録】
(1)ファミリーハウスの紹介
「にいがたファミリーハウスやすらぎ」は、新潟市内の病院に入院する患者さんの付き添いをされる家族のための滞在施設です。善意の方からお部屋を提供していただき、市民、企業、団体などの支援を受けて開設されました。各病院の理解、協力のもと、「にいがたファミリーハウスやすらぎ支援の会」が責任をもって管理、運営しています。入院したその日からすぐにご利用できます。これまでご利用いただいた方からは、「ゆっくり手足をのばせるその事が、とても有り難かったです」、「夜すべてを終えてこのハウスに帰り、ホッとした心のやすらぎは、何ものにもかえがたいものでした」などの声が寄せられています。(以上、当会のパンフレットより)
*詳細については、ホームページがありますので、そちらをご覧いただくのがよいかと思います。アドレスは以下の通りです。
http://www.ng-familyhouse.npo-jp.net/index2.html
(2)今回の話のあらまし
1)ファミリーハウスとは?
病院中心の医療制度のもとでは、効率よく治療が行われ一方で、「治療やケアの場」と「生活の場」が隔絶しがちになります。病院や医療施設という特別な場所へ、家という普段の生活の場を離れて、治療のために「移住」しなければならないわけです。特に慢性疾患中心の現代では、この隔絶は患者とその家族にとって深刻な問題を生んでいます。専門的な治療を受けられる病院に、家を遠く離れて入院しないといけないことも多い。しかも療養には長い時間がかかる。その間、患者と付添の家族は、生活の場から離れて過ごさねばならず、生活の上で非常に負担がかかってくることになります。例えば宿泊はどうするか、子供の教育はどうするか、お金はどうするのか ・・・。
残念ながら、日本の保健医療制度ではこうした面まではカバーしきれていません。そこで、ファミリーハウス活動が始まったわけです。「病院」の近くに、「家」に近いものを作り、そこで患者をささえる付添者のために「生活の場」を提供しようというアイデアです。ただし、一口に「ファミリーハウス活動」といっても、宿泊・滞在施設の提供だけのところもあれば、相談事業を展開しているところもあり、さらに幅広いサービスを提供しているところもあり、その実態はとても多様なものです。
2)新潟でのファミリーハウス活動
児玉義明・にいがたファミリーハウスやすらぎ支援の会・会長から、会の立ち上げ、実際の運営などについてお話させていただきます。これまで多くの方のご協力により、民間アパートの部屋を借りて、ハウスを運営しています。利用された方からはとても感謝されている活動ですが、マンパワー不足、一般市民の関心の低さなど、克服しないといけない問題もあります。
【後 記】
私が始めて「ファミリーハウス」を知ったのは、昨年(2002年)9月29日「にいがたファミリーハウスやすらぎ支援の会」主催の『第1回命(いのち)のシンポジウム』でした。
宮坂道夫先生(新潟大学医学部保健学科;当時講師、1月1日より助教授)がコーディネーターをされ、児玉義明氏(にいがたファミリーハウスやすらぎ支援の会会長、新潟大学での生体肝移植を受けた第一号)の講演がありました。遠方から入院されている患者家族のために宿泊施設を低料金で提供という、とても素敵なアイデアでした。世の中にこんなことに頑張っている方がいるのかと、感動しましたし、新鮮でした。
今回、当勉強会でもお話して頂くよう宮坂先生にお願いしたところ、快くお引き受け頂き、またにいがたファミリーハウスの会員の方にも参加を呼び掛けて頂きました。さらに私にとって嬉しかったのは、難病を抱えながらもほのぼのとした心癒される色鉛筆画を書き続けている羽田沙織さん(白根市在住)にも参加頂いたことでした。
宮坂先生の講演で「ファミリーハウス」について説明して頂きました。ヨーロッパでの状況、日本での状況(1988年に大阪で最初に開設)、そして新潟での現状と課題。必要なのは、施設、資金、労力、そして何よりも必要性の認識。白山駅近くに2001年7月に開設。以来利用料1500円という低料金で頑張っているとのことです。全国的には国や自治体の支援を受けているところ、病院と直結しているところ、企業から支援を受けているところなどあるそうですが、新潟の場合、運営は全てボランティア。
終了後会場からは、素晴らしい事業であるという賞賛と同時に、いくつも質問がありました。この料金でペイは大丈夫か?これは病院なり自治体で頑張ってもらうべきものではないのか?ボランティアだけでは大変なのでは?米国では病院の周りに安い宿泊施設がありその負担は患者がするが、、、。患者自身の利用や、外来通院への利用は可能か?宣伝が少ないような気がする、、、、、。ニーズの掘り起こしが必要では?インターネットでの申し込みは出来ないのか?全国的な連絡網はないのか?そもそも子供が長期間家族から離れて暮さなければならない入院治療に問題があるのでは、、、、等々。
宮坂先生はじめ、にいがたファミリーハウスやすらぎ支援の会の皆様、ありがとうございました。
報告 特別企画“新潟盲学校生徒による弁論大会イン済生会”
日時: 平成14年11月1日(水) 16:00~17:30
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
1)「私を支えてくれる人」 片岡恵子 高等部普通科3年生(佐渡)
2)「『自分に勝つ』とは」 加藤俊一 高等部普通科3年生(豊浦町)
3)「障害者スポーツとの出会い」 石浦智美 中学部3年生(上越市)
===============================
1)「私を支えてくれる人」 片岡恵子 高等部普通科3年生(佐渡)
今年度3年生で佐渡相川高校から盲学校に転入。30数名のクラスから4名のクラスへ、そして寄宿舎では二人一部屋の生活。入学早々、人間関係でトラブルが生じた。母には優しい気持ちで人に接することと教わっていた。そして自分では自分のことを主張しないことが他人に対する優しさと思っていた。しかし、人に良かれと思ってやったことでも、人を傷つけることがあるということが今回のトラブルで判った。今では自分が素直になることが大事だと感じるようになった。
*とても母親想いの優しい生徒でした。将来は針灸師を目指すとのことです。
2)「『自分に勝つ』とは」 加藤俊一 高等部普通科3年生(豊浦町)
柔道の大会で負けた。がっかりしていた時、先輩(53歳)が悔しかったら、毎日一緒にトレーニングやろうかと言ってくれた。朝食後の20分間、ランニング、腹筋、背筋、腕立て伏せをこなしている。毎日やるのは大変だ。でもその先輩は自分のことを真剣に思ってくれている。自分に勝たないと力がつかない。楽をして自分を高めることは出来ない。一つの事に打ち込むことで「心のエネルギー」を蓄えたい。毎日トレーニングを続けることで、体力がついた、周囲のに応援してくれる人が出来た、何事にも積極的になれた、そして何よりも自分自身が変わってきたことを実感出来るようになった。
*好感の持てるスポーツマン。来年からは筑波に進学して勉強を続けるとのことでした。
3)「障害者スポーツとの出会い」 石浦智美 中学部3年生(上越市)
小学校入学前から水泳を続けていた。小学校2年生の時、眼底出血が起こり眼科医から水泳を禁じられた。ショックだった。他人に抜かれてしまうと思い、辛かった。一年後、水泳を許されてホッとした。小学校5年の時、視力が悪いということで水泳大会に出場出来なかった。悔しかった。別な大会で先生にリレーの選手に選んでもらえた。入賞することが出来た。嬉しかった。選んでくれた先生には今でも感謝している。身体者障害者競技会では黒く塗ったゴーグルをつけて泳いだ。スポーツを通じて色々な人と出会えた。スポーツは障害のあるなしにかかわらず楽しみと励ましを与えてくれる。
*昨年に続き連続弁論大会の新潟盲学校代表に選出!今年の新潟市の中学生弁論大会で2位入賞(1位は全国大会で入賞)、今年のジャパンパラリンピックの水泳大会(大阪)では銀メダルを獲得。どこにそんなエネルギーがあるのかと思うほど、物静かな少女でした。
報告:第76回(2002‐9月)済生会新潟第二病院 眼科勉強会 清水美知子
日時:2002年9月11日(水)16:00~17:30
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
演題:「Coming out —-人目にさらす」
講師:清水美知子 (信楽園病院視覚障害リハビリ外来担当)
【抄 録】
視覚障害を持つ自分を世間はどう受けとめるのか?自分の記憶の中にある視覚障害者は、杖を突いて、黒メガネをかけて、電柱や自転車に当たりながら歩いていた。自分もあのようになるのだろうか。世間の人の目に自分はどう映るのだろうか。
世間は視覚障害を持つ人に好奇の眼差しを注ぎ、蔑み、憐れみ、無関心、同情、冷淡、お世辞など様々な心情を示します。世間の人にとって視覚障害者は珍しいのです。視覚障害者と言葉を交わしたことがないのです。視覚障害者に「テレビを見ますか?」と尋ねることを躊躇するのです。ひとりで歩く視覚障害者を見て、「カンがいい」で簡単に片付けてしまいます。「眼が見えないのに明るい」と驚きます。視覚障害者は「点字が読める」と思っています。断ってもついてくる不要な手助け、呼び掛けに応えない群集、ガイドに自分の体調をきく看護婦、入居を拒む大家など、世間には無知、無理解、人権軽視の態度があふれています。
coming out はこのような世間へ踏み出すことです。視覚障害を持つ自分をさらし、人々の反応を見るのです。そして新しいセルフイメージを確立していくのです。世間の視覚障害者のイメージに挑戦するのです。既存の鋳型にはめようとする世間と、ひとりの人間として生きようとする者の衝突です。
【略 歴】
1976 歩行訓練士
1979 ~ 2002 江南施設施設長
1988 信楽園病院視覚障害リハビリテーション外来担当
【後 記】
今回は人気の清水美知子先生が講師だったため、いつもより多くの40名を越える(当院の職員を含めると50名を越える)方が参加されました。巻町の団体、西川町からの団体、信楽園病院パソコン教室の皆様等々、今回始めて参加された方も大勢いらっしゃいました。外来の視力検査のスペースを利用しているものですから、会場はそんなにひろくはありません。清水先生と一番近い方は、わずか80cmくらいのところでの聴講でした。場所の狭さと、話の面白さで熱気むんむんの勉強会でした。
「Coming out かみんぐ-あうと」を、人目にさらす、自分になると定義して講演は始まりました。障害者が世間からどうみられているか、医療福祉関係者はどう見ているか、ボランティアに問題はないか、障害者は必要以上にへりくだっていないか、自分を見えにくくしているものは何か、障害者が自分を出そうとする時に衝突する世間の期待している障害者像、、、、、、等々。最後に、世間を変えるためには自分を変えることが重要と結びました。
講演終了後の質疑でも「白杖歩行に抵抗がある」「障害者の方を手助けしたい時に、声を掛けられなかった」「今までモヤモヤしていたものをはっきり言って貰った」「世間よりも家族との関係が難しい」等々、多くの声を聞きました。本当にいろいろと考えさせられる勉強会でした。
報告:第70回(2002年3月) 済生会新潟第二病院 眼科勉強会 宮坂道夫
演題:NBM(narrative based medicine)
-物語論の観点から医療をとらえなおす-
講師:宮坂道夫(新潟大学医学部保健学科講師)
日時: 平成14年3月13日(水)16:00~17:30
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
【講演要旨】
1. 〈物語〉の広がり
NBM(narrative based medicine=「物語に基づく医療」)というものが最近注目されるようになってきている。これは何か。特にその核心部分である〈narrative=物語〉とは何だろうか。この基本的な問いに答えるのは、実はたいへんに難しい。物語という語は、最近では人文・社会科学の広い領域で使われており、しかもその意味内容は実に多様である。昨年お話をうかがう機会のあった、この分野に造詣の深いある哲学者は、物語という言葉は使う人によって意味が違うと言っておられた。文献を眺めていると確かにその通りで、姿形の異なる樹木が立ち並ぶ雑木林に踏み込んだような気になってくる。それでも、物語という言葉の定義よりも、それを使おうとする人たちの動機や関心の流れを追ってゆくと、何となくではあるが、この語が医療も含めた幅広い分野で使われるようになってきた理由が見えてくるように思う。
医療者が関心を抱く物語とは、患者が病や実人生について語る〈生の物語=life narrative〉である。しかし、物語という言葉を聞いてまず思い浮かぶのは、『源氏物語』のような文学作品としての物語の方だろう。患者の語る物語と文学フィクションとではまったく別物に思える。しかし、両者をよくよく比べていくと、実はそんなに大きな違いはないことがわかってくる。どちらも始まりがあって、終わりがある。語り口は様々だが、様々な出来事の叙述がある。患者の物語も文学作品も、例えばカルテのような〈事実の記述〉以上の情報を含んでいる。そこに登場する人々がとった行動だけでなく、その時に何を見て、何を思ったかが語られる。〈語られないこと〉もある。何を語り、何を語らないかを取捨選択するのは、患者であり、作者である。
このような類似性は、文学研究の一領域である〈物語論=narratology〉では、もはや当然のこととして受け入れられている。たとえば、ジュネットによれば、物語とは・物語内容(イストワール)(語られた出来事の総体)、・物語言説(レシ)(それらの出来事を物語る、発話されるか書かれるかした言説)、・語り(ナラシオン)(語るという行為そのもの)という三つの側面を持っている。『源氏物語』といえば、私たちはその話の内容(物語内容)にばかり注目しがちだが、語り手と聴き手の存在や、語り聴くという行為、および物語を伝える媒体にまで視点が拡大しているのである。
2. 〈物語〉の背後にあるまなざしの転換
このような視点の拡大は、現代思想の潮流と深く関係している。その潮流をあえて一言でいうならば、〈正当なものとして権威づけられ、固定されたまなざしの正当性への疑問〉といえるように思える。たとえば、「正常者」と「異常者」の線引きへの疑問(フーコー『狂気の歴史』)、「世界の中心」である西洋社会と「辺境」である非西洋社会という世界認識への疑問(レヴィ・ストロース『悲しき熱帯』)、政治や経済の歴史を「正史」と見なして普通の人々の生活史を記述しない歴史認識への疑問(アリエス『死を前にした人間』)というように。こうした思想家たちは、従来は顧みられることもなかった「普通の」(あるいは「異端の」)人々がそれぞれに生きている固有の〈生の物語〉の中に、人間や社会の真実を見いだそうとした。フーコーは精神病患者を長年にわたって観察し、レヴィ・ストロースは文明化されていない部族の中に入って生活を共にしながら彼らを観察した。アリエスは「日曜歴史家」と自称して、一般大衆の日記などを収集した。彼らに共通しているのは、現実は単なる科学的事象とは違って、その現実を生きる人それぞれの視点によって異なったものであり、さらにそれが語り手から聴き手へと語られることで、意味づけられ、解釈され、形づくられてゆくものだという認識である。
3. 医療における〈物語〉
このような流れから考えれば、NBMの位置づけも見えてくる。NBMはしばしばEBM(証拠に基づいた医療)との対比で語られる。これは、NBM自体に、「〈患者〉ではなく〈病気〉を見る」という近代医学のまなざしへの反省が込められていることをあらわしているように思う。医学的データからは最適な治療法でも、患者にとってはそうではない場合もあるかもしれない。たとえば、医学的適応だけでなく、患者のQOLを視野に入れて治療やケアの方法を選択することは、今日では当然のこととされているはずだが、QOLの評価は「証拠に基づいた客観的評価」だけでは不可能であり、個々の患者に固有の価値観に基づいて評価すべきものである。したがって、医療者は、患者個々の生のなかで抱かれている価値観を知るために、患者個々の生の物語に耳を傾けざるをえない。そこからNBMが始まる。
これは患者の立場からすれば歓迎すべきことで、まさに「患者中心の医療」の実践にほかならない。しかし、医療者の側にとっては必ずしも簡単なことではない。NBMを誠実に実践しようとすると、一つの難問に悩ませられることになる。それは、物語をどう評価し、解釈し、理解すればよいのかという問題である。患者の物語に耳を傾けること自体はよいとして、その物語をどう捉え、臨床判断にどう反映させてゆけばよいのか。たとえば容易に想像がつくリスクは、患者の物語を、医療者の都合や偏見によって過度に単純化してしまったり、「いかにもありがちな」ステレオタイプなストーリーに当てはめてしまうことであろう。「患者の物語」が、いつの間にか「医療者の物語」に作りかえられてしまう。こうしたことを避けるにはどうしたらよいのか。
この難問に取り組もうとしているのが、早くから物語を積極的に利用してきた領域、つまり精神医学、臨床心理学だと思う。この領域では、患者の物語を語り聴くことそのものがケアとして成り立っている。医療者は患者の物語を、患者自身が語ったり、意味づけたりするのを促したり、手助けしたりする。ここで紹介することはできないが、どこまで患者の物語に立ち入るべきか、どのような価値観に基づいて意味づけを促すかについて、すでに様々な議論が行われている。
むろん、一般の医療では、患者の物語をめぐって、ここまでの働きかけをする必要はあまりないのだろう。それでも、患者の物語を基礎に置いて、そこから何らかの臨床判断をしてゆくのであれば、医療者は自分の立場を決めなければならないようにも思う。「事実は小説より奇なり」というように、患者の物語は文学フィクション以上に複雑な、深い森のようなものである。それを外から眺めているのか、そこに分け入ってゆくのか。黙って「森の声」を聴いているのか、それとも何らかの働きかけをするのか。このような問いかけをしてゆくことが、NBMの本質として求められるような気がする。そして、このような問いかけを深めてゆくと、患者の側だけではなく、医療者の側にも各人に固有の〈生の物語〉があることに突き当たるのではないだろうか。NBMとは、そうした気づきの上に成り立つものであってほしい――これは筆者の素朴な感想にすぎないが。
NBMはしばしばEBM(証拠に基づいた医療)との対比で語られる。これは、NBMに、「〈患者〉ではなく〈病気〉を見る」という近代医学への反省が込められていることをあらわしている。医学的データからは最適な治療法でも、患者にとってはそうではない場合もある。医学的適応だけでなく、患者のQOLを視野に入れて治療やケアの方法を選択することは、今日では当然のはずだが、QOLの評価は「証拠に基づいた客観的評価」だけでは不可能であり、個々の患者に固有の価値観に基づいて評価すべきものである。
したがって医療者は、患者個々のなかで抱かれている価値観を知るために、患者個々の生の物語に耳を傾けざるをえない。そこからNBMが始まる。これは患者の立場からすれば歓迎すべきことで、まさに「患者中心の医療」の実践にほかならない。しかし、医療者の側にとっては必ずしも簡単なことではない。「患者の物語」が、いつの間にか「医療者の物語」に作りかえられてしまう事がある。こうしたことを避けるにはどうしたらよいのか、、、、、
【略 歴】
早大卒業後、阪大で修士、東大で医学博士を取得。
現在は新潟大学医学部講師。生命倫理・医療倫理の専門家。
第66回済生会新潟第二病院眼科勉強会 竹本吉夫
演題:「病気と共存の健康―持病息災―」
講師:竹本吉夫(秋田赤十字病院名誉院長)
日時: 平成13年11月21日(水)16:00~17:30
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
今回は、秋田赤十字病院名誉院長である竹本吉夫先生に「病気と共存の健康」というテーマでお話して頂きます。
竹本先生は昭和24年新潟医科大学卒業、昭和27年新潟大学医学部第一内科入局、昭和40年新潟大学助教授、昭和42年秋田赤十字病院長・秋田赤十字看護専門学校長、平成8年より赤十字病院名誉院長、日本赤十字秋田短期大学初代学長として活躍され現在に至っておられます。
今回は「病気と共存の健康―持病息災―」と題し、以下の項目をお話して頂きます。Ⅰ健康長寿”は可能か、Ⅱ医療とは何か、Ⅲセルフケアのキイポイント、Ⅳ“痴呆”をどう防いだらよいか、Ⅴ“老後の不安”にどう対処するか-高齢者の楽園構想-。
わが国のオピニオンリーダーの一人でもあり、国際的にも活躍中の先生の、医師として患者としての豊富な経験からの貴重なお話を伺える機会だと思います。
今回もご期待下さい。多くの皆様の参加をお待ちしております。
【講演レジメ】病気と共存の健康―持病息災―
Ⅰ.“健康長寿”は可能か
①健康とは ②秋田県民の健康の実態 ③ヒト・人間の一生と私の病気体験
Ⅱ.医療とは何か
①人間とは何か ②ヒト・人間の病気の3視点 ③医療の3つの考え
Ⅲ.セルフケアのキイポイント
①健康習慣と危険因子 ②カクシャク百歳老人の生活実態 ③大友式ボケ予測テスト
Ⅳ.“痴呆”をどう防いだらよいか
①痴呆は果たして病気か ②脳老化防止法 ③ボケない小唄とボケます小唄
Ⅴ.“老後の不安”にどう対処するか-高齢者の楽園構想-
総務庁調査(1999年);自分と配偶者の健康・病気68.5%、要介護状態52%、生活のための収入26.3%、一人きりで頼る人がいない20.3%、子や孫の将来16.4%。
【略 歴】 竹本吉夫
大正14年(1925年) 5月26日生
昭和18年 3月 旧制県立新潟中学校卒
昭和20年 3月 旧制新潟高等学校理科乙類卒
昭和24年 3月 新潟医科大學卒
昭和27年10月 新潟大学医学部第一内科入局
昭和33年 3月 医学博士
昭和40年10月 新潟大学助教授
昭和42年10月 秋田赤十字病院長・秋田赤十字看護専門学校長
平成 8年 4月 秋田赤十字病院名誉院長
日本赤十字秋田短期大学初代学長、現在に至る
【後 記】
期待通りスケールの大きい、判りやすい、テンポのある、素晴らしいお話でした。会員の評判も上々でした。これだけのお話をされるのには、大変な準備が必要としたのではないかと思います。ありがとうございました。
「老年期こそ人生の完成期、奉仕の時期」「音楽療法」「病因として、遺伝・環境・ライフスタイル・加齢」「宗教」「全人的ケア」「医療には限界がある」「人生の質、いのちの質、生活の質」「健康習慣」「セルフケアの重要性」「ボケ防止法」「ジェロントピア」。どの話題ももっともっと聞いてみたい話題でした。竹本先生の人生と人生観を教えて頂きました。
報告 第64回(01-09)済生会新潟第二病院眼科勉強会
“新潟盲学校生徒による弁論大会イン済生会”
日時: 平成13年9月12日(水) 16:00~17:30
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
1)「住みやすい環境づくり」 石浦智美 中学部2年
2)「障害者に優しいものの開発を」 酒井久美子 高等部普通科3年
3)「素直に生きる」 曽我加奈子 高等部専攻科3年
===============================
1)「住みやすい環境づくり」 石浦智美 中学部2年
ニュースで駅のホームから転落する事故が相次いだことをきっかけに、道路の縁石など身の回りの環境に目を向けて、住みやすい環境整備への配慮を呼び掛ける・・・・。
*中学部の友人たちといつも楽しそうに会話して、笑顔の絶えない中学2年生。水泳の実力は並外れ、プールの中ではイルカのように泳ぎます。
2)「障害者に優しいものの開発を」 酒井久美子 高等部普通科3年
購入したMDがブラインドタッチではとても使いづらいという体験を通して、各メーカーで統一された使いやすい規格を整えるなど、障害者にも配慮された物作りを呼び掛ける。
*フロアバレーボールのエースアタッカー、アタックの威力は北信越でもナンバーワン。万代太鼓クラブでも大活躍で、天まで届く掛け声がとても魅力的です。
3)「素直に生きる」 曽我加奈子 高等部専攻科3年
ストリートミュージシャンとふれあう機会を通して、次第に視覚障害というバリアが薄れ、周囲の人と積極的にかかわることができるようになってきた自分自身の意識の変化を表現する。
*専攻科の紅一点、盲学校では白衣姿で理療の実習などをがんばっています。フロアバレーボールの中心選手として大活躍し、北信越大会で新潟盲学校を優勝に導きました。
報告:第62回(2001‐7月) 済生会新潟第二病院眼科 勉強会 栗原 隆
演題:「医療資源の配分と正義」
講師: 栗原 隆(新潟大学人文学部教授)
日時: 平成13年7月11日(水) 16:00~17:30
場所: 済生会新潟第二病院 眼科外来
【抄 録】
今回は新潟大学人文学部教授の栗原隆先生に、「医療資源の配分と正義」をして頂きます。先生には以前(98年12月)「インフォームドコンセントと医者と患者の関係」というお話をして頂いたことがあります。先生に要約を頂きました。・・・お医者さんにしても看護婦さんにしても、病床、お薬、みな稀少資源であって、そこにいかに配分するべきか(配分における正義)という問題が生じてきます。その基準を幾つか検討するとともに、、、そうした正議論を乗り越える形でていきされた「ケアの倫理」と「ローカル・ジャスティス」の構想について瞥見したいと思います。・・・先生の専門は、生命倫理学、環境倫理学、近世哲学(ドイツ観念論)で、医学部5年生の生命倫理の講義も担当されています。講義の達人でユーモアを交えて判りやすくお話しして下さいます。
【略 歴】
1951年生まれ、万代小学校三年まで新潟市にて育つ。
高校は長岡高校、その後、新潟大学人文学部哲学科を卒業、
東北大学大学院文学研究科(修士課程)、神戸大学大学院文化学研究科(博士課程)を修了した後、神戸大学大学院文化学研究科助手、神戸女子薬科大学非常勤講師を経て、
1991年から新潟大学教養部助教授、
1994年に人文学部に移籍、
1996年から教授。
専門は、生命倫理学、環境倫理学、近世哲学(ドイツ観念論)
【後 記】
参加者から感想が届いていますので、以下に記します。
・貴重な講演を聞かせて頂き,ありがとうございました。「資源の配分」の問題は,教育の世界にもケア・マネジメントの理念が導入されることになり益々重要なテーマになってきました。今一度,「時間」ではなく「正義」というキーワードから「教育の資源配分」について考えてみたいと思います。
・今回のお話の内容は、私には難しすぎたように思いますが、大学の先生のお話を聴く・・という機会はほとんどないので、とても新鮮な感じがいたしました。今現在、「医療」にそれほど近い場所にいるわけではないので、講師の方のお話を真に理解することは私にはできませんが、今子供の幼稚園の父母の会の役員をしていまして、園の少ない駐車スペースをどのような形で利用していくか・・・ということを話し合っているところなので、”local justice”という言葉がとても強く印象に残りました。
父母の会として、少ない駐車場の管理をきっちりして行こうという意見が出たのですが、かえって反発を招くのでは・・・と懸念する声をもあり、そんなことでいろいろ頭を悩ませていたところに、「全体的な管理・規制ではなく、・・・・自律を尊重し、市民の間から生まれる声に耳を傾けるところに、多元的正義論への一つの道を見出すこともできよう・・」というレジメの文章がすぅーっと入ってきました。
「なに、ピントはずれのことを言ってるんだ・・・」というお声が聞こえてきそうですが、普段の、自分の生活圏内を抜けて違った世界に出ると思わぬ発見がある・・・ということをとても強く感じました。